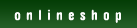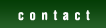知識人の役割
本日見た2本はどちらも立ち見。かなりの盛況ぶり。メイン会場である中央公民館ホール以外は朝から席を取らないと座れない。なので朝この日記を書いていると、間に合わない。でも人がたくさん来ることはいいことだ。自分が見たい(聞きたい、食べたい)ものは、ひとりでも多くの人間に見せる(聞かせる、食べさせる)こと。資本主義社会の基本ストラテジーだ。
ということで、アジア千波万波の1本、ユフィク『溺れる海』。インドネシアのスガラアナカン潟は、年々陸地に浸食されていっている。風に乗って運ばれてくる成長の早い植物の種が沈泥(シルト)を形成し、海が陸になる。そこで漁業を営んできた人たちが、農業に転職したりしていく。
かつてあったものがなくなること、その結果の記録である作品は同時に、なかったのにできたものをどう扱うのかという問題に直結する。海の消滅という現象は人為的なものではない(はずだ)が、その結果新しく出来上がった土地は、所有と管理という極めて人為的な問題を呼ぶ。海の住民が陸の住民になっていくと同時に、家の登記やよそものの存在といった限られた土地に対する争いが生じる。その入り組んだ事象に対する監督の距離感と人々に向けられるまなざしにはだいぶ好感が持てた。それと事情はよくわからなかったが、人々の口から「刑務所の役人」という単語が漏れるのが印象に残った。
その後、ワン・ビン『鳳鳴ーー中国の記憶』。ひとりの女性がその半生を一息に語る。フィックスで据えられたカメラの前で淀みなく語られる物語は、時に淡々と、時に情熱的になりながら、聞く者の耳を捉えてやまない。上映後のティーチインで監督が語っていたのは、「彼女が語ることを、ある事件の証言として撮りたかったのではなく、彼女が物語るという行為も含めた彼女自身を撮りたかった」ということだった。夕暮れ時のだんだん暗くなっていく室内、もうほとんど何も見えないくらいぼんやりとした薄闇の中で、彼女の言葉が目の前にスペクタクルを展開させる。誰もが思い浮かべるのではないかと思うが、まさにジャン・ユスターシュ『ナンバー・ゼロ』を髣髴とさせる。私がその映画を見たのは、ワン・ビンの『鉄西区』が上映された年のこの映画祭でだった。
「彼女の世代のアーティストは最も重要な存在であり、他の世代はその足元にも及ばない」、「彼女と話すことで、知識人がなすべき役割について考えさせられた」。そう語る監督の言葉は力強い。これまで見たコンペ作品の中では別格の感があるが、この作品と競合しうる作品をもっと見たいというのが正直な感想だ。
魔女のダンス、革命の歌、母親の写真
スケジュール調整と体調管理の悪さのせいで、今回の山形国際ドキュメンタリー映画祭は3日目からの参加。例年より暖かい気候がありがたい。最初の映画はジャン・パンルヴェの短編作品8本。勝手に決めた山形国際ドキュメンタリー映画祭2007サントラvol.1、ヨ・ラ・テンゴ『Sounds of the Sounds of Science』をポータブルCDプレーヤに入れて出かける(ちなみにvol.2はヤング・マーブル・ジャイアンツ『コロッサル・ユース』)。2001年4月のサンフランシスコ・インターナショナルフェスティバルでジャン・パンルヴェの作品が上映された際に、その映像の前でヨ・ラ・テンゴが演奏を行い、その曲をスタジオ録音したものがこの作品。収録曲と今回の上映作品も重なっている。
ということで、週末といえどほとんど人影の見当たらぬ駅前通を意気揚々と横切って向かったはいいが、会場であるフォーラム4はかなりの混雑振り。それもそのはず、このプログラムの2度目の上映はペドロ・コスタ『コロッサル・ユース』の上映とかぶっているからだ。立ち見にはなるだろうなとは思っていたが、立ち見でも最後の一席だった。と、最初の上映でそんなことがあっただけに、今年はなんか例年よりいっそうの盛り上がりをみせてるんじゃないかと思ってしまう。
件のヨ・ラ・テンゴのCDのこともあって、なんとなく静謐な深海の映像を漠然とイメージしていたパンルヴェ作品だが、予想とは裏腹に音と運動にみちみちた映画だった。代表作である『タツノオトシゴ』のダリウス・ミヨーはじめ、デューク・エリントン(!)やらピエール・ジャンセンといった人々を起用した音楽は、映像とともに彼の作品を決定付ける大きな要素となっている。タツノオトシゴやコウモリ、エビや貝を見つめるまなざしは、その形と動きとを人間の動きに重ねあわせるユーモラスなものだ(『タツノオトシゴ』の反復される「不安そうで落ち着きの無い目」)。しかしそこにジャズや、現代音楽や民俗音楽めいたサウンドトラックが重なり、同時に映像が対象を解剖し(『タツノオトシゴ』)分解し(『ウニ』)拡大(『液晶』)していく間に、断片や部分が全体の形態からは独立してそれ自体の「かたち」をあまりにも印象強く見せつけはじめる。それは、人間以外の生物を人間に近づけてみせるという擬人法のユーモアに似たものでありながら、人間の視点を超えたものに触れる作業でもある。彼が製作した『四次元』の中で、二次元の世界に落とし込まれ影だけの存在となったネズミに人間がイタズラする一方で、もし四次元の存在がいればそれと同じ事を人間にもできるということが戯画的に描かれているように。
それにしても『アセラ、あるいは魔女の踊り』で繰り広げれる、何の変哲もない浜辺に暮らす貝たちのダンスには、もうただ目を奪われてしまう。
その後、インターナショナルコンペティションの作品を。『革命の歌』『M』の2本。
ヨウコ・アートネン『革命の歌』は、1960年代後半にフィンランドで盛り上がりを見せた、社会主義的な歌詞のポップソングを歌ういくつかのグループの元メンバーたちにインタヴューを行う。冒頭、「あなたはどちら側か」という扇動的な歌詞の歌で幕を開ける。広場のようなところで女の子がカメラを向いて歌っている当時のビデオクリップ(?)に、40年後の今、同じ歌を歌う彼らの姿がつながれていく。サウンドだけならイェ・イェとかそんなのに近い。
インタヴューの合間にそれぞれのグループの曲が挿入されつつ映画が展開する。その時に必ず、年老いた今同じ歌を歌う彼らの映像がいかにもMTV的PV風な照明や演出で使用されているのだが、それも受容する環境が根底から変化したことを示すのだろうか。「どちら側」の音楽であれ、われわれはお構いなしに受容する。
時代とともにサウンドも歌詞も変化していく。歌詞が抽象的な理想や社会を変化させよう!というものから、銀行が金を貸してくれないとか、石油会社の横暴なやり口を訴えるという生活に密着した内容になるにつれ、サウンドもサーフ・ロックっぽい要素を取り入れていったりする。商業的なドキュメンタリーのフォーマットにおいてもよくできている。なんにしろ、パンクな人々が語り、音楽がたくさん流れるとそれだけで楽しい。
ニコラス・プリビデラ『M』は、軍事政権下のアルゼンチンで行方不明になった母親の行方を捜し求める監督のセルフ・ドキュメンタリー。冒頭の失踪した母親の写真を並べているイメージや音の処理などに期待を感じるが、見続ける間にどうしても違和感が募ってくる。ひとつの激しい時代、その過酷さゆえにだれも言葉を用いようとしないような時間を、いかにして現在や将来に継承していくのか、こうした問題体系を考える際に私がどうしても思い出さざるを得ないのはリティー・パニュの『S21 クメール・ルージュの殺人者たち』である。彼がこの映画に持続させている峻厳さを考えると、監督自身がひとりの俳優として直接に記憶や記録の不在を嘆き糾弾するというやり方に疑問を感じざるを得ない。もちろん彼は実際にこの問題を一歩前進させているのであり、その活動は評価されるべきだが、その活動をいかに記録するかというのはまた別の問題体系から捉えられるべきだろう。
監督のニコラスさんのお母さんはほんとうにきれいな人で、だからこそ彼女のイメージを単に失われた記憶の奪還の象徴に還元してしまうのはどうも納得がいかない。それこそロラン・バルトの言うプンクトゥムのような何者にも還元不可能ななにかが、まるで女優みたいだなと思ってしまうあの美しい母親の写真の中にはあるはずで、それと社会に対する政治的な活動の部分とをもっと厳密に取り扱うことによって、私にとってあの写真が唯一無二の不可欠な映像になりえたのではないかという気がしている。