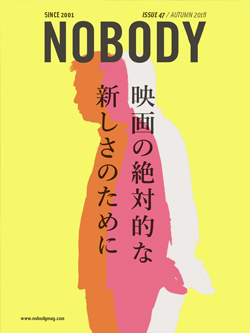EDITORIAL
NOBODY47号は、現代日本映画の特集であると同時に「映画の新しさ」についての特集である。
もちろん、映画とは常に新しいものである、とも言えるかもしれない。そもそもの誕生からして、映画は人々にとって新しいものとして驚きをもって迎えられた。映画史を俯瞰してみれば、新しさが獲得された瞬間がままあるのも事実である。それは、D.W.グリフィスがクロースアップを発明した瞬間かもしれないし、ロベルト・ロッセリーニが戦後の瓦礫の中で映画をつくり始めた瞬間であるかもしれない。それこそ1950年代末のパリでそれまでの映画を再審する形で映画づくりを始めたヌーヴェル・ヴァーグが現れたことでもあるかもしれない。さらには、そうしたよく知られる大きな映画史の外側に、ロベール・ブレッソン、ジャン=リュック・ゴダール、ストローブ=ユイレ、マノエル・ド・オリヴェイラといった映画作家たちが孤独に探求した結果として生まれたものもある。これら固有名詞はいくらでも交換可能で、至るところに新しさは生み出されていた。
そういった映画に絶えず訪れていた新しさを私たちは本を読み、名作と呼ばれる映画を追いかけることで知っていった。つまり、映画史の流れや進歩史観を俯瞰的にみることで知りえるような。だが、今号の特集が「映画の絶対的な新しさのために」と付けられているのは、それに匹敵するほどの新しさが実感を持って感じられたからだった。その新しさとは同時代に生きているからこそ感じられるようなものだ。これらの映画に触れることではっきりと同時代に生きている喜びがあった。私たちは新しさの中にいる! おそらくこの号の編集中に感じたのはそのような感動の連続だった。
そのことをより明確にするために、NOBODYをつくってきた上で実感してきた新しさを少しだけ振り返ってみたい。
NOBODYが創刊された2001年とは、それまでのフィルム制作からデジタルでの制作へと移行する過渡期であった。デジタルカメラとノンリニア編集があることで映画制作は容易になった。だが、いまになって思えば、そのときより重要だったのは誰もが映像をつくれるようになったことではなく、そのことによって映画への考え方、そのアプローチそのものが新しくなったことだったのではなかっただろうか。ペドロ・コスタ『ヴァンダの部屋』(2000)が持つ親密さ、あるいはチョン・ジェウン『子猫をお願い』(2001)が持つ軽快さ、キアロスタミ『10話』(2002)が持つ無機質さ、冨永昌敬『亀虫』の持つ自由さ(2003)……。そうしたデジタルの特性を使った映画がいくつもあって、映画自体の新しさが決定的に刷新される可能性が見出すことができた。それは、カメラの前に俳優がいて用意されたセリフを話し、そこには演出があって、物語のドラマツルギーがあって……という、従来の映画づくりとは一線を画すもののように感じられた。いや、それは次のように言い直す方が正しいのかもしれない。デジタルであるからこそそれに応じたつくり方を発見する必要があるのだ、と。そして、その模索の先に再び過去の作品と接続することができる。当時、ペドロ・コスタが繰り返し小津安二郎の映画について語っていたことを思い出す。まるで見た目も印象も異なるのに、同じ問題を共有してしまう。そして、そのことが映画の可能性を拡張させてしまう。デジタルへの移行は映画にとって何か新しいことが始まる希望を感じさせてくれたのだった。
しかし、そうした流れがあるときからはっきりと行き詰まってしまったような印象がある。異なる方法、異なる流儀であったからこそ、映画の核心に触れる可能性を持っていたのに、(あくまで実感ではあるが)いつからかデジタルによる映画はかつての方法、流儀へと戻ってしまったのではないか。ただ素材が変わっただけだとばかりに、2000年代初頭にあった驚きはいつの間にかなくなってしまった。もちろんその一方で、作品のたびに新しくなっていく映画作家たちの孤独な営みはあったが。
そんな中でまた別の新しさの実感を得られるものがあったすれば、それは2010年に起こる。
1月23日から29日まで1週間に渡り、横浜・黄金町のジャック・アンド・ベティにて「未来の巨匠たち」という特集上映が行われた。この特集は、連日30歳前後の若い監督たちが日替わりでひとりあるいはふたり取り上げられ、それぞれの監督作品と各監督たちが選んだ参考作品の上映、そしてゲストを呼んでトークショーを行うというものである。特集された監督は、上映日順に、瀬田なつき、加藤直輝、桝井孝則&唐津正樹、桃まつり(片桐絵梨子&矢部真弓)、小出豊、佐藤央&三宅唱、濱口竜介。当時劇場公開作を持つ者はひとりもおらず、つまりここで上映された作品は教育機関でつくられたもの、自主制作という形でつくられたものだった。この中の何人かの監督は劇場公開作を準備しつつある段階で、どこか暗闇に1本の陽がさす夜明け前のような瞬間であった。
梅本洋一が命名者ではなかったか、「未来の巨匠たち」とは随分と大仰なタイトルを付けたものだと思ったが、しかし日本映画にとって何かしらの地殻変動が起きるのではないかという気配がそのときにはあった。実際、そのことに敏感な観客たちによって劇場は連日賑わいをみせていたのである。やはり「未来の」と付いているのがポイントで、つまりここで取り上げられた監督たちはまだ何者でもなかった。たとえば、今号にも登場する濱口竜介は東京藝術大学映像研究科を卒業して間もなく、自主制作という形でつくられた『永遠に君を愛す』(2009)をこの特集でお披露目している。三宅唱にいたってはまだ長編作品を1本も完成しておらず『やくたたず』(2010)という名の処女長編作をつくるのはその後のことになる(それにしても、彼らのそのあとの制作本数の多さには驚きを禁じえない)。「未来の巨匠たち」はまだ当時何者でもなかったが、その作品をみればすでにそう呼ばれるだけの萌芽があり、その後の活躍は予想されたものでもあった。
同年10月に刊行された34号でNOBODYは「日本映画のための挑発的資料」という特集を組んでいる。そこには空族、真利子哲也、そして青山真治といった名前が新たに加わる(脚本家として佐向大も登場している)。この特集では映画制作のための資金調達という入り口、劇場での上映という出口が考察された。なぜこんな特集を組んだかと言えば、映画をつくってはみたものの今度はその作品をどうすればいいのかという問題が、切実なものとしてあったからだ。つくられた映画は限られた機会でのみ上映が行われ、当時それらの度に集まった人々との会話は決して明るい雰囲気はなかった。会えば「最近、何かいいニュースあった?」と聞くのがお決まりの挨拶で、それに対して誰もが暗い顔をしてうつむくのが常だった。そういう雰囲気が漂っていた。
それがひとつの運動であったかはわからないが、連帯感というのか、当時は何かしら共通の問題意識を持っていたような気がする。そこから各々が少しずつ各々の道を歩み続けてゆく。たとえば濱口は震災後の東北へ赴き被災地の声を撮り、神戸ではワークショップから参加者の身体に合わせて作品をつくる。三宅はiPhoneで周りにある日常を撮影し、それを編集した作品「無言日記」としてboidマガジンに発表し続ける。これは彼らふたりだけに限ったことではない。瀬田なつきは人々がアクションを起こすその瞬間への探求を進め、真利子哲也は暴力の肌さわりそのものを焼き付けようとする。空族は人と出会う、人と話すといった行動をすることがそのまま映画をつくる営みであるかのように、よりそのスケールを拡大させてゆく。鈴木卓爾はワークショップから映画つくりを開始することで映画そのものの境界を曖昧にしていく。監督たちそれぞれがそれぞれの映画つくりの方法を模索していた。そうした動きはNOBODYで定点観測的に追いかけていたとおりである。
そして、2018年。同時代に生きている喜びを感じさせるような新しさが再び実感される。それはかつてのデジタルというメディア自体の変化によってもたらされたものではなく、映画に対してその足場からいまいちど向き合うことで生まれてきたものではないだろうか。そう、それは今号にて取材させていただいた三浦哲哉の著書『『ハッピーアワー』論』の文章が明確に述べていることかもしれない。「このような認識は、おそらく作品制作の姿勢を根本から変えるだろう。作品を支える伝統という、いわば無意識の足場それ自体の検討がいまや要求される。もはや伝統への無条件に依存し続けることはできないように思われるからだ。だから、一からやり直し、制作の営みそれ自体が再検討される。また、再検討の過程そのものが作品の内容へと組み入れられる」。
いま映画をつくることとはどういうことなのか、その原理的な問いが再審されている。俳優がいかにして台詞を発するのかというこれまでの方法の延長上に、いかにして観客に登場人物の行動心理を想像させ信じうるものとするのか(『寝ても覚めても』)。小説の中に、現実の中にあった確かな時間をそのまま映画に実現することができうるのか(『きみの鳥はうたえる』)。人間の顔を撮ることとはどういうことなのか。そして、人間の存在にいかにして接近しうるのか(『教誨師』)スクリーンの手前と向こうの境界を曖昧にすることで現実と再び接近しうるのか(『ゾンからのメッセージ』)。その模索の先に絶対的な新しさが生まれる。
だが、この新しさはちょっとやっかいかもしれない。というのも、それは実感として強く感じられはするものの、決してわかりやすいものではないからだ。ゆえに今号では、その新しさを一緒に考えてくれる仲間たちともに、映画をつぶさに観察し、そこから議論をし、ときに想像することでその新しさに近づこうとした。実際、これだけの文章を掲載することができたことだけでもこの号をつくった意味はあったと本気で思っている。また、その新しさに近づくために、監督たちと対話をした(インタヴューというよりもやはり対話と言った方がふさわしい気がする)。そこにはどう映画と向き合うかという真摯な姿勢が感じられ、大いなる感動と刺激を受けた。
そして、後半に置かれたふたつの対話。当初、三浦哲哉との対話は現代映画の持つ新しさをより明確にするものとして意図されていた。だが、実際はより大きなスケールの下で、映画/映像の現在/未来の可能性に向けて、あるいは批評そのもの新しさの可能性に向けてまで射程を広げられるものとなっている。五所純子と月永理絵との対話は、映画作品内部の美学だけで映画を書く時代が終わり、現実で何が起こっているかそのことと結びついた形で行われなければいけないのではないかという問題とともに、いま映画について書くことそのこと自体も問題にもなっている。