 |
 |
 |
 |
 |
 |
わずか2日間しか映画祭に参加せず、しかも審査員としての参加なので、そのレポートも断片的なものになる。日記形式ではなく、別の形の断章にまとめてみよう。
まず学生映画祭の「学生」とは何なのだろうか? 応募作を撮る人が学生であり、運営・審査に当たるのも学生であるというのが定義らしい。ぼくは「最終審査員」という「お目付役」のような役回りだ。どんな「学生」でもいいので、来年はぼくもNOVAで駅前留学をすれば、作品を出品できるということだ。そして、学生が多様であるように、出品作のジャンルもフォーマットも多様だ。8ミリ、16ミリ、35ミリ、DVの作品がどれでも応募でき、尺にも制限はない。入選作も十数分のDV作から96分の16ミリまであり、ドキュメンタリーでもフィクションでもよい。
応募作は、上記のことで多様さを400本という数が確保できているようだ。だが、運営という面を考えるとかなりきつそうだった。もちろん全員がヴォランティアの学生諸君の仕事ぶりはとてもよかったけれども、彼らのほとんどが映画祭を経験したことがなく、どんなことも初体験だったのはやはり苦しい。ノウハウを伝えるためには何回も映画祭を経験しているプロフェッショナリズムも必要だし、他の多くの映画祭にあるように、プログラム・ディレクターの個性がその映画祭の魅力になっているのも事実だ。すべてが民主的に決定されていくプロセスはそれなりにいいものだが、逆に、プロフェッショナリズムの欠如が映画祭の個性を失わせていることも事実だろう。
応募については世界の主だった映画学科を持つ大学や映画学校にアプリケーション・シートを送付しているとのこと。だから各組織からのまとまった応募が多い。たとえば日本では大阪芸術大学、映画美学校、日大芸術学部、イメージフォーラム……。作品を見てみると、それぞれの作品の個性よりも、その母体の組織の教育方針が浮き出る。環境が人を教育するということだ。最終審査員──松下正己氏、井口奈巳さん、ぼく──の口から美学校っぽいとか大阪芸大風とかの言葉が漏れたことが何度もあった。 |
|
 |
 |
 |
| 何時間もかかった最終審査の席で「審査の基準」という言葉が何度も出た。そこで問題になるのは、当然、技術的な巧拙をどのように見るか、ということだった。ぼくの場合は、才能あふれる作品に出会ったときは、技術的な巧拙はほぼ問題にならないのだが、巧いに越したことがないのも当たり前だ。だが、巧さだけを鍛えるなら、職業映画監督にはなれるかもしれないが、映画に新たな領域を加えることはできないだろう。そして、巧拙というのも過去の価値観の集大成であって、そんなものに拘泥していては新たな作品など生まれないだろう。だが、もちろん、技術的な意味で「見るに耐えない」ものもなくはなかった。学生という身分をエクスキューズにすることだけはやめてほしい。もう立派な大人なのだから。
だが学生スタッフが審査に参加すると、過去の価値観の集大成という言わずもがなのことがなかなか通用しない。それも当然だ。彼らはまだ若いし、映画を勉強したこともないのだから、過去を集大成することなどできないからだ。そして、ほぼ同じことが応募作にも当てはまる。学生=若い=過去を知らない──仕方がないことだ。映画について、かつて開拓された多様な可能性を知らず、自分が属する学校で教えられたことに磨きをかける──それによって優秀な学生と見なされる──自分の周囲にいる人と自分との距離をもとにしか作品を見ることができない。これは悪循環。プログラムで井口さんが述べていたが、単に多くの映画を見るしかない。そうした映画の一番先端でこれから自分たちが作業していくのだという自覚は必要だ。しかし、シネフィリーの伝統──これはオートディダクト(独学)──が失われ、仮にでも映画教育のシステムなどが措定されてしまうと、作品が相対評価でしかなくなり、とても新たな可能性など生まれるべくもない。作り手にはまず何よりも自らが属する組織の教育方法を疑う行為が求められる。単純に与えられている価値を信じて、その中で自分を磨くことよりも、その価値を再審に付すことからしか新たなクリエーションなど生まれはしない。 |
|
 |
 |
 |
| 幸いぼくの主張が認められ、スロヴァキアのミラン・バログの『LOOP』という作品がグランプリになった。東欧の崩壊、スロヴァキアの独立、フィルムからDVへの移行──多様な問題を作品の周辺に配置して、それが弁証法的に論述されるこの作品は、もし通常のフィクションの映画を小説と呼ぶとすれば、エッセーと呼びうるものだろう。映像と音声を使用して、映像作品が立ち至っている現在の様相を、自らの場──スロヴァキアの地理と歴史の中で考察した作品に仕上がっていた。この昨年までリヴァプールに在籍していたストライカーと一字違いの映像作家の才能についてはいくらでも語ることができるだろうし、子どもや家庭崩壊やニートばかりを主題にする日本の「学生映画」に比べると知的で爽やかだった。
同時に昨年のグランプリになった真利子哲也の作品にも触れておこう。8ミリというアナクロなメディアに徹底して拘りながら、そのアナクロニズムを賛美するのとは逆に、法政大学の学館の解体とそのメディアの消滅とは平行して語られている。自らに拘りつつ、自らを異化する方法は、ミラン・バログに与えた知的という形容詞がここでもまたふさわしいことになるだろう。『マリコ三十騎』という昨年の作品でも、『極東アパート』という一昨年の作品でも、過去への傾斜とその考察=反映という様式は変わらない。ゴダールにおける「白痴」の主題やヴェンダースの『ことの次第』のキャメラ=武器、そして敗北というロマネスクと生きながら、別の何かを提示しているようにも見える。次作に期待したい。 |
|
 |
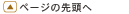 |
 |