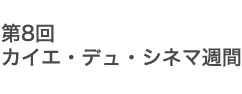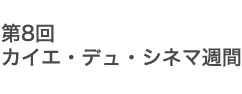

|
|
|
| |
2/2
野蛮な遊戯 / ジャン=クロード・ブリソー
少女は見てしまう。彼女に初めての恋心を芽生えさせ、世界に向けてその眼と耳を開かせた男が、見知らぬ女とベッドの上でもつれ合う姿を。彼女にとってその光景は、正確に言って崩壊そのものだ。
少女は先天性の脊髄損傷によって、生まれつき自立歩行が困難である。「障害者である私」という自己のイメージは、彼女の身体を通じて、恐らくは長い時間をかけて獲得されたものである。理性とか知覚とかいったものによって形成されるのではなく、彼女の半身の思うに任せないもどかしさ、その苛立ちが堆積したものであり、彼女にとってそれはただただ呪わしいだけのものだろう。そうした呪わしさは容易に外部に向かって反転してしまう。六本の足を器用に動かして動き回る虫や、休日の市場を楽しげに歩く人々へ向ける常軌を逸した彼女の憎悪は、そのようにして生まれたはずだ。
しかし「このようではない生」に対する彼女の憎しみは、そのまま彼女の叶えられることのない願いそのものでもある。そんな彼女に突如、ほとんど暴力的に捉えられる映像がある。裸体をさらし、乳房を揉む(というよりほとんど掴み取る)鏡に映った自分の姿だ。それまで知るべくもなかった「私」を、彼女は一瞬のうちに手に入れる。少女は自らの生の内部にあっても、「このようではない生」が確かに存在することを、鏡を通して半ば動物的に理解する。冒頭の男が彼女の前に現れるのは、その直後のことだ。たかだか初めての失恋の光景が、ほとんど理解を越える程の悲劇として立ち現れるのはこうした瞬間である。
この後、彼女がほとんど憑かれたように山頂を目指すのは、そうした悲劇や崩壊をも内包した未知の風景を手に入れ、愛すためであるはずだ。世界を知覚することと、誰かや何かを愛することが統合で結ばれるまでの、厳しいレッスンの過程がこの映画を構成している。
中川正幸
|
| |
|
| |
2/7
かごの中の子供たち / ジャン=クロード・ブリソー
オープニングで、英語の字幕が「The sounds and the fury」とでたので、原題の『De bruit
de fureur』が『響きと怒り』であることに気付いた。「郊外」は空間的な広がりをまったく欠いた「西部」だと思っていたのだが、どうやら「南部」でもあるらしい。
2月末発売のnobody第6号に収録されるジャン=クロード・ブリソーのインタヴューの中で彼は新作の『秘め事』について、「『かごの中の子供たち』が郊外で撮られた代表作だとすれば、今回はその女性版をつくろうと思った」と語る。超近代的な高層のきれいなビルが立ち並び形づくる幾何学模様。周りには見晴しのいい公園などがあって、遠くには都市が佇んでいるのが見える。しかし近寄ってみると玄関のガラスは割られ、団地の中ではマットが燃えているし、立体交差の影ではレイプ事件が起こっている。この内実を包むきれいな見せかけがただの表面に過ぎないとしたら、その表面を覆う状況、風景もまた表面に過ぎない。その全てが互いに隣り合って浸透しあう。ブリュノ・クレメールの狂った笑いは壁を砕いて隣の部屋まで響き、窓を通じて全ての隣接する教室へとフランソワ・ネグリの「革命だ!!」という叫びが響く。
雄々しい“悪党”=“英雄”たちのその叫び声だけが唯一、ハリボテのフロンティアを踏破して響き、近親憎悪の家族に距離感を与える。“名誉ある”=“悪名高き”血統の我らが“英雄”=“悪党”たちの響きと怒りは、しかしながらあっけなく破れ去る。音として響くことがほとんどなく、意味を伝達するだけの無感情なささやきの前に。
先述のインタヴューはこう続く。「どちらとも人生の意味、善と悪の意味にかかわっており、「侵犯」がフィルムのモーターとしてある」。全てが均しく隣り合っているが故に、「侵犯」はより困難なものとなる。善から悪へ、悪から善へというのではなく、もはやどちらとも呼べない彼岸へと滲み出ていくこと。それはしばしば、あまりに多くの“英雄”=“悪党”の犠牲を必要とする。
結城秀勇
|
| |
|
| |
1/19
亡霊 / ジャン=ポール・シヴェラック
「カイエ・デュ・シネマ週間」で、もう一週間」以上前に上映されたフィルムですが少しだけ。
原因不明に人々が消えてしまう、そんな現象がパリで頻発する。そんな主題だけでもワクワクするフィルムなのだが、夜な夜な男の亡霊が、生きている彼女を訪れセックスするとか、乱交パーティめいた裸の男女が集うユトピックな集団があったりだとか、あるいは中年女性を幾人もの男性亡霊たち(あとからあとから湧いて出てくる彼らは一体何人だったかも定かでない)が訪れキスし合い抱擁し合う・・・。一方で「消える」ということがあって、それからタイトルが『亡霊』とあるほどだから、亡霊が実体として登場する、つまり「実体幽霊フィルム」。
『亡霊』では、生き残った男の子が最後に海に行って少女に出会う。「私の名前分かる?」/「愛?」などと会話が交わされるこのシーンは、もはや亡霊であることも生きていることもどちらも変わらないことだという解放を、もちろんもたらしてくれる。そこは裸の男女がこれから生まれでようとする「始源の海」なのか、あるいは、実は亡霊となってしまった男の子が渡ってゆく「黄泉の海」なのか。それは「どちらでもある」わけで、つまりラストシーンを転換点として、「誰かの生前の世界」であり「誰かの死後の世界」であるようなフィルムになる。とんでもない留保地。
オゾンが『まぼろし』(『亡霊』とそっくり)を撮った後に『8人の女たち』を撮ってしまったこと、それから『シックス・センス』や『ヴァニラ・スカイ』などの、「死」という場所をラストで一挙に観客にもたらすハリウッドのフィルムたち、あるいは『回路』のあとに『アカルイミライ』を撮った黒沢清。
これは近い内に試論が必要でしょう。
松井宏
|
| |
|
| |
1/24
防寒帽 / ジャン・フランソワ・ステヴナン
ジャン・フランソワ・ステヴナンは映画で地形学をやる。この『防寒帽』の鳥が翼を大きく広げたがごとき稜線、『男子ダブルス』の奇妙な矩形をした岩肌、『ミシュカ』の稜線、地平線、水平線。やればやるほど基本的な幾何学へと近づいていく。地図に走る何本もの等高線では描けない、実に簡単なかたちになる。
空を切り取る山のかたちに相似した砦の建設のために、セルジュは山をスケッチしそれを極めて単純な直線の配置にデザインし直す。建築家であるジョルジュも鳥の翼のかたちをした谷の絵を描く。設計図が実現し砦が大きく翼を広げたとき、それは眼に見えない建築になるはずである。
ふたりは鳥の翼のかたちの谷間へ行ってみる。雪原の中を「ここは本物の谷じゃない」「ここも違う」といってとぼとぼ歩き回る。とぼとぼ、といっても見渡す限りの雪の中ではどうしても寒くて小走りになってしまうのだが、それはやはりあてのないとぼとぼ歩きなのである。谷のかたちはあまりに明瞭すぎて一目瞭然である故に、姿を消してしまうから。酩酊した興奮とその後の二日酔い。
目印にとチェーンソーで切り倒した大きな杉の木が、どれだけの変化を地形に与えたかは知らない。ただ巨大な図形は強度を持っている、それが単純なものであればある程。ステヴナンの映画がかたちづくる図形は、人間の何倍もの大きさの巨木が倒れてもびくともしないのである。
結城秀勇
|
| |
|
| |
1/17
ふたつの顔を持つ女 / ジャック・ノロ
とあるポルノ映画館。客達は開映の時間に合わせてやってきたりはしない。客は年寄りから若い男まで、いい男からブ男まで、そしてそれを狙ってくる女装の男までさまざまである。彼らはじっとしてスクリーンを観ているわけではない。席を立っては違う席に座り、出たり入ったりし(いろんな意味で)、くわえたりくわえられたり(そのまんまの意味で)する。彼らは映画を観るためにこの「双頭のプッシー」という名を持つ映画館を訪れるのではなく、ある者は見られるために、ある者は見ないでいろんなコトを済ますためにここにやってくる。したがって87分のこの映画の約半分が映写室の中で進むにもかかわらず、スクリーンが映し出されている時間はごく僅かだ。ここがこんな場所であると知らずに足を踏み入れてしまった私としては、スクリーン上の成り行きが気にかかるのだがいたしかたない。
突然、上映トラブルが起きて、客達は戸惑う。場内は明るくなり客はそれまでの中途半端な姿勢から、ちゃんと席を立つなりちゃんと席に座るなりを余儀なくされる。大声で怒りもあらわにクレームを言う者もいる。それは彼らのいる場所が本来強制する観ることを思い出させるからでもある。途中で警官がぬきうちで調査にやってくるときも同様である。座席で寝ている男にひとりの警官が言う、「ここはホテルじゃないんだぞ」。つまり本来の目的のオマケでしかないようなものを求めて男達はここを訪れているのだ。それは入場の際に受付嬢から手渡される、それ自体が切符の一部であるかのような入場料のお釣りにも似ている。中には小銭を掻き集めてちょうどぴったりの料金を払う者もいるのだが、料金を全部小銭で払うという行為の中に、あのじゃらじゃらというお釣りのなんとも割り切れない感じが既に含まれている。
入場時間は決まっていなくても退場の時間は決まっている。満足した者もそうでない者も時間がくればばらばらと劇場を後にする。オマケの楽しみを知っている男達は、それが所詮オマケにすぎないことも重々承知していて、本来の目的へすごすごと帰っていくのだ。
結城秀勇
|
| |
|
| |
1/11
ウェッシュ、ウェッシュ、何が起こっているの?
/ ラバ・アムール=ザイメッシュ
映画を見終わって幾つかの疑問が残った。
まず、警官の顔やパトカーのナンバー等にモザイクがかけられているのが理解できない。隠し撮りをしたものだから公開する際にまずいと考えての自己検閲かもしれない。だがそうしてまであれらの場面が必要かどうか疑わしい。モザイクをかけることでいかにもドキュメンタリーらしく見せようとしているようで気にいらない。
この映画では社会的に不利な立場にある人々が不当な扱いを受ける様が描かれ、権力の濫用が描かれるのだが、或る映像にかけられるモザイクには、それが不当であるか否かを問わず、より上位の審級の介入が露呈しているとも言える。だとすると、それが警察にかけられているのだからさらに上位の権力が設定されているのだと思われる。それは結局映像を操作する主体に行き着くだろうから、ここではその主体が無前提に受け入れられゆるぎない最上位に置かれているかのように感じられる。
ところで、なぜレンズをきれいにして撮影しないのかという点がこの映画でなにより不思議であった。冒頭の住宅地を俯瞰でとらえたショットからして画面には水の跡か何かの汚れが付着していて、それが気になる。まさかとは思うが単なる不注意かもしれない。だがわざとやっているとも考えられる。なぜそんなことをするのか疑問なのである。何事も美しく撮ろうとする価値観に反対しているのだと一応は言える。映画なんか汚くていいんだ、と。だが例えば湖の水面に陽の光が反射してきらきらと輝いている映像に鳥の鳴き声を重ねてしまうあたりなどのように美しさ以外に拠りどころのない場面がこの映画には紛れ込んでいる。あんな場面はなくても別にいいわけだからこの映画には美しさへの志向がかけらもないのだとは言えないだろう。
だが、それとは別に、レンズに付着した汚れを画面にみとめるや否やカメラの存在を観客が意識せずにはいられないということがあり、それを試みたのだと解釈することもできる。これはモザイクによって映像を操作する主体を露呈させることと矛盾しない。さらに言えば、そういった主体の視線は汚れていて不透明なものだという風に受けとるのが妥当かと思う。ことによると、Wesh(ウェッシュ)というのはWash(洗う)の間違いかもしれない。どうなってるんだ、レンズが汚れてるぞ、洗え、洗え、みたいな。
ともあれ、この映画は警察という監視し統御する主体とその対象たる地域住民という構図が映画の主体とその対象という構図とパラレルにあり、それを画面の表層に露呈させていると言えるわけだ。どちらかといえば、社会(学)的というよりむしろ映画的に考察された映画であると思う。
だが、それが面白いかは別の問題であり、今日にあって刺激的たりうるかどうかもまた別の問題なのである。
須藤健太郎
|
| |
|
| |
12/20
ウィンブルドンの段階 / マチュ−・アマルリック
英語、フランス語、イタリア語でもって会話が交わされているこの映画を英語字幕付きの上映で見た。英語もフランス語もイタリア語もわからないので、そこで人々が一体何を話しているのかさっぱり見当のつかないままに映画は進行してゆき、それでもなんとか懸命にわかろうとして、必死に英語字幕を追っていくのだが、意識は次第に映画に遅れ始めて別の事柄が頭の中では展開し出し、ふと唐突にジャン・ユスターシュのことを思い出す。「僕は外国語がわからない。これは僕の大きな欠点の一つだ。
なぜなら、オリジナル・ヴァージョンで上映されるシネマテークの映画の50%は英語だったから」。
もちろん、彼はこの後で自分はそのおかげで演出に目を向けることが出来るように
なったといった意味合いのことを口にするのだから、自分の「大きな欠点の一つ」を反省しているのではない。「溝口の映画を無字幕で見た時、僕は俳優が正しく演じているかどうか分からなかったし、そんなことはどうでもよかった。僕はほかの事に惹かれていた」。
要するに、台詞を理解したり、俳優の演技やその正しさに云々することなど映画を見るにあたってはどうでもよいことであり、そこには還元しきれないほかの事、例えば演出にこそ目を向けるべきなのだといった真っ当と言えば真っ当なことが言われているわけである。だが、かと言って、皆が皆、映画の中で交わされる会話が何を巡るものなのか、何を話しているのかを気にせずにいられると言うわけでもないはずだ。そして、例えば、『ウィンブルドンの段階』がどういうお話なのかとチラシに解説を求めるようになるだろう。
『ウィンブルドンの段階』の物語は、知識人で、作家たちの知人でもあり、物を書いていても不思議ではない或る男が結局のところほとんど何も書かずにこの世を去ってしまったことに疑問を抱いた或る女が、それを究明すべく、彼の知り合いに話を聞いてまわるというものだ。ジャンヌ・バリバール演じるその女が、イタリアへ、あるいはイギリスへと国境をするすると越えて、人に会うたびに話をし、そこに彼女のモノローグが重なるこの映画では「言葉」が重要なモチーフとなっている。実際、彼女はその男の跡を辿って、電車や飛行機を使って、次から次へと移動してゆくのだが、その移動のシーンはごくあっさりと処理されていて、ときたま走行中の電車のシーンがあるにはあるが、その場合、彼女は他愛もない会話を乗客の一人としなければならなくてうんざりしてしまうわけだ。また、そもそも彼女を駆っていたのは彼が「言葉」を書かなかったことなのである。
彼女が様々な人々と様々な言語で会話するのを、またそのフランス語のモノローグをこの映画は丹念に記録している。と、ここで再びジャン・ユスターシュのことを思い出し、彼の映画の主要な目的は「言葉を撮ること」だったという評言を思い出す。「言葉を撮ること」と言っても、それは厳密に言えば「話し言葉」のことであり「書き言葉」と区別されて用いられているのに違いないが、この評言がそっくりそのまま『ウィンブルドンの段階』にも当てはまるような気がしないでもない。マチュー・アマルリックの出演していた『そして僕は恋をする』は『ママと娼婦』に似ているだとか、ジャンヌ・バリバールはベルナデット・ラフォンの若い頃にすこし似ているだとか、そういった下世話な思惑とは異なったところでアマルリックがユスターシュにちらりと目配せをしているような情景がふいに浮かび上がる。いや、それも下世話だと言われればやはり下世話なことに違いない。だが、ジャンヌ・バリバールの声をはじめとした言葉の響きがほかには変え難い魅力としてこの映画を貫いていたのは間違いのない事実だ。
須藤健太郎
|
| |
|
| |
12/20
ウィンブルドンの段階 / マチュ−・アマルリック
列車の窓の外、2本の平行に並んだ電線はたえず同じ距離をとり続けているのに、近づいては離れ、時にひとつに重なり合う、そんな風に見える。それは列車のスピードのせい、見る者の速度のせいだ。2本の平行に並んだ電線とはなんのことだろうか。現在と過去か。死者と生者か。作品と作者か。それとももっと一般的な人と人との関係だろうか。いずれにしても、見る者は電線と平行に移動している。交わることは、決してない。
作家たちの友人であり、優れた知性を持ちながら(英語字幕によるとMonsters of intelligenceのひとりだという)、1冊の本も書くことなくこの世を去った男をジャンヌ・バリバールは探し求める。列車から列車へ、ホテルからホテルへ、街から街へ。母国語ではない言葉で話し、聴き、見る。彼女は常に目と耳をフル稼動させいていなければならない。ふたつある大学のどちらが目指す場所なのかわからないためにバスに乗り損ない、急についた電気にビックリし、男性用のビーチに迷いこむ。その仕種はしばしば子供じみている。
ある名前から別の名前をたどり、名前が人間となり喋り出す。点と点とを結んで線をつくるように、バリバールはボビー・ヴォーラーへと近づく自らの軌跡を描く。しかし彼女がよく見聞きすればする程、自分が求めている者は曖昧になる。「ある者は彼を陰鬱な男だというかもしれないし、他の者は彼こそ真に楽天的な男だというかもしれない」。「これがボビーよ。これもボビー。これもこれも」、数多くの写真を突き付けられても男の顔は鮮明な像を結ばない。ふらふらと流され出た沖には道などなく、途方に暮れる。
おもちゃのテープレコーダーが、子供の意味もない叫び声をリピートする。線上に記載された情報に意味があろうがなかろうがとりあえず再生する単純な機械。そういえば男の写真はたくさん出てきたが、男の声は聴くことができなかった。バリバールがまとめあげたレポートは、単純な音声記号であるアルファベット=点を文章=線にしたてあげたものだ。「書く」ということ。書かれることのなかった男の本。あるいは磁気テープに記載された男の声。それは男本人とは一定の距離をとり続けるが、角度によってはひとつに重なっても見える。
見る者=バリバールが電線とは交わらないとはじめに書いたが、もっと遠くから別の者が見ていたとしたら、彼女の高速の移動の跡が電線と重なって見えることもあるかもしれない。
結城秀勇
|
| |
|
| |
12/20
ウィンブルドンの段階 / マチュ−・アマルリック
いくつもの扉を開けるジャンヌ・バリバールは囚われた女だ。海と空とが、たった一本の線によって重なり合うその空間で、女は小さな死を何度か繰り返し、何度目かの新たな生を繰り返す。
彼女はある男の痕跡を拾い集めてゆく。もはやこの世を去ったそのイタリア男は、友人や恋人であった作家たちの言葉や作品によって語られ書かれるが、しかし彼自身はひとつの作品も残さなかった。
バリバールは未完の作品を作り上げる、ではなく、「作る」ことすらせずただ未完の作品となる。中世より貿易で栄えた港湾都市トリエステには様々な言語が刻み込まれ、都市は都市たりえず未完の都市となる。バリバールとトリエステはその限りで、いつも同じ地図を描き、描き変え、描き変え、描き変え、以下続く・・・。駅や港などの交差点が映され、そして絵葉書のようなステレオタイプの風景が映される。すると旅はもはや風景で満たされず、つまりバリバールは「見る人」の変奏となり、外国語を交響させる未完の身体を獲得するのだ。孔だらけでペラペラの身体の内側に、外国語が刻み込まれる。
そしてこのフィルムはバリバールの身体を指標にフランス語を再発明する。ナレーション(フランス語)は単純さを獲得し、絵葉書の風景と同じく地図の一要素として響きはじめる。
「今どの段階(stade)にいるの?」。彼女にとって「stade」は探究の段階や病気の進行段階である以前に「スタジアム」を指す。この錯乱した明るさが彼女の地図だ。ペラペラの地図の上でスピードを競い、理解する以前に感覚する、それがこのフィルムだ。
映画の登場人物は、こうして怪物となる。グローバリゼイション、シミュラークル・・・、我々の立つこの平面上で、ストレンジャーと怪物たちの新たなフィルムがそこかしこに生まれている。逃げ場(楽園)を自ら断ったフィルムたちは、俳優のとことん抽象的な身体を必要とする。知覚変動は現在進行中だ。
松井宏
|
 |
 |