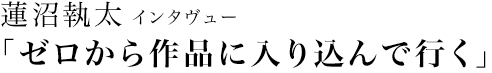7/18、浅草のアサヒ・アートスクエアで開催された「ミュージック トゥデイ アサヒ」で、初めて蓮沼執太のライヴを聴いたとき、素直に「これは瀬田なつきの作品に近いかも」と思った。もちろん瀬田作品で音楽を担当し続ける木下美紗都がメンバーのひとりとして参加していたことも、その近似性を示すことではあるのだろうが、なにより繊細なディテールを組み上げて作り出すダイナミズム、力強さ、そのピークへの持って行き方に、瀬田なつきの映画を思い浮かべてしまった。 ライヴ音源を元に製作されたアルバム『wannapunch!』を聞いて既に知ってはいたことだが、このライヴでもっとも印象に残ったのは、蓮沼が曲中に時折差し挟む「one、two」というかけ声だ。それはアンサンブル全体を指揮し、コントロールするというだけでなく、なにかが生まれつつあるこの場所に積極的に介入し、自らを刻み込んでいこうとする姿に見えた。 その蓮沼は、瀬田なつきの映画製作の現場に、どのように介入し、その徴を残したのか。
ーーまずは今回の企画に関わる経緯を伺えますか?
蓮沼執太 今年の1月に、原宿のVACANTで蓮沼フィルというアンサンブルで1日に2公演やったんですね。そのときに、建築家の藤原徹平さんが来てくれて、同じ場に瀬田さんも見に来てくれた。僕のアンサンブルに、瀬田さんの映画の音楽をずっとやっている木下美紗都さんがメンバーで、瀬田さんは木下さんを見に来ていたのかな。それに瀬田さんは藤原さんの大学の後輩に当たるんですよね? そこでなんとなくゆるやかなつながりができていて、その時に藤原さんの頭の中に「瀬田さんと蓮沼君はいいんじゃないか」と閃いたようです。
ーーそれから実際、映画の音楽を、という話が来たのが4月の末でしたね。
蓮沼今回のイベントは、通常の映画音楽、テーマソングや主題歌をつけてくれという依頼とは違っていました。街中のいくつかの会場を回って、いくつかの作品を次々見ていくという特殊なものですから、全体がしっかりと決まってこの部分を担当してくれというより、とにかく一緒になにかを作っていこうという感じでしたね。
ーー今回は具体的にどういう作業を担当されたのですか?
蓮沼一般的には、映画で音楽を付けてくれと頼まれる最初のタイミングって、編集も終わった段階で、監督に「こことここにこういう感じのテーマで音を付けてください」と言われる、という感じだと思うんです。でも今回はなにを作るかというミーティング段階からずっと参加していたのでそういう関わり方はしたくないなと思っていました。
瀬田さんも実力ある監督だし、彼女の作品も知っていましたから、まずはどうやって作るんだろうという映画製作のプロセス自体に興味を持ったという感じですね。ゼロから作品に自分が入っていくような関わりがしたいと。どんなことが行われているのかを理解したかったんです。
それに今回の企画は、製作は実質1ヶ月くらいですごくスピード感がある。だからある程度全体の進行を共有していないと音楽を作れないなと思ったんですよ。
ーー撮影現場にも行かれて、作業をされたんですよね?
蓮沼横浜の黄金町で歩きながら鑑賞体験をするという上映方法だったので、撮影場所もそれに近い場所が選ばれました。だから撮影の時点から関わらないといろいろ共有できないなと感じて、そこでまず思いついたのが、フィールド・レコーディングでした。
いわゆる台詞などを録る録音部とは違ったシステムで、レコーダーをもって音を拾っていこうというところからスタートしました。撮影は5日間でしたが、行けるところはだいたい行って、かなりの量の素材を撮りためて、という感じですね。
最初はMAもやろうと思っていたんですが、それは結果的に難しいなということになってやめました。やはり映画の環境音というのは、独特の技術が必要なものです。録音の段階からパッケージの音が見えていないといけない。だから途中で、僕がこの素材を使いたいと思っても、たとえばそこにちょっと違った画があったりすると、画と音が離れちゃうということがよくわかって。奥深いなぁ、と。

ーー蓮沼さんはこれ以前にも映像を使ったインスタレーションなんかをなされてます。今回の映画の製作とはまったく別物ですか。
蓮沼そうでもないですね。今僕が作ってる作品は、映像に入ってる音を使ってコンポジションするんです。たとえばコップがテーブルに置かれたら、そのコン、という音を使って作っていく。もともと画と音は分離していない。そういうのは映画では当たり前のことですよね。だから勉強になるところはたくさんありました。
でも一方で、映画の場合は、音はフィクションなものでもある。環境音とか入ってるんですけど、全部が作り物だとも言えるなと感じました。
ーーそれはある台詞だとかの特定の音をしっかりとらえて、また別の特定の音はなるべく排除するという録音方法が、ということでしょうか。
蓮沼そういうことも含めてですね。僕は現象を切り取って作品にしていくので、その方がマテリアルなものにより大きく寄っている。
ーー映画の方が、画がそこにあって音を作っていく、という印象を受けたと。
蓮沼そうですね。とはいえ、音楽は視覚的なものよりも感情的な操作を行いやすいので、弱いわけではない。作り物であるが故に、一気に全体のムードを変えたりもする。
ーー特殊な上映環境ならではの音作りというのは、今回意識されていますか?
蓮沼作ってる段階では考えていないですよ。ただ、上映場所に対しては操作しようと思っています。『5windows』という作品が、「港のスペクタクル」が終わり、たとえばどこかの映画祭だとか他の上映機会があったときには、通して観れるような状態に作っておこうと思っています。
ただ今回の上映は、その場の環境音がすごく鳴ってたり、京急の電車がすごい近くで走ってたりする。そういう場所で映画を上映すること自体が、まあアメイジングですよね(笑)。だからこそ、通常の映画であれば、ノイズとして排除されてしまうような環境音を、あえて観客に気づいてもらうような仕掛けを作ったり。そういうアイディアはいくつかあって、ちょっとのスパイスで可能なことだと思うんです。
ーーソフトはソフトとして作り込んで、今回の上映に関してはある意味ライヴ的なものとして考えてということですか?

蓮沼そうです。サイトスペシフィックと言うか、その場でなにができるかということには僕は比較的に慣れていると思っていて。たとえばコンサートをするとき、クラブでライヴするのとライヴハウスでライヴするのは全然違いますからね。その場でなにができるかということを考える。とはいえ、リハーサルする時は、どちらもニュートラルな状態です。あのアンサンブルを持っていく場所によって色々と変化をつけていくというのは慣れているというか。徐々に身に付けた、身体感覚みたいなものだと思います。
ーー『5windows』の劇中、登場人物が口ずさむ鼻歌も蓮沼さん作曲ですよね。
蓮沼いま話してきたような、僕が考えた細かいことが観客にどこまで伝わるかは未知数なので、僕が関わったことをより直接的にアピールしたいと思って、映画参加者の全員が共有できるようなメロディがあった方がいいと思ったんです。それが劇中で、みんなが口笛とか鼻歌で歌ってくれているメロディです。
そもそも映画の中では、目に見えないかたちで登場人物4人はつながっていく。そういう意味では音も目に見えないのでとてもシンクロしていると。上映空間が特殊で、話も説明的なものではないので、それらをうまく混じり合わせて行くには、音はとても大切だろうなと思ってたんです。
ーー『5windows』には、実際蓮沼さんが登場して演奏するシーンがありますね。
蓮沼最後に、僕含め三人の楽団が出てきます。なぜそれをやったかというと、瀬田さんの脚本に「演奏チームがいる」と書いてあったからなんです。僕は、バンド編成の場合は「チーム」と呼んでいるんです。だからまさかこれ、それを出すの?と思って(笑)。ツインドラムだよ、とか(笑)。でもそうじゃなくて、ちょっとしたのでいいということだったので、横浜、黄金町とと言えば家が近い大谷能生さんにちょっとサックス持ってきて、とお願いして。ちょっと練習してもらって、吹いてもらってます。 そのラストシーンは、同録の音が、スタジオレコーディングの音に被さっていくようにしたいんですよ。自然とスタジオの音に変化していく。そうした演出は最初から想像していました。
ーー最後に、実際に体験された瀬田監督の作品製作のプロセスはいかがでした?
蓮沼まず瀬田さんの脚本が、なんというか、メタファーの連続なんですよ。「?」って思う感じの。
音楽でたとえて言うと、楽譜がありますよね。楽譜は正確に書かないと演奏家に伝わらないですよね。それが瀬田さんの場合、コード譜になってるみたいな感じなんですよね(笑)。「F」とか書いてあって(笑)、そこでメロディが欲しいとか言われる。とはいえ、もちろんそういうタイプの音楽家もいるわけで、それによって良くなる部分だってあります。プレイヤーにゆだねる、その力を引き出すということを期待して、それができるタイプの監督さんなんだと思います。撮影現場のアクシデントを取り入れて対応していくとかね。とはいえすごいなあ、これは暗号かな?って思ったり(笑)
それと脚本を読んで思ったのは、役者さんに対する具体的な指示が少ないなということです。でも現場に入ると、瀬田さんはその暗号を役者の方にやさしく説明している。それで撮ってみると、ああこういうことだったのかとわかるものになっている。
ーー抽象的であっても、難解であったり閉じているわけではない。
蓮沼瀬田さんは、普通に見ているけど認識しない音に対する感覚がするどい。たとえば画面の端で、鳥が飛んでいる映像があったとして、鳥を見てはいるけど普通認識しないじゃないですか。でもそこに鳥の音があると、鳥がいると意識する。そういう無意識なものを具体的に説明するところが、瀬田さんはすごいうまいんじゃないかと思った。さらりとして見えても、実はさらりとしてなくて、随所にひっかかりがあるように作ってある。そうした細かいところ、些細なところでうまいなと思うことが多かったですね。
だからといって、そうした細かい部分だけで満足してしまうわけでもなくて。僕も自分の作品でディテールをすごく凝ったりしますが、それでも狭いポイントではなくて、なるべく広い視点に持っていきたいといつも思っています。その間口の広さというようなものは、瀬田さんにも近い感覚があるかなと思いました。
あのアブストラクトな脚本であっても、完成したものを見ると、瀬田さんの作品には「観る人」を選ばないところがあると思うんです。今回は特殊な上映形態の企画で、いわゆる実験映画や映像インスタレーションを体験するような感じではまったくない。頭でっかちな感じには無っていないと思うんですよね。僕もそれに寄り添えるようにしたいですね。
蓮沼執太
1983年東京都生まれ。HEADZを中心に国内外の音楽レーベルから作品を多数発表。主なアルバムに『OK Bamboo』(07)、『POP OOGA』(08)、『wannapunch!』(10) など。《蓮沼執太チーム/フィル》《ウインドアンドウインドウズ》《音楽からとんでみる》《ミュージック・トゥデイ》など音楽を基とするプロジェクトを制作。現在、東京藝術大学大学院映像研究科研究生。
取材・構成 結城秀勇