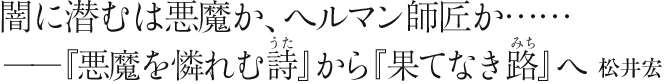モンテ・ヘルマン21年ぶりの新作長編『果てなき路』とは、いったいどのような映画なのか。
事実に即して簡単に言えば――もちろん一側面でしかないとはいえ――それは映画づくりに関する映画である。ミッチェル・ヘイヴンというひとりの映画監督とローレル・グラハムというひとりの女優が主人公であり、全編に渡って映画づくり(準備から撮影)の光景が描かれてゆく……。しゃれた言い方をすれば「メタ映画」などと呼ばれもするだろうこの作品。
だが実のところ『果てなき路』は映画に関する映画というより、むしろ役者に関する映画とでも言った方がよい。どのようにひとりの女性が女優になるのか。どのようにひとりの女優が登場人物になるのか。あるいは、どのようにひとりの登場人物がひとりの女優になり、またひとりの女性になるのか……。この作品がおもに描くのは、まさにそれだ。
「要するに『果てなき路』はアメリカ映画におけるメタ映画の名高い系譜に属するはずだ。だが実際はその逆だ。これは鮮明なデジタル時代におけるひとつの映画的リテラシーであり、キャスティングに関するヘルマンの理論の実践なのだ」。本作の公開と同時に発売されたインタヴュー集『モンテ・ヘルマン語る――悪魔を憐れむ詩』(以下『悪魔を憐れむ詩』)のインタヴュアーであるエマニュエル・ビュルドーは、序文でこう記す。
もちろん『悪魔を憐れむ詩』というインタヴュー本では、自身の出生から現在にいたるまで、また舞台演出から映画演出まで、処女監督作『魔の谷』(59)から代表作『断絶』(71)を経て最新作『果てなき路』まで、あるいは実現しなかった企画の数々や、クレジットもされないままさまざまなかたちで彼が手伝った仕事、そして「映画とは何か?」という問いについて……などなど、とにかくありとあらゆる事柄がヘルマン本人の口から語られている(おそらくすべてを読み終えた後、ヘルマンを「ヘルマン師匠」と呼びたくなること間違いなし)。
その寡作ぶりや、その仙人風の(?)容貌、また『断絶』や『銃撃』(66)のあのとてつもないラスト(『断絶』のラストではフィルムが炎とともに溶け出し、『銃撃』のラストではスローモーションのさなか、主人公のカウボーイが自らの分身に出会ってしまう)、あるいはタランティーノやヴィンセント・ギャロの口から漏れるヘルマン賛美などから、どうしても伝説というか神話というかホラ話というか、そんな謎めいたイメージが彼にはまとわりついてきたヘルマンだが、『悪魔を憐れむ詩』という本は、そうしたイメージをひとまず払拭し、ヘルマンをひとりの映画作家として見る透明な――複数の――視線を観客にもたらしてくれるだろう。
そんななか、エマニュエル・ビュルドーが書くように『悪魔を憐れむ詩』をヘルマンの役者論、あるいは役者演出論として読み、『果てなき路』をその実践として見ることは、ひとつの読み方として可能だ。というか、そこまで言わないまでも、このインタヴュー本でもっともおもしろい事柄のひとつが、やはり役者たちの話だったり、役者への視線だったり、彼らとのやり取りだったり、なのだ。この映画作家が、これまでの映画づくりを通していかに役者との関係に喜びと重要性を見いだしてきたかが、実際『悪魔を憐れむ詩』を読むと、とてもよくわかるのである。
そしてこの観点を軸にしてみると、ヘルマン映画の、そして『果てなき路』の、ある重要な一側面がみえてきたりもするのだった。
すべてはキャスティングにある Everything is casting
1にキャスティング、2にキャスティング、3にキャスティング。それが仕事の9割を占める。あとの1割はどうでもいい(ミッチェル・ヘイヴン)

(C) 2011 ROAD TO NOWHERE LLC
そう、ヘルマンはあっけらかんと断言してしまうのだ。「すべてはキャスティングにある」と。もちろん「それは俳優だけにかぎらない。つまり撮影監督、作曲家……その他も同様さ」とつづけるとはいえ、やはりここでのキャスティングとはまず何より俳優に関わるものだ。『果てなき路』でもミッチェル・ヘイヴンとローレル・グラハムが最初に出会うのは、まさにキャスティング作業においてだった。そして『悪魔を憐れむ詩』でも、これまで仕事をしてきたさまざまな俳優たちについて、多くが語られている。ジャック・ニコルソン(『バックドア・トゥ・ヘル/情報攻防戦』『フライト・トゥ・フューリー』『旋風の中に馬を進めろ』『銃撃』)、ウォーレン・オーツ(『銃撃』『断絶』『コックファイター』『チャイナ9、リバティ37』)、ファビオ・テスティ(『チャイナ9、リバティ37』『イグアナ/愛と野望の果て』『果てなき路』)、ミリー・パーキンス(『旋風の中に馬を進めろ』『銃撃』『コックファイター』)、ローリー・バード(『断絶』『コックファイター』)、そして最新作のタイ・ルニャン、シャニン・ソサモン……。
たとえば盟友ジャック・ニコルソンについて語っている箇所は、この本のなかのもっとも愉快で興奮する箇所だし、『イグアナ』(88)を捧げたウォーレン・オーツについてのこんな言葉を読んで感動しない人間などいまい。「そう……、心地良さの問題だよ。彼はことばに頼らずコミュニケーションすることができた。楽だったね。彼との仕事はまさに幸福さ」。あるいは『イグアナ』から『果てなき路』までの長編の脚本を書いてきたスティーヴン・ゲイドスとの対話における、今作での手に汗握る(?)キャスティング作業。あるいは『イグアナ』の主人公を演じたエヴェレット・マッギルに対してぶちまけられる不満の言葉!
いいかい。(役者の)キャスティングにはある決定的な要素が存在する。そしてそれは、作品を機能させるためにかならず必要なものなんだ
おそらくこうしたヘルマンの態度は次のようにも言い換えられるだろう。いいかい、わたしが君を選んだ以上、君は何をしたっていい、安心しろ……。「すべてはキャスティングにある」と断言すること、それは他人の才能を見抜く才能を彼が持ち合わせていることを意味するのだが、それはまた、役者たちとの共同作業を行うための下地をきちんと準備することをも意味する。
わたしたちが作り出したのは、言うなれば自由に失敗できる空気だった
ヘルマンがここで言う「自由に失敗できる空気」は、けっして撮影現場だけのことではなく、シナリオ執筆から編集作業まで、映画づくりという共同作業全体に当てはまる。だがそうした空気が、何よりも撮影現場での、役者たちとの関係において作りだされていたことは間違いない。
おもしろいことにこのヘルマンの言葉は、あるひとりの映画監督を思い出させる。ジャック・リヴェットだ。リヴェット映画の多くの脚本を担当したパスカル・ボニゼールは、以前インタヴューにてこんなことを語っていた。
『恋ごころ』(01)の俳優セルジオ・カステリットがこんなことを言っていました。ジャックの映画作りの原理――つまり日に日に場面ごとにシナリオを発見してゆくやり方――というのは、大きな恐怖を俳優にもたらすのだが、同時に安堵感も与えてくれると。なぜならそこでは間違えることができる。不確かさに囲まれているがゆえに、間違える権利を持つことができるのです
実はヘルマンは『悪魔を憐れむ詩』のなか、別の文脈でリヴェット映画について重要なことを語っている。「リヴェットは登場人物がドアをくぐるところを見せ、階段を見せ、彼らが玄関を通り過ぎ、部屋まで行くところを見せる。結合組織、つまりシーンとシーンの間にあるものを、彼はそのまま残しておく……。それは私がのちに発展させたスタイル――まあ、あるとしたらだが――のベースだと思う。リヴェットは実時間において物事を表象していたんだ」。ここでいう「結合組織」、あるいはリヴェット特有のショットの持続性などは、たしかにヘルマン映画にしっかりと見ることができる。
それはそれで興味深いのだけれど、いまここでおもしろいのはヘルマンにおける「失敗できる空気」とリヴェットにおける「間違える権利」の共通ぶりなのだ。
リヴェット映画の多くには、あらかじめ完成したシナリオがないのは有名な話だ。その日その日で場面のシナリオが渡されていき、つまり役者たちは「日に日に場面ごとにシナリオを発見してゆく」。おもしろいことに、実はヘルマンもまた『断絶』でそれに近いことをやっていたのだという。『断絶』の撮影中、ジェームス・テイラー演じる〈ドライヴァー〉と、デニス・ウィルソン演じる〈メカニック〉、このふたりの役者にはその日その日でシナリオの新しいページを渡していったというのだ(もちろんジェームス・テイラーはそれに反対していたらしいが!)。
もちろんこのやり方は、けっして即興賛美を意味するわけじゃない。むしろ、たとえば『断絶』において役者の即興に任せたシーンはひとつしかないというし(どこかは読んでのお楽しみ)、『銃撃』にいたっては、ヘルマンは台詞を一語一句書かれた通り厳密に役者たちに言わせたというのだ。ヘルマンが重用視するのは即興ではなく、あくまでも役者たちの自発性であり、そしてそれが生まれる空気の方なのだ。
たとえば『断絶』という作品は、まさにそうした空気がすべてのカットに充満していたと言えるだろうし、『コックファイター』(74)だって、『チャイナ9、リバティ37』(78)だって、同様だ。そう、思い出してみよう。ヘルマン映画を見るときに感じてしまうのは、何よりもまず次のことなのだ。「彼ら、彼女らはなんて居心地良さそうなんだろう。どうしてこんな存在の仕方ができるんだろう」。『悪魔を憐れむ詩』を読んでいくと、改めてそれを思い出さざるをえない。

(C) 2011 ROAD TO NOWHERE LLC
よくよく考えてみると、ヘルマン映画におけるこの「失敗できる空気」「間違える権利」というのは、なにも役者との関係だけではなかろう。というか、ヘルマンはそれらをつねに映画化してきたような、そんな印象さえ受けてしまうのだ。たとえば『断絶』で、〈ドライヴァー〉〈メカニック〉のふたり組と、ウォーレン・オーツ演じる〈GTO〉は、そもそも敵同士なはずなのに、いつの間にやら奇妙な友情関係を結んでしまう。その、役割を間違えてしまったかのような、つまり本来語られるべき人物関係を失敗してしまったかのような時間帯こそが、『断絶』の本当にすばらしい時間帯だったりする。またそれは『チャイナ9、リバティ37』でも同じだ。ファビオ・テスティ演じる殺し屋ガンマンが、標的であるはずの男(ウォーレン・オーツ)と、いつの間にやら一緒に暮らしだし、友愛とでも呼べるような関係を築いてしまう。また『イグアナ』の主人公オーバラスとカルメンにも、それは当てまると言えよう。ヘルマン映画の登場人物たちは、あたかも物語を失敗し、人物関係を間違えることで、独自の関係性と時空間を生み出してしまうのだ。
そしてまた、ヘルマン映画の登場人物たちはけっして完全な「勝利」を得られない。『断絶』も『チャイナ9、リバティ37』もそうだし、初期の傑作『フライト・トゥ・フューリー』(64)もそうだし、『銃撃』だって『コックファイター』だって『イグアナ』だって……。エマニュエル・ビュルドーが「(ヘルマン映画の)どの世界も尽き果てているのだ」と書くように、そこで登場人物たちはけっして十全な勝利を得ることなく(たとえ何事かの勝負に勝ったとしても)、ただただその世界の方こそが尽き果て、映画は終わりを迎える。
ところがヘルマン映画におけるそうした終わりは、ニコラス・レイ流の(あるいはマイケル・チミノ流の)鋭い痛みをともなう「苦い勝利」では、けっしてないのである。むしろある種の風通しの良さみたいなものが、そこに生まれるのだ。そう、おそらくそれは、彼らがまさにラストにおいて「失敗できる空気」のなか、「間違える権利」を行使しているからだと言える。言い換えればヘルマンの映画とは、そのような空気や権利を体現することで、自由を獲得しているのだ。人生には勝利する権利があると同時に敗北する権利だってあるし、正しいことをする自由と同時に間違える自由だってある。ヘルマンの映画、そしてそのラストとは、その不確かさゆえに自由を獲得するのである。
もちろん『果てなき路』もまた、「自由に失敗できる空気」「間違える権利」でできあがっている作品だ。しかも『悪魔を憐れむ詩』を読むと、それらがまさにローレル・グラハム/ヴェルマ・デュラン役のシャニン・ソサモンによって体現されることで『果てなき路』ができあがっていったことがわかる。詳細はぜひ読んでいただきたいが、彼女の「失敗」があるシーンのトーンを決定し、また彼女の「間違え」が即興になり、作品全体の構成すらを変えてしまう……。その意味でもやはり『果てなき路』は、役者に関する映画だと言えよう。
登場人物が重要だとは思わないし、わたしは登場人物を、まさにそれを演じる俳優のある一面として見ている。登場人物が俳優になるべきで、その逆ではない。演じる俳優のおかげで登場人物が独自のものになればなるほど、その登場人物は普遍的なものになる
このヘルマンの言葉が、まさに「ローレル・グラハム/ヴェルマ・デュラン/シャニン・ソサモン」に当てはまることは、『果てなき路』を見れば一目瞭然だ。もしかしたら『果てなき路』とは、この言葉を証明するためにこそつくられたのでは? とさえ思えてしまうほどだ。
そしてまた繰り返すが、すべてが不確かさのなかに置かれている『果てなき路』とは、徹底して「間違える権利」を持つ、とても自由な作品なのである。物語の謎めいた核となる、あのトンネルの暗闇。あるいはラスト、壁に貼られたローレル・グラハム/ヴェルマ・デュラン/シャニン・ソサモンの顔写真の、上唇と下唇のあいだの少しばかりの黒い隙間(ラストカットのズーム!)。恍惚のまま半開きにされた口の、その闇の空間は、まさに不確かさに満ちあふれた空間であり、観客もまたそのなかにいる自分を発見するだろう。
作品が存在しうるためにもたらされるすべての協力の最後の一手。そう、今度は観客が協力者になる番だ。わたしはそんな観客のために映画を作っている。作品のプロセスに参加してくれる観客だ
映画監督は自分の観客の知性を高く見積もっておく方がいい。低く見積もっておくよりはね。それに観客は一種類じゃない。すでに話した通り、映画というのはまさに共同作業による構築物であり、観客はその最後の作業者なんだ
そう、ヘルマン映画の観客とは作品への最後の「協力者」であり「作業者」だ。そしてその作業とは、不確かさに解を与えることというよりは、その不確かな闇のなかで快楽を感じ、自由を獲得することを意味するはずだ。
『果てなき路』は――そしてヘルマン映画全体は――こうして闇のなか、観客の力を借りて未完の完成を果たす。そう、わたしたち観客もまた『果てなき路』の役者なのだった。
※モンテ・ヘルマンの言葉の引用はすべて『モンテ・ヘルマン語る――悪魔を憐れむ詩』より。