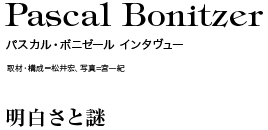あらすじ:
フランスの小さな村の大邸宅に住む上院議員夫妻がパーティを行う。ゲストは医師夫妻に彫刻家、作家に女優といった上流階級の男女で、ごく親しい間柄。そんななか精神分析医のピエールが何者かに殺害される。結婚当初から妻への忠誠心はカケラもなかった彼。パーティに集まった女たちの中には、過去の火遊びの相手、現在の愛人、そして復縁を迫る元恋人もいた。事情を知る男たちも含めて、全員がピエールに愛情と嫉妬、憎しみや哀しみなど、殺人の“動機”にも成り得る複雑な感情を抱いていた。しかしまた、全員に“アリバイ”もあった。犯人は誰なのか? そして捜査が暗礁に乗り上げ、互いに誰も信じられなくなったとき、第2の殺人が起こる……。
今作『華麗なるアリバイ』が日本での初公開作品となるパスカル・ボニゼール。『カイエ・デュ・シネマ』誌の同人として名を馳せ、またジャック・リヴェットの共同脚本家としても知られる彼だが、96年の長編デビュー以来、今作がすでに5本目の監督作品である。アガサ・クリスティの『ホロー荘の殺人』を翻案した『華麗なるアリバイ』は、「遅れて来た新人」ボニゼールが、すでに確固たる独自の道を歩みつつある事実を確認させる作品だ。

——新作『華麗なるアリバイ』はサスペンス映画ですが、これはあなたのキャリアのなかではじめてのジャンル映画ですね。
PBこれまでも私の作品はすべて、さまざまなジャンルに足をかけてきました。ただし「真正面から」ジャンル映画に取り組み、それを引き受けたのは今回がはじめてです。非常に興味深いエクササイズでした。
と同時にちょっとしたチャレンジでもありました。この作品はサスペンスですから「誰がやったのか?」というゲームをうまく機能させねばならない。つまり観客がすぐに犯人を当てられる、そんな馬鹿げた作品は絶対につくってはならないわけです。その点に関しては、ある程度成功したと自負しています。
——また翻案というのも、あなたにとってはじめてとなります。
PBそうです。これもまたもうひとつのチャレンジでした。非常に「ジェントリー」で「英国風」で、登場人物のキャラクターやシチュエーションの面で、古めかしさがあるアガサ・クリスティ作品をどのように翻案するか。原作には結婚プロポーズの逸話があったり、また書かれた当時の典型的で、そして戯画化されたハリウッド女優もいます。とにかくオリジナルの素材を使い、その構造を尊重しながら、同時に十分な変化を施す必要がありました。そのまま翻案するなんて何の意味もありませんからね。主人公のエルキュール・ポワロを消したのもそのためです。物語を現代化し、その舞台をフランスに移すのを決めた瞬間、彼を消したんです。ただある意味でその選択はもっとも大きな困難を導きました。というのもこのジャンルは原則としてかならず探偵を必要とするからです。利口で、でも制度に飼いならされておらず、そして彼固有のメソッドで解決法を見つけ出し、自らの威厳と神秘性で観客を惹き付ける人物、それが探偵です。ポワロが意味を持つのは、アガサ・クリスティの宇宙のなかだけ、つまり完璧に英国的な宇宙のなかだけです。ベルギー人である彼は、英国の風土における染みのようなものです。つまり「ヨーロッパ大陸的」な染みです。と同時に、その滑稽さと典型的にヨーロッパ大陸的な奇癖を越えて、彼はとてつもない分析能力を備えており、それによって英国的なメンタリティから逃れているのです。よって舞台を英国以外にした瞬間にポワロを消去したわけです。
もちろん主人公たちのひとりを探偵役に仕立てましたが、それはその人物をポワロの代わりに仕立てるためではありません。その点において、私はジャンルに対してリスクを負ったと言えるでしょう。
——ピエール・アルディティ、ランベール・ウィルソンというキャスティング、またFloc'hによるポスターのイラストなど——『かすり傷 Petites coupures』(03)のイラストも彼でしたが——、どうしてもアラン・レネを想起してしまいます……。
PBキャスティングの際、とくにレネを考えたわけではありません。実はピエール・アルディティの役は当初アンドレ・デュソリエに頼んでいたんです……、そうですね、もちろん彼もレネ組の俳優のひとりですが(笑)。アルディティは、登場人物にちょっとだけ手を加えることを条件に、引き受けてくれました。というのも実は、ラストあたりの、ベッドでの夫婦のやり取りは、当初存在していなかったんです。あれは撮影前に、アルディティからの要求を受けて書き足したシーンです。しかも私自身、あのシーンはかなり気に入っています。
またレネの宇宙には、非常に推敲された滑らかな側面と亀裂や裂け目が同時に存在しますが、これは私が目指すところでもあります。
——と同時にこの作品にはレネと共通のテーマがあるように思います。記憶と忘却です。
PBそうですね。そのモチーフは物語の横糸を織りなしていると言えます。そもそもアガサ・クリスティの原作にも、そうした側面が存在しています。作品冒頭あたり、ランベール・ウィルソン演ずるピエール・コリエは一種のぼんやりした状態にある。「お家に帰りたい」とふいに口にするとき、その言葉がいったい何と関係があるのか自問する。この一連はもともと小説にあります。またピエールのお気に入りの患者で記憶喪失のジュヌヴィエーヴ(エマニュエル・リヴァ)も、もともと小説に存在します……。他方で、マチュー・ドゥミ演ずるアル中のフィリップ。記憶が穴だらけのこの男は小説には存在しません……。とにかく、記憶と忘却というのは一種のライトモチーフですね。
——記憶が穴だらけのフィリップが、いつの間にか探偵の役割を負ってしまう。そこにはまさに矛盾があります。そしてこれこそ、あなたが先ほど言った「ジャンルに対してリスクを負う」ことでもありますね。
PB彼は混乱を持ち込むと同時に、彼そのものが混乱した存在なのです。まず自分が誰を愛しているのか、という点において。エスターを愛しているはずが、次はマルトを愛していると思い、しかし最終的には彼が本当にマルトを愛しているのか、確かではありません。ちなみにエピローグは少し悲しげなものになってしまって、後悔しているんですよ……。ともかく、この登場人物に関して私が考えたのは、探偵が同時に犯罪者であるような映画です。つまり犯人を捜しながら、最後に自分が犯人そのものだと知ってしまうような作品たちです。たとえばミッキー・ローク主演の『エンゼル・ハート』(アラン・パーカー監督/1987年)。まああれはかなり冴えない例ですが……(笑)。もちろん物語自体は異なりますが、この様式に近いかたちでフィリップという登場人物をつくったのです。言うなれば彼は、何かを犯してしまったことに泣きわめきながら真実を発見しようと試みつつ、しかしその真実があまりに自分と関わりが深すぎるのに恐怖している、そんな人物ですね。
——またあなたのフィルモグラフィを貫く要素、つまりコメディという要素もここでは見事に組み込まれています。
PB私はこの物語——非常にメロドラマ的な側面を持つ物語です——にコメディの登場人物がほしいと強く望みました。というよりも登場人物たちが同時にコメディの登場人物であってほしいと思ったのです。私にはコメディと自分を結びつけてくれる拠り所がつねに必要なんです。
なかでもミュウ=ミュウ演ずるエリアーヌ・パジェスこそ、まさしくコメディの登場人物です。また彼女はコミカルな面も強調しています。この登場人物は小説内の「レディ」、つまり家の女主人であるアンカテル夫人に対応しています。典型的な特権階級のエキセントリックなレディです。私は彼女を、少し天然な、フランスのブルジョワ夫人に変えたみたのです。小説内のレディはより強烈です。というのもアガサ・クリスティが、自分の知っている実在の人物をモデルにしたような印象を読者は強く受けるからです。つまりある現実性を持った登場人物が『華麗なるアリバイ』では「単なる」登場人物になったのです。
——そういえば、あなたの実の娘であるアガット・ボニゼールも出演していますが、彼女は劇中で若者風のかなり汚い言葉遣いで話しています。非常に異質に響くと同時に、コメディ的要素としてもうまく機能していました。
PBちなみに彼女は現実ではあんな風に喋りませんよ。ちゃんと教育されていますからね(笑)。原作であの役は、もっと感じの悪い、コミュニストの少女なのですが——アガサ・クリスティにとっては、これこそ下劣で親不孝な年頃の極みです——、私は彼女にも変化を加えたわけです。
私にとって重要だったのは、登場人物たちのポートレート集を作ることでした。それに合う俳優たちを見つけ、彼らとともに生をつくりだしていく作業は非常に興味深かった。その意味でこれは遊戯的な作品だと言えましょう。
——タイトルについてお聞きします。『Le Grand Alibi』(『華麗なるアリバイ』の原題)は、アルフレッド・ヒッチコックの『舞台恐怖症stage fright』(1950年)の仏語題とまったく同じですね。
PBタイトルはもちろんですが、屋根の上のシーンにもヒッチコックへのほのめかしがあります。『めまい』(1958年)ですね。ヒッチコックは「誰がやったのか?」という規則を毛嫌いしてしました。ただ嫌いだと言いつつ、それを実践した作品はいくつもあります。
ちなみに屋根のシーンは……。そもそもこの作品は、たしかにそれなりの額とはいえ比較的限られた予算です。たとえば必要な特殊効果も予算のせいで叶いませんでした。だから屋根のシーンは特殊効果もなく、実際に俳優が宙を舞っているんですよ。
——フランソワ・トリュフォーは『映画術 ヒッチコック/トリュフォー』のなかで、『舞台恐怖症』を批判していますね。
PBたしかに『舞台恐怖症』はヒッチコックのなかでも傑作とは言えない作品でしょう。ヒッチコック自身、この作品をそれほど気に入っておらず、フランソワ・トリュフォーもまた「好きではない」と断言しています。とりわけ「嘘つきフラッシュ・バック」の手法を批判していました。
このタイトルを使ったのは、まず大きな理由があります。それはアガサ・クリスティの『The Hollow(ホロー荘の殺人)』というタイトルが非常に平板で、観客に何も訴えかけないと思ったからです。『Towards Zero(ゼロ時間へ)』『Crooked House(ねじれた家)』など、彼女の作品には一瞬で人目を引く見事なタイトルもありますが、この作品は残念ながらそうではなかった。それでプロデューサーに「Le Grand Alibi」を提案したら、権利的にも問題はないし、これでいこうと彼は言ってくれたのです。それにこのタイトルは作品のプロットとの関係で非常に興味深いと思えました。このプロットはまさに「アリバイ」の問題をベースにしながら、そこにはパラドクスがある。つまり通常「アリバイ」とは「どこか別の場所にいること」を意味するにもかかわらず、この場合では「その場所にいること」を意味してしまうわけです。
——今作の尺は93分ですが、あなたの作品はどれも、ほぼすべて90分前後に収まっています。作品の尺にはつねに配慮があるのでしょうか?
PBこのジャンルの作品は最大で1時間45分、それ以上長くてはいけません。私も編集段階でかなりのシーンを落としました。最初の編集バージョンは2時間強で、これは長すぎました。とにかくもっとも配慮したのは、最初の殺人が作品の半分あたりではなく、もう少し早めに来るようにすることでした。遅くとも3分の1あたりで起こらねばならないと考え、それが編集にも影響しましたね。それから冒頭の数シーンも削りました。たしかにそれらは登場人物たちの心理的な色合いを強くするには役立ちました。しかし同時に劇構造を決定的に傷つけてしまうシーンだったのです。天秤にかけた結果、やはり劇構造を優先させたわけです。
——また、この尺の短さはB級映画にも通じますね。
PBたしかに私はB級映画を非常に愛しています。その状況展開の素早さ、プロットの表層的な複雑さなど、まさにそれは自分にぴったりのフォーマットなのです。
——最初の殺人はプールで起こりますが、プールと殺人と言えば、どうしても『キャット・ピープル』(ジャック・ターナー監督/1942年)を思い出してしまいます。
PB『キャット・ピープル』は大好きな作品の1本です。ただし『華麗なるアリバイ』の殺人は真昼間で——これも原作通りです——、『キャット・ピープル』の方は暗闇のプールですよね。その恐怖の瞬間、観客には影しか見えない。とはいえ……、たしかに『華麗なるアリバイ』にはネコがたくさん出てきますからね(笑)。
私は「幻想映画cinéma fantastique」をどうしようもなく愛しているんです。そしてこのジャンルの作品をつくるのは、とりわけフランスというコンテキストにおいては、もっとも難しいように思えます。フランス映画は「幻想性」との関係が非常に薄い。日本、中国、ドイツ、イギリス、アメリカ、スペイン……、あらゆる国には非常に豊かで大衆的な「幻想映画」ジャンルが存在しますが、フランスだけがそうではない。もちろんそれぞれ「幻想映画」に取り組んだシネアストたちはいました。エドガー・アラン・ポーを手掛けたジャン・エプスタイン、ジョルジュ・フランジュ、ジャン・コクトー、それから『吸血鬼』のルイ・フイヤード……。たしかに各作品はありますが、しかしそれらは各々単独の作品であって、彼らは大衆的なシネアストというよりエリート的なシネアストです。つまり「作家の映画」ですね。ジャック・ターナーやジェス・フランコと同じような存在がフランスにはいまだいないのです。幻想的な要素を好んで作品に注入する作家たちはいますが、B級「幻想映画」はありません。アメリカでは、たとえばティーンむけの「幻想映画」——たとえばホラー映画ですね——がしっかりとありますが、それらは決して高級で偉大な映画ではなく、まさしく大衆に深く根を下ろしたものです。植物が育つための腐植土のようなものです。
——最初の殺人では観客に血がまったく見せられず、2番目の殺人では、少しグロテスクなほどに血が見せられますね。
PB最初の殺人のシーンでは、ほんの少しだけ血が見えます。実は当初、血がプールに広がるようにしたかったのですが、ゴア映画を作ってもしょうがないと思いやめました。2番目の殺人では、女優のノドが切られる殺人ですので、逆に血が必要でした。
最初の殺人に関しては、心臓に銃弾が達した場合、大量の出血があるのかどうかを医師に尋ねてみたんです。応えはノー。内出血が起こって全身が蒼白になるとのことでした。また口から血はでるのかどうかも尋ねました。これも答えはノー。肺に銃弾が達した場合のみ口から血が出るのだそうです。そうやって丹念に調べた結果、あそこには特別な何かは必要ないと判断しました。それに観客がいるのは、あくまでもアガサ・クリスティの物語であって、けっしてジェームズ・エルロイの物語ではありませんから。
——実は今作を見ながら、エドガー・アラン・ポーの『盗まれた手紙』を最初に思い出してしまいました。幻想性という意味でも、ポーに通じる点は多々あります。
PB嬉しいですね。私も『盗まれた』が頭にありました。衆人の目に曝されていながら隠されているものの問い……。『華麗なるアリバイ』の殺人者が施すのは、自分が犯人だと明らかになりながら、罪から免れ得るような演出=仕掛けです。そこには『盗まれた手紙』の構造と関係する何かがあります。そしてまた演出においても、明白であると同時に不可解な側面こそが必要だったのです。
——劇中でミュウ=ミュウのこんな台詞があります。「殺人ですって? 私は悪いイタズラか、演出だと思ったわ。まるで誰かが、それが実際に起こっていながら、それが起こったことを私に信じ込ませようとしているような感じね。でも、本当にそれは起こったのかしら?」。どこかポーを思わせる台詞です。
PBあれは原作には存在せず、まさしく私が書いた台詞です。最初のバージョンのシナリオではもっと長かったのですが——彼女の役はとにかくおしゃべりな女性にしたかったんです——、さすがに長すぎて切りました。とにかく、あの台詞はこの作品自体の問いを要約しているんです。

『華麗なるアリバイ』
2008年/93分/ヴィスタ/カラー
監督:パスカル・ボニゼール
原作:アガサ・クリスティ『ホロー荘の殺人』
脚本:パスカル・ボニゼール、ジェローム・ボジュール
出演:ミュウ・ミュウ、ランベール・ウィルソン、ピエール・アルディティ、ヴァレリア・ブルーニ=テデスキ、マチュー・ドゥミ、アンヌ・コンシニ
7月17日(土)、Bunkamuraル・シネマ他にて、華麗なるロードショー!
オフィシャルサイト:
http://aribai-movie.com/
© 2008 - SBS FILMS - MEDUSA FILM
パスカル・ボニゼール Pascal BONITZER
1946年パリ生まれ。「カイエ・デュ・シネマ」誌を中心に批評家・理論家として活動した後、ジャック・リヴェットやアンドレ・テシネの脚本家として活躍。短編制作を経て長編『アンコール Encore』(96)で監督デビュー後は、コンスタントに作品を発表しつづけている。
フィルモグラフィ(監督作品のみ)
『アンコール Encore』(96)
『ロベールとは無関係 Rien sur Robert』(99)
『かすり傷 Petites coupures』(03)
『君を想う Je pense à vous』(06)
『華麗なるアリバイ』(07)
以前のボニゼールのインタヴューはコチラ:
・「重要なのはバルザックを翻案することではなく、映画をバルザックに翻案することです」( http://www.nobodymag.com/boni/index.html" http://www.nobodymag.com/boni/index.html)
・「もっと淫らに、もっと幻想的に」(「nobody」本誌29号所収)
取材・構成=松井宏、写真=宮一紀