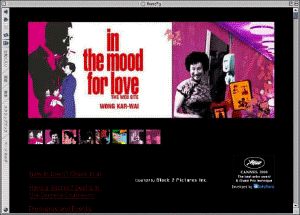nobody/Journal/'01_04
top >>
4月30日(日)
『ドルチェ-優しく』アレクサンドル・ソクーロフ
この映像に冠された「ドルチェ」という題名は、フェリーニの映画『ドルチェ・ヴィータ(甘い生活)』を嫌でも思い起こさせる。過ぎ去った長い年月を回想し一人独白する老女。彼女の人生はどうやら辛く痛々しい日々でもあったのだが、「回想」となり得た時点でそれらは愛しい日々へと転換することにもなる。そんな彼女や障害を抱える娘マヤを捉える映像は、確かに静かで穏やかで、「優しい」ヴェールで島尾ミホという人物を包みこみ、その存在を丹念に肯定していくかのようだ。正方形に近いスクリーンはつまりポラロイド写
真のことであり、過ぎ去った時間への憧憬をこれでもかと呼び寄せる。
しかし、そこに聞こえる音はどうだろう。ナレーションだけに留まらず島尾の台詞を吹き替えもするソクーロフ監督のロシア語。上映時間中ずっと消えることのない打ち寄せる波の音、吹き付ける風の音、そして豪雨。島尾が畳の上をちょっと動いたり、階段を上り下りするだけでミシミシギシギシ、パリパリと音は発生してしまう。はっきり言ってこれらの音たちはかなり耳障りというか、暴力的ですらある。こんな迂闊な言い方をして良ければ、唯一映像のトーンと「合って」いる島尾の独白の声、慣れない演技ではあるが一人の老女の真意を含んでいよう重要な言葉の数々がこれらの音たちによってないがしろにされ、まるでどうでもいいことのように隅に追いやられてしまう。
マイクの拾った音というのはある意味残酷だ。畳がバリバリ言う音なんか誰も聞きたくはないのだ、もう少し沈黙していたいはずなのだ。束の間でも沈黙を過ごすことは、「一定の長さ」である過ぎ行った時間への自覚でもあるのではないだろうか。そしてこの自覚の獲得は、達成感というと言い過ぎかもしれないが、「そしてそれは終わったのだ・つまりそれはかつて在ったのだ」という後日談的な認識を与えるだろう。だが、ここではそういった沈黙の作用は許されない。畳は容赦なくバリバリ言うし、ソクーロフは島尾のゆっくりとした日本語に休みなくロシア語を重ね続けるし、海も林も近いらしいその家の周辺の自然はざわざわと我々の耳に届きつづける。この映像を、島尾を、観客を、過去への愛しさを獲得する前にばらばらに解体しようと拮抗するかのように。
では、それらの音に敗北を記する「島尾」がここには映っているのだろうか。いやそうではない。むしろこの『ドルチェ』において自分から沈黙を破ろうとしているのが島尾ミホという人物であり、故にこれらの音は拾い上げられ、鳴り続けねばならなかったに違いない。
物音一つせず静まり返った家の玄関。階段をギシギシ言わせて娘が降りてくる。言葉を喋らない娘が発せられるのはこの音だけだ。そんな娘に、島尾は愛情を込めて話しかけることを選んでいるではないか。「あの子はもう沈黙の世界に慣れたかしら」「神様は何故あの子にこんな試練を与えたのかしら」と洩らしながら決して自分の共有できない世界に娘が生きていることを心配するのと同時に、「あの子は強いから大丈夫」と自らを励ますのが彼女だ。
だから、彼女をヴィデオに収めるためには、音によって沈黙が破られ続けなければいけない。彼女は自分の人生をただ休みなく、喋り続けなければならない。その身体や言葉が他の様々な外部の音によって追いやられ続けるとしても。それがつまり、この老女の生き様を映すことなのだ。娘が部屋のドアを開けて音も立てずこちらに向かって笑いかけた時、島尾は何とも言えないような複雑な表情を浮かべる。それはそのような自分の生き様がどんなに願ったところで自分と娘とを繋がないであろう事へのちょっとした諦めや確認や寂寥感なのかもしれない。しかしそれでも沈黙に身を委ねようとしてはならない。
ところで映像の方に話を戻すと、いや、それは一見穏やかには見えるが本当に肯定的で優しいものだったろうか。最初のシーンでは夫・敏雄や家族との写
真が一枚、また一枚とめくられていく。そこには木の枝葉か何かの映像も重ねられていて、そのざわざわとした動きに惑わされるように写
真となった過去の一瞬たちは何となく所在無げに澱んでいた。「母が死んだ」と語るやいなや写
真に写った母親の姿だけが暗く黒くなっていくのもかなり陰鬱だ。部屋にたたずんでいる島尾の顔がぼうっと見えなくなるのもしばしば。極めつけは先ほどのドア越しに娘がいるシーンで、粒子も粗いし真っ暗なのに、笑う顔が一つこっちを向いていることだけははっきり分かってしまって、本当に恐ろしいものを見たような気分にさせられたものだ。そんな風に列挙すれば、ここに登場する映像や音のそれぞれはまるで「ドルチェ/甘美」なんかではないということか。
しかしそれは「甘美さ」についての誤りである。「甘さ」を現在時制とするならば「甘美さ」とは複合過去なのだから。撮り直せもまた焼き直せもしないポラロイドが愛しいのは「もう一度見る」ことによって過去の一点と今現在の遠さを見せつけられるからで、その痛みと共にしか甘美さはない。愛する母・父・夫をとっくに失い、娘は共有できぬ
世界に生き、後に遺された島尾はそれでも現在に生きている。今生まれたばかりの音を一人聞き続け、自分も音を出し続ける齢を重ねた人間の姿こそは甘美的なのかもしれない。ヴィデオ装置によって実現された映像と音は、この人物に辛く当たることでその人生の甘美さを際立たせていかねばならない。
ガラス越しの彼女の顔、手前の窓枠に落ちて跳ねあがる幾つもの雨粒。もちろん雨音は過度に聞こえて来るのだが、そのポロンポロンという雨音と老女の穏やかとも虚ろとも言える表情が一緒になったワンシーンが最後に登場する。それが意外にも、夢のように美しい。映像と音が気まぐれに結託して彼女を祝福しているのだろうか。しかしそれは日常から切り離された時間・ひと時の逃げ場のようで、それよりも、うっとうしく違和感のある過度な音ともやもやした映像、そちらに身を置かなければ…。何の為に?自分が今ここに居る為に。だからまた再び、彼女は畳をミシミシパリパリ言わせる現在を続行していかねばならないのだ。
(加藤千晶)
4月29日(日)
『花様年華』ウォン・カーウァイ
香港、1962年、とあるアパートの階段で、見知らぬ男女が一瞬すれ違う。お互いの顔を確認し、素早く視線をそらし、肩が触れないよう身をかわし、一瞬の交錯のあと、彼らは正反対の方向へ、歩みを進める。執拗にアングルが変えられ、ときにはフィルムスピードを変化させながら、カメラは彼らの一瞬の交錯を捉え続ける。その瞬間、男と女は、笑っているようで、戸惑っているようで、なんとも感情を判別
しがたい、曖昧な表情を見せる。
しかし、何度も何度も繰り返される交錯、その度に流れ始めるインストのBGM、その正確な反復が私たちに気付かせることとは、「曖昧」と総称してしまったトニー・レオンとマギー・チャンが浮かべる表情の差異だ。彼らの顔の運動は、何某かの感情を表象するためにあるのではないという単純な事実だ。男の眉尻がふっとさがり、女の口の端が微妙に歪むのが、一回性の事件としてフィルムに刻印される。その「現実」は映像効果
に転換する一歩手前で、ひらりと身をかわす。その「身をかわす」という身振りは、映像技術の展示会に陥りかけるウォン・カーウァイという映画作家が、絶妙なポイントでその身をかわす身振りと正確に同一のものだ。その身振りによって、『花様年華』というフィルムは、のっぺりとしたイメージの連鎖に留まることなく、揺れ動く距離の記録となる。
フィルムの終盤、「秘密を抱えた人間がどうするか、知っているか?」と男は口にする。「大きな木に空いた穴を見つけて、その穴に秘密を吹き込むんだ。そして穴を土で埋める」。この後、突然現れるアンコールワットの遺跡で、その言葉通
りに行動する男の姿を私たちは目にする。『花様年華』というフィルムは、この男の甘く切ない思い出話だったというわけか?そして穴に秘密を吹き込む男を後ろから見つめる幼い僧同様、私たちはその証人となるべくこのフィルムを見つめるのだろうか?
答えは、そうであり、またそうではない。『花様年華』で語られるのは、たしかに男の思い出話だ。思い出話の危険、それは時間的な距離と説話的な距離のなさが生み出す安定だろう。私たちの体験は、思い出話になった瞬間に、説明のつかない過剰な要素がことごとく削られ、ものわかりのいい、優しげな「お話」になる。しかし、映画は「お話」に抵抗する。カメラは時間的な距離を一瞬で無効化し、説話的な距離を一気に増加させる。映画によって、男の思い出話は体験にきわめて近い何かになる。男の手をするりとかわす女の手。女がステーキを切る音。風に揺れる観葉植物と煙草の煙…。思い出話では摩滅してしまうような差異が、カメラによってもう一度表象される。
かつて荻野洋一はウォン・カーウァイの『恋する惑星』を評して「目的化されない空隙だらけの映画」と述べた(「カイエ・デュ・シネマ・ジャポン16」)。映画はものわかりのよい「お話」ではないし、「お話」に回収されえない「空隙」を表現するものでもない。空隙を埋めようと揺れ動くイメージの流動性、それ自体が「映画」だ。それが「体験」に、「現実」に、きわめて近い何かだ。『花様年華』において、ウォン・カーウァイは堅固な構築を選択しながら、それに同化することなく、かといって一定の距離を保つ方法を選ぶこともなく、構築が揺れ動く様をそのまま記録してみせた。それがあの反復であり、俳優の「曖昧な」表情である。あなたはマギー・チャンがコーヒーをかき回す際にたてたスプーンがカップの底をこする音を、あるいは彼女が留守中の男の部屋で座ったソファの軋む音を、聞いただろうか?たとえばあの音が、「目的化されない空隙」であり、私たちと「映画」が一瞬交錯し、身をかわしたときの距離である。
(志賀謙太)
4月28日(土)
『ファクトリーの時代』ジョナス・メカス
一体これはなんのだ…?
おそらく家庭用ビデオに毛がはえた程度の代物で撮られたであろう粗い映像に現れたジョナス・メカスは、今日はアンディ・ウォーホルのファクトリーについて話そう、と自身の想い出も交えながら、ゆっくりと語り始める。自分の部屋の中で、自分に向けてカメラを据え付けただけの一人称で。時折徐に、そうそうその頃の写
真があったはずだ、と据え置かれたカメラを手に持ち、家庭用ビデオ特有のがとごと耳障りな音をたてながら、写
真を見せてくれるのだが、手持ちであるためにぶれまくる。かつて
ファクトリーがあった場所に行ってみよう、とカメラマン兼ナレーション兼インタビュアーのメカスは、今は空き地となったその場所へと赴き、ニューヨークの路地を散歩する人を捕まえて、ここにかつて何があったか知っているか、などと不躾に質問する。友人の家に訪ねては、ファクトリーに乾杯、などと恥ずかしいくらい昔の想い出に浸っているようにも見える。
その友人がファクトリーがあったビルディングが写った写真を持ち出して来て、メカスは、これがファクトリーだ、とそのビルディングの4階部分にカメラを(ぶれながら)ズームをさせるのだが、ファクトリーが3階にあったか4階にあったか自信がない、などとメカス自身が語っていたことを思い出し、おいおい本当にその場所にファクトリーがあったのか、と不安に思っていると、その友人が、違う違う、ファクトリーはその隣のビルディングだよ、と指摘し、メカスも、そうか、ならばこれがファクトリーだ、と隣のビルディングにもう一度ズームアップするのだが、今度はピントが合っておらず、ぼやぼやの映像が見えるだけであるのだから、微塵の説得力もないというものだ。
冷静に考えて…、こんな映画が面白いはずがない、つまらなく、退屈なはずだ…、なのに、私は、にもかかわらず、3日でできたしまったようなこの作品に、ひかれてしまい、この作品が重要であるように思えて仕方なかった。メカスは自分が死んだら消えてしまう彼の記憶の保存を試みているのだろうか? だが、同時に、ぼやけて全く説得力のないファクトリーの写
真のごとく、それらメカスの記憶も危うく、かつ再構築不可能で表象不可能である、という認識があるようでもある。ただしその認識は、
ニヒルでも、シニカルでも、悲愴的でもない。彼の記憶が表象不可能である、という認識に対する締念は感じられないのだ。ただそんな認識などないかのごとく振るまい、しかしその振るまいが逆にその認識を滑稽に強調していくようである。いや、そう言ってしまうのもどうにもしっくりこない…。
確かに、メカスが語るアンディ・ウォーホルやファクトリーの時代の話は充分にエキサイティングなのだが、やはりメカスにとってのそれらの出来事の強度を思えば、私たちにとっては決定的に他人事でしかないようでもある。例えば、ぶれまくるフレームの中の、粗く、ピントの弱い、退屈以外のなにものでもないはずの映像に現れる、ファクトリーの跡地やら、ファクトリーやファクトリー縁りの人々の写
真…。それらはメカス自身が手持ちカメラで捉えたものである。それらの映像がメカスの視線と一致する、などとはとても言えないが、それらの映像がメカスの瞳に飛び込んで来た時の、彼の記憶の奥底で蠢く映像が存在するであろうことを、私たちが想像する、あるいは絶望的に夢想することはできないだろうか。いや、それさえ許されないのだとしたら、背後にいる幽霊を感知するごとく背筋をゾクゾクさせることぐらいは…。
(新垣一平)
4月27日
『青い乳房』鈴木清順
産婦人科医院の待合室に赤ん坊の泣き声が響く。
1人のチンピラが父親になる瞬間、その時彼は長椅子の上で仰向けに寝転がったままの姿勢で、カメラはその顔を逆さのままで捉えた。その時点で彼に父親としての自覚はまだ無い。しかし世界を逆さまに見ながら我が子の泣き声を聞いたその時、彼は間違いなく父親に(生まれ)変わったのだ。
我々が「過去」から切り離される、あるいは「過去」を呼び起こす瞬間、それは一瞬のことであっても様々な要因が複雑に絡んでいるはずであり、だからこそそれを他者に伝えることは困難だ。そして鈴木清順はそれを承知した上で、いや承知しているからこそ、その瞬間を丁寧に説明したりはしない。例えばその後父性に目覚めたらしいそのチンピラが主人公の若いカップル(チンピラは彼らを悪の道へ引きずりこもうとしていた張本人)に、「悪い奴らと付き合うなよ。」とサラリと言ってのける。そのあまりの身代りの速さに人々は「おいおい」とあっけに取られ、実際映画館では笑いが起きた。
だが鈴木清順は決してその瞬間を伝えることを放棄しているわけではない。彼は説明し我々に解らせようとするのではなく、その瞬間を我々に何よりもまず見せることに、言い返るならば、その瞬間の時間・空間を文字通
り瞬時に一気に切り取ることに徹しているのだ。だから若い義母が1枚の絵画から暗い過去を呼び起こし、現在の時間軸から切り離された瞬間、彼女の周囲は暗転する。安易?単純な演出?その通
りかもしれない、が、それで良いではないか。これほど瞬時に単純にその瞬間のまま捉えられる人が他にいるだろうか。
そしてその演出は瞬間に限らず、この映画全体に行き渡っている。人物が1階から2階に上がればカメラはそのまま垂直に移動し、1階に降りれば垂直に下降する。車が猛スピードで走るとカメラは同じ流れに沿って平行に移動し、Uターンと同時にカメラも平行に逆流する。そういったカメラの、フレームの運動によって我々は時間と空間の交差を感じるのではなく、はっきりと自分の目で「見る」のだ。
映画は理解するのものでも、感じ取るものでもない。映画は何よりもまず見るものなのだ。映画館で「今の映画わけわかんなかった〜」などとぬ
かす若者に遭遇したら、即刻清順先生の映画を見に行かせるべし!
(黒岩幹子)
4月21日(土)
『花様年華』ウォン・カーウァイ
レッスン。
枠を設ける。
枠を設けてみること、つまりマギー・チャン演じるチャンとトニ−・レオン演じるチャウの二人にさらに「夫婦」という枠をおしつける、「夫婦」を演じさせること。「わたし知ってるのよ」、「何が」、危機に瀕した夫婦によくあるありきたりの会話が重ねられ、ついには「妻」の平手打ちが「夫」の頬へ、堪えきれなくなり泣き崩れる「妻」・・・。直前のNGテイクを知っている僕達は今回のシーンでも「夫婦」という枠の存在(を知っていること)によって何の不安もなく「妻」と「夫」をみていたはず・・・、なのに、どうだろう、チャンの泣き崩れる顔は。そこにいる女の顔は果
たして「夫」を愛する「妻」の顔か、それともチャウを愛するチャンの顔か(はたまたオリヴィエ・アサイヤスを愛するマギー・チャンの顔か!?)、二人は枠のなかの「夫婦」なのか、それともチャンとチャウなのか。どちらが正しいのか、そんなことは分かるはずもないし、分からなくたって別
にいい。ただ僕達はこの枠の攪乱するその有り様を受け入れること、そこに開かれてあること、それだけでよし。
すなわちこれがレッスンの成果。
さて、さらなる強力な「枠」、映画が映画であるという「枠」、これをどうやって攪乱させるのか。といっても当然、絶対的に物質としてあるカメラフレームそのものをとっぱらったり、フニャフニャにしたりなんてできるわけもない。しかし、映画において枠は何も物質としてのカメラフレームばかりではなくて、カメラを向けた時点で俳優は登場人物となるわけだし(<ドキュメンタリー>と呼ばれる映画もそれは免れえない)、上映時間だって無際限に続くはずもないし、あるいは実際の撮影に際しての様々な枠、制約(光、音、ロケ地・・・)や、経済的な枠だって厳然と存在するし、物語すら時として枠になることもあるわけだ。
こうした諸々の「枠」を、あたかもそれが存在しないかのように振る舞うこと、何をカメラフレームの枠内にとらえ、何をその外に隠し、どんな光や音を拾い、また隠すか、さらには思うままにセットを組み立ててみる。それらを、物語を語る際の経済性と如何にうまく結び付けてゆくか、枠を如何にして意識しない/させないようにするか、「見事な」、「快い」演出にどのように到達するか。
しかし、「枠」のなかの心地よさがふと、とんでもない苦痛と苛立ちに変わってしまうこともある。嫌でも「枠」を意識してしまうこと。その苛立ちから、例えば、眼前の「豊かさ」、その「豊かさ」の無秩序を無秩序として受け入れてみること、「枠」が存在しないかのように振る舞うのではなく、その無秩序さで「枠」を攪乱させてみること。あるいは、異様なまでの過剰さを「枠」自身に与えることで、それを撹乱させ露出させてみること(ソクーロフの使う異様な過剰さを持つレンズ、異様な過剰さを持つセット)。あるいは他にも・・・。
つまり『花様年華』において、愛が生まれたのかもしれないあの香港のアパート、チャウが勤めるシンガポールの新聞社、そしてアンコールワットとを、カメラの運動によって接続してみること。香港で、シンガポールで何度も繰り返される奇妙で過剰な横移動は、すべてその接続のためである。そうやって「枠」を攪乱させてみること、カメラという枠を使いながら「アンコールワット/アパート/新聞社」、または「カンボジア/香港/シンガポール」と、隣接させてみること。あるいはさらに・・・。
映画を撮るに際してのあらゆるレヴェルの枠を連動させながら忘れさろうとすること、いかに全てを流通
させるか、いかにして自らを危険に曝すことなく枠をはめてゆくか。しかしながら、その枠を(再)発見してしまった時点から、枠は自らの実存すらも縛りつけるなんとも不自由なものとして浮かび上がってくる。それが存在しないように全てを連動させなければならなかった枠が、それゆえに、全てが連動した不自由極まりない「枠」となる。そして、その「枠」を攪乱させること(そうでなくともその時点から出発すること)、それは既に自らもが危険に曝されそこに巻き込まれてあることなのだ。「倫理的」であること、「政治的」であること、ドゥルーズが言うように、「少数民族が、(マイナーの言語によってではなく)広く使われている言語を用いて創造する」こと、「プラハのユダヤ人が、(プラハの)ドイツ語で書く」こと、つまりカフカのように創造すること・・・、そうやって『Nobadys Diary』を更新させてゆくこと・・・、レッスンの成果
を活かすこと。
(松井宏)
4月18日(水)
『ミドル・オブ・ザ・モーメント』ニコラ・ハンベルト、ヴェルナー・ペンツェル
映画館の暗闇の中蹲る身体は一体何を待ち望むというのだろうか? 己の言葉をかき消された、周囲の世界を遮断された、暗闇の中から、スクリーンの向こう側へと、何処か別
のここではない何処かへと、自らが誘われる瞬間を待ち望んでいるとでもいうのだろうか? だがその欲望は真夏の太陽照りつけるハリウッド(なり東京なりパリなり)の映画館の中にいながら『カサブランカ』の哀愁の霧の中を酔いしれたように己の魂を漂わせることと必ずしも一致するわけではない。とりあえず乱暴に比喩的に『ミドル・オブ・ザ・モーメント』に関連づけて言い表わすなら、それは遊牧民的欲望である、とすることができるだろう。だが、スクリーンの前でじっと座る行為と、遊牧民(そしてあるいはサーカスの一団)の非定住型の絶えまない移動が、如何に重なり合わさると言うのか?
遊牧民の一人は砂漠の砂の上に慣れた手付きで模様を作る。そして彼は模様を砂の上に形作るや否やその模様を消しさり、また平になった砂の上に模様を作り出す。砂の上で消しては形作られ、消しては形作られる模様。その行為には極めて呪術的な印象があり、ある種の目的と名を持った儀式か占いかもしれないが、そんなことつゆ知らない私の目に焼きつけられるのは、間断なき模様の生成と消滅のはざまに横たわる、一見何でもないような砂の上のありえないはずの模様である…、あるいはこう言えばいいだろうか、ある模様と次の模様の間に打ち捨てられてしまったような、もしくは知覚されることを頑として拒むような、模様…。
ここでまた、怠惰な比喩を使うことを許してもらえるのなら、こう言えるかもしれない。それはある模様=映像(あるいはショット、フレーム、1コマ…)と次の模様=映像(あるいはショット、フレーム、1コマ…)との間に広がる完全な「闇」である、と。
middle of the moment. そう命名しうる何か。このフィルムは、遊牧民トゥアレグ、前衛的なサーカスの一団「シルク・オー」、老詩人ロバート・ラックスの姿を捉えているらしく、フレッド・フリスの音楽を流しているらしい。「らしい」とい
うのは気取った物言いだが、そのような言い方をするのは、もちろんこれらの固有名を事前の情報で私たちは知っているのだが(私自身このフィルムの上映へと馳せ参じた理由の一つはフレッド・フリスという固有名だ)、フィルム自体は決してその固有名を標榜してはいないからだ。この傑作はそれらを弁証法的に繋ぎあわせたり、何がしか通
奏するものを暴きたてようとしたり、これといった感慨もない身ぶりで暴力的に併置するわけでもなく、ただ静かに、ある模様=映像と別
の模様=映像を連続させ、そのことによってその「はざま」を垣間見ようと、あるいは映画館の闇に潜む瞳に垣間見させようとしているようだ。その時私たちは、常に映画が進行してくれること、模様=映像が次から次へと流れさっていってくれることを希求し始める。そうでなければ「はざま」などやって来はしないからだ。やや迂闊な言いきりであると謗られようと、その欲望を遊牧民的と言ってみたい。
(新垣一平)
4月15日(日)
『僕の小さな恋人たち』ジャン・ユスターシュ
ヌーヴェル・ヴァーグという映画運動を準備した論考のひとつとされる「映画−空間の芸術」において、著者のエリック・ロメールは映画の本質は文学的な脚本でも絵画のような構図でも効率的なモンタージュ技術でもなくて、カメラの前の空間、それもフレームに区切られた平面として写るそれではなくて、現実にカメラの上下左右に広がる空間そのものなのだ、ということを手を変え品を変え示している。要するにそれは、カメラはレンズの前の事物を記録する−それしかできない−装置であるという特性に徹底的に根ざした考え方で、このような発想が生まれた時点で、映画はふわふわとした夢である資格を失って、私たちが生きる現実と地続きのものになる。
だからといって、カメラを担いで適当に街をふらつけばそれで映画が出来上がるかといえばそんなわけはなくて、人がひたすらにただ歩いているとか車が渋滞で延々動かないといった映像を好んで見る人はあまりいないし、普通は映画と呼ばれない。ならば、多くの人が好んでみる映像、例えば人が殺される映像や男の人と女の人が性器の出し入れをしている映像が、そのまま映画になるかというとそういうわけでもなくて、それらは「カメラが収めた衝撃的瞬間」とか「わいせつな映像」とか呼ばれて、あくまで映画ではなく映像に留まるものとして扱われる。子供や老人をいじめる映像も、人は好んで見るが、それは「さんまのからくりテレビ」なのでやはり映画ではない。
では映画とは何か、という問いに答えるのは、なかなかにやっかいな問題を多々含んでいるけれど、とりあえずここでは記録装置が残した映像と音を、ある意図に沿って組み合わせ、つないだものである、という答えを用意することにする。そこで映画監督たちは、そうそう人を殺したり、セックスをさせたり、子供を泣かせてばかりもしていられない以上、「人がひたすらただ歩いている」といったどうということない出来事を、映像として如何に見せるか、そしてそれをどうつなぐかという選択に知恵を搾ることになる。
そうしてできあがった映画を見たときに、選択の基準となったであろう監督の意図は時系列に沿った形でしか現れないので、普通の観客はその意図の集積を「物語」として認識する。それじゃあ映画は結局物語を語るもので、ふわふわした夢のままではないか、というと、それはもうぜんぜん違って、記録装置というカメラの特性を強く意識する映画監督は、事前に用意した物語を映像によって語るという素朴な映画を信じられなくなった。
カメラが残す映像は物語を説明するために存在するのではなくて、本質的には何の意味もなく現実に存在した事物のコピーであり、そのことを重大なことと考えるか取るに足らぬ些細なことだと考えるかは人によって違うだろうが、ロメールの論考はそれが映画のなかで一番重要な問題だと言い切っていて、そのように考える映画監督は必然的に物語から映画を考えるのではなく、目の前の現実から映画を考えるようになる。
だから結果的に出来上がった映画が雄弁に物語を語っているように見えても、それがその物語から作り出されたものであるか、現実から作り出した結果としてその物語が浮かび上がってきたのかによって、映画はまったく異なるものになる。
実際エリック・ロメールの長編デヴュー作である『獅子座』は、小金持ちの青年がだんだん貧乏になっていって、浮浪者同然となったあげく、映画のラストで突然伯母の遺産を相続することになって金持ちに戻る、という双六のような単純な物語を一時間半かけて素直に語っているようにも見えるフィルムだ。しかしそこで実際目にするものは、夏の人気のないパリの街並みであり、揺らめく川面であり、ほとんど表情を変えないジェス・ハーンであり、といった現実にカメラの前に存在した事物である。ロメールはこのろくでもない男の悲哀やらおかしみやらを描くために、それらの映像を作り出したわけではなくて、カメラを担いで街へ出て現実の事物を映し出し、それをつなげて提示することで、結果としてその単純な物語を浮かび上がらせる。ロメールにおいて、この相関関係は不可逆なのだ。
だから私たちが『獅子座』を見て、パリの町を彷徨うジェス・ハーンを心の底から暑苦しいと感じ、ラストに車の上で喜ぶ彼の変わらないろくでなしっぷりに爆笑するのも、ロメールが巧みな話者だからということではなく、キャスティング、ロケーション、プロットといった映画の企画自体が優れていて、彼にはその意図を映像として示す確かな演出能力があるからで、アンドレ・バザンとロベルト・ロッセリーニというふたつの固有名以後、映画的才能とは物語を巧みに語ることでも美しい映像を撮ることでもなくて、ロメールみたいな人のことを指すようになる。
 何故ロメールについてうだうだと書いたかといえば、ジャン・ユスターシュの『ぼくの小さな恋人たち』を見たからで、この映画を見てまず連想したのが『獅子座』だった。『ぼくの小さな恋人たち』では、サーカスの設営地に響く木槌の音や、ダニエルの無表情っぷりや、ラリナスという村で木々を揺らす風や、刻一刻と色を変えていく日の光や、そういったすべての構成要素が結果
的にあるひとつ物語を浮かび上がらせる。その物語はとても単純なものだろうし、もっといえば、ありふれた退屈なものかもしれない。しかしこの映画には、物語を異化したり複雑にしたりで忙しい映画群からは感じることの少ない魅力に溢れている。その魅力はもしかしたら「豊かさ」とでも呼べるのかもしれないが、もしそう呼ぶとしてもそれは物語が豊かなのではなく、監督のユスターシュが豊かなのでもなくて、カメラの前の空間が豊かだったのだ。その豊かさをきちんと提示すること。それがユスターシュの意図であり、私たちが「物語」と呼ぶものの力だ。
何故ロメールについてうだうだと書いたかといえば、ジャン・ユスターシュの『ぼくの小さな恋人たち』を見たからで、この映画を見てまず連想したのが『獅子座』だった。『ぼくの小さな恋人たち』では、サーカスの設営地に響く木槌の音や、ダニエルの無表情っぷりや、ラリナスという村で木々を揺らす風や、刻一刻と色を変えていく日の光や、そういったすべての構成要素が結果
的にあるひとつ物語を浮かび上がらせる。その物語はとても単純なものだろうし、もっといえば、ありふれた退屈なものかもしれない。しかしこの映画には、物語を異化したり複雑にしたりで忙しい映画群からは感じることの少ない魅力に溢れている。その魅力はもしかしたら「豊かさ」とでも呼べるのかもしれないが、もしそう呼ぶとしてもそれは物語が豊かなのではなく、監督のユスターシュが豊かなのでもなくて、カメラの前の空間が豊かだったのだ。その豊かさをきちんと提示すること。それがユスターシュの意図であり、私たちが「物語」と呼ぶものの力だ。
私たちは、退屈しながらでもダニエルの身体を二時間見つづけることで、例えば田舎町の野原という空間が最初と最後で随分と表情を変えていることに気付く。だから言うまでもないことだけれど、映画においては退屈と面白さは共存する。ここで私たちは青山真治の『ユリイカ』というフィルムを思い出してもよい。映画的才能の持ち主が単純な物語を浮かび上がらせることに成功したときに、その映画が現代において如何にラディカルで力強いフィルムになるかは、この映画が十分に示してくれた。『ユリイカ』が現代的な映画であるのと同程度に、『ぼくの小さな恋人たち』は現代的であるのだ。黒沢清が『ユリイカ』にむけた最大級の賛辞、「なんだか知らんが飽きない」という言葉を『ぼくの小さな恋人たち』にも捧げたいと思う。
しかし拘ってしまうのだが、ダニエルがキスをする女の子があまりに幼いのでびっくりした。まあダニエルとだけなら、彼はロリコンということで納得するのだが、16,7歳にしか見えないナンパ仲間の男の子たちが彼女を取り合っているのだ。だってどう見たって10歳そこそこですぜ。また彼女もナンパにちゃんと対応してるし。どうなってんのよ、フランス。私なんて10歳ったら、野球ですよ。サッカーですよ。「キャプテン翼」ごっこで朝から晩までドライブシュートの練習ですよ。ナンパだなんて、そんなアダルトなこと思いつきもしなかった。悔しい。いや、別
に悔しくはないが、なんだろう。私が球蹴ったり、棒振りまわしてたときに、フランスの田舎町では同い年の女の子が玉
吸ったり、棒舐めたりしているかと思うと。なんでしょう?…いいの、フランス?
(志賀謙太)
4月12日(木)
『アリックスの写真』ジャン・ユスターシュ
アリックスの写真は、いつ完成するのだろうか。
アリックスが彼女のカメラのファインダーを覗き、構図を決定した瞬間か。そして、シャッターレリーズを切った瞬間か。それとも、彼女がボリス・ユスターシュに見せるプリントの中に、彼女のものではないネガを焼いたプリントがあったり重ね焼きをしたプリントがあったように、印画紙に像を焼きつけた瞬間か。
いや、そのどれでもないだろう。そして、少なくともこの映画が見せ続ける、プリントを前にした時の彼女の言葉はそうした如何なる瞬間とも乖離しているはずだ。言葉を失わずしてフィルムに像を焼きつけることが、どんな写
真家に出来るというのだろうか。
すると、この映画がスクリーンの左側に絶えず見せるアリックスという女性は、一体、誰だ。
中学生の頃であるから随分前になるが、「激烈バカ」という4コママンガにこういうのがあった。
1コマ目、少年の映ったスナップ写真。
2コマ目、その写真を得意げに友人に見せるその少年、「どうだ、怖いだろ、心霊写
真だぞ!」。
3コマ目、友人、「何も映ってないじゃないか!」。
4コマ目、少年、「違うんだよ、これは、幽霊が撮っているんだよ。」
単にそれだけのマンガに僕は何とも言えない恐怖感を抱いたのを覚えている。心霊写
真とは、存在しないはずの幽霊が写真という「真実を映した(とする)像」の中に存在してしまうからこそ恐ろしいはずではないか。仮にも、少年はシャッタータイマーを用いていたかも知れないし、ひょっとしたら別
の友人がシャッターを切ったのかも知れない。しかし、少年は「心霊写真だぞ!」と言うことによって、友人に、写
真の中には何か得体の知れないものが「存在する」という意識を与えたのだ。それは、像=存在として「何か」を映すという写
真のテーゼに何かしらの異義を申し立てているかのようだ。
映画の後半、アリックスは彼女らしき人物の像が映っていないプリントを前に、「ここにいるのが私よ」というような言葉を発する。それまでの写
真と彼女の言葉によって囲われてきた、ロンドンのホテルだとか3年前だとかいった時空の連続性は、この瞬間にあっさりと崩れ去る。しかし、それは単に映像と言葉がズレることによって生じる写
真映像のリアリズムに対する問題提起という極めてネガティヴなものではなく、むしろ、アリックス自身が真にプリントに存在する為のこの上ないポジティヴな衝動の現出なのだ。おそらく、彼女はレンズの前にはいない。ただ、ファインダーを覗いているに過ぎない。だが、そうして映された写
真において「非存在」でありながら、「存在する」ために彼女は自身を「言葉」そのものと化すことにより写
真を完成させる。「言葉」という像を犠牲にして。しかし、それが写真家の宿命だ。
そして、『アリックスの写真』というわずか20分足らずのフィルムは、そうした「非存在」に坑がうアリックスという女性、または像=存在を信じる写
真家の姿を二重に「プリント」し、確かにアリックスという「言葉」を像として映し出している素晴らしいフィルムだ。
(酒井航介)
4月6日(金)
『花様年華』ウォン・カーウァイ
物語は極めてシンプルだ。隣に住む夫婦が、互いの旦那、妻の不倫疑惑をきっかけに徐々に近づくようになり、次第に本気で愛するようになってゆく。スクリーンにはマギー・チャンとトニー・レオン以外の人物はほとんどと言って良いほど映らず、この映画の上映中我々は始終、この2人が近づいては離れ、近づいてはまた離れるのを繰り返す恋愛の駆け引きに向き合っている。これらの映像はトニー・レオン扮する男の記憶としての時間であり、またマギー・チャン扮する女の記憶としての時間でもあり、別
の場所にあったそれら二つの時間軸が近づき、離れ、瞬間的にではあるが交わり、浸透するのだが、その彼らの極めて個人的な時間、記憶の背後には、年号や「歴史」によって刻まれる揺るぎ無い時間もまた流れている。(ド・ゴール大統領のカンボジア訪問のニュース映像、アメリカに移住する隣人。)その「歴史」が、特にこの映画の終盤目まぐるしく移行するから、だからこそ余計にそれまで我々が向き合っていた彼らの個人的な時間が、ぽっかりと宙に浮かんでいるようにように、歴史の時間軸からは取り残されてしまったように見えるのである。まるで度々スクリーンに映し出される時計のように、ぽっかりと。
男は常に過去ばかりを見つめている。ガラス越しに眺めるように、ぼんやりと..。
確かこんな言葉でこの映画は終わっていたように記憶しているが、2人のプラトニックな恋愛を描いた映像が回想であるということを最後に示唆してはいるものの、それらの映像はガラス越しに眺めたような過去の映像では全くない。画面
はけばけばしい程の原色で溢れ、赤、青、黄といった色によって極めて明確な輪郭を持っている。まるで黒いキャンバスに絵具を塗りたくっていったような映像とでも言おうか。
エンドクレジットもこれまたどぎまぎするくらい真っ赤な赤色に、白字で出演者やスタッフの名前が書かれているのだが、それらは白字で書いたというよりも、もともと白かったところを原色の赤で塗りつぶしていって名前を浮かび上がらせたように見える。エンドロールをぼんやりと眺めながらそんなことを考えているうちに、これが正にこの映画なのではないかという考えが頭をよぎった。つまり背景というのは過去で、ガラス越しに見ているようなぼんやりとした過去に絵具を塗り、輪郭を作ってゆき、そうすることで今現在の自分がぱっと浮かび上がってくるような、そんな感覚だ。何年か経って彼らは再びかつて住んでいた部屋を訪れる。そこで彼らが目にする、相手が残していった痕跡を手掛かりに、彼らは宙にぽっかりと浮かんだそれぞれの過去の輪郭をなぞっていたんじゃあないだろうか。
(澤田陽子)
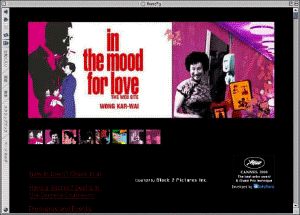 『花様年華』オフィシャル・サイト
(Lizhen's Room >>
closet 必見。)
『花様年華』オフィシャル・サイト
(Lizhen's Room >>
closet 必見。)
http://www.wkw-inthemoodforlove.com/jap/homepg/homepg.asp
4月4日(水)
『僕の小さな恋人たち』ジャン・ユスターシュ
冒頭に流れる古めかしいシャンソンを耳にした時は、これから見る映画は、多少なりとも思春期の甘いノスタルジーをくすぐるようなものかとも思ったが、映画が進むにつれ、『ママと娼婦』を撮った監督にはそんな感傷に浸る暇はやはりないのだ、と自分の早計を恥じた。『僕の小さな恋人たち』は子供から大人へと季節の移り変わり目だとか、思春期の痛々しい思い出だとか、大人達への反駁だとか、そういったものとは少し違う風景を捉える。『ママと娼婦』に写し出された生々しい70年代初頭のパリの風景やシネフィル的教養を身に纏ったジャン=ピエール・レオー扮するアレクサンドルとは違い、『僕の小さな恋人たち』の風景はある特定の時代と密接に結びつくわけでもないようだし、主人公の少年は確かに映画好きではあるようだが、そのことが何か主人公を取り巻く特殊な環境を主張するというわけでもないようだ。あるいは、その全編を会話する声が包み込んでいたような『ママと娼婦』と対照的に『僕の小さな恋人たち』は寡黙な映画である、とも言えるかもしれない。
だが、やはり『僕の小さな恋人たち』の少年は『ママと娼婦』のアレクサンドルと同様の困難を生きているとも言えるだろう。確かアレクサンドルは「他人の言葉で話すのが楽だ」みたいな事を言っていた。ラストシーン、そんな彼が始めて「自分の言葉」を発するかのごとく「結婚しよう」と叫ぶにもかかわらず、その「声」がフランソワーズ・ルブラン扮するヴェロニカに「言葉」として届かないように彼女は振る舞う。結局、他人の言葉を喋るとは「自分の言葉を発せない」ことを露呈させていくだけなのかもしれない。そして『僕の小さな恋人たち』の少年もやはり高校進学を諦めさせようとする母親に対して「言いたい事はあるが言えない」と心の中で呟くだけで、自分の言葉を発することの困難を背負っているようである。ただ、アレクサンドルのような饒舌になれない彼は、彼に言葉を発させないそんな世界にたいして、沈黙という形の抵抗を試みているかのようだ。
だから、このフィルムの中で彼があまたのキスを見つめるのは、そんな抵抗の学習なのだ。素敵なキスの数々がこのフィルムには鏤められているが、中でも忘れる事ができないのはやはり、少年がナンパした少女を年上の仲間に横取りされそうになった時、少女とひそひそと二人にしか聞こえない声で二言三言言葉をかわした後にする、あのキスだろう。フレームの中で二人きりになる少年と少女。「目をつぶると二人きりになれる」というクリシェなナレーションもこの時ばかりは感動的だ。だがこのナレーションの後すぐに「耳も塞げたらいいのに」と続く事に注意しなくてはならない。実際このシーンで聞こえる音は凄まじい。風と木々のざわめき、と書けば聞こえは良いが、というよりほとんど、風がマイクにあたる音、といった具合なのだ。それはちょうど、『ママと娼婦』のラストのフランソワーズ・ルブランのけたたましい笑い声のように、残酷なまでに容赦なく耳にやってくる「声」のようでもあった。少なくとも私の目には、少年は、キスという名の抵抗を実行しがら同時に、沈黙のさなかやって来る、この「声」を聴くことを学んでいるようにも見えた。こんな素晴らしいキスシーンは他に出会った事がない。
(新垣一平)
4月3日(火)
『見い出された時』ラウール・ルイス
自宅のベッドに横たわり、望遠鏡で窓の外を眺める、そのようにして執筆活動を行ったといわれるマルセル・プルーストにおいて「近くのもの」と「遠くのもの」との境界は混乱をきたす。
『失われた時を求めて』を読破したわけじゃないけど、やっぱりあの小説は遠近法が無茶苦茶に混乱してると思う。話者マルセルとその対象(人物、風景・・・)との関係は決して安定しないし、歪められ、断片化されることによって、対象だけでなく、それにとらわれながらもかろうじて語っているマルセル自身も危険に曝されている。人物、風景云々は観察者マルセルに読まれることを要請する、あるいは、読んでしまったマルセルによってしかそれらは現れてこない・・・、のか。
さて、パスカル・ボニゼ−ルは自著『歪形するフレーム』のなかでホルバインの『大使たち』に触れている。あの歪んだ髑髏、つまり「歪形されたイマージュ」は、充実したタブローを一枚の画布に貶めつつ、視点の変化による(正面
からのイマージュとは異質の)新たな時間と空間を見る者に要請する。いや、そうした時間と空間を生み出さざるを得ない「見る者」を要請する、のかもしれない。有機的な統一体としてのタブローは、(髑髏のような)歪形、断片等によって、見る者が読むべき装置となる。
『歪形するフレーム』でも取り上げられている『盗まれたタブローの仮説』、このとんでもないフィルムの冒頭に(だと思ったけど)こんなワンシーン・ワンショットがある。カメラが一枚のタブローに徐々に正面
から接近してゆく、そして、画布の上に描かれたものが把握できるほど十分に前進したとき、ふとカメラは直進を止め、左へ曲線を描くことになる。それでもとらえ続けられるタブローは、視点の変化によって当然「歪形されたイマージュ」となる。つまりここではカメラ自身が意識的に歪形をつくりだし、かつ同時にその罠(歪形)を暴き出し、そして新たな時間と空間をも発生させ獲得するわけだ。その時点で、とらえられる対象(タブロー)は歪みを元々有するものとして把握されるのかもしれない。
『見い出された時』でのラスト近くの演奏会、豪華なサロンで奏でられるピアノとヴァイオリンの演奏に、イスに座った社交界の人々はうっとりと酔いしれる。カメラは演奏者の側から彼らをとらえるのだが、ここで僕達は二重の罠に嵌められる。直線状に並んだ聴衆をカメラが順々に映し出す最中に、彼らの座る椅子一列そのものもまた、(レールに乗せられたように)動き出すのだ。同方向に等速度で両者が運動すれば問題はないのだが、当然そこにはズレが生じるわけだ。さらに、続くショットでは直線状の列を半円状にして両者を運動させる。こうなってくるととどちらが動いているのか、あるいは両方とも止まっているのか、どうにも判別
がつき難くなってくるし、実際にこうした仕掛けを見抜く以前には単に驚きと気持ち悪さがあるだけだった。
歪んだ髑髏という罠、それの要請する視線の移動によって、タブローが一枚の画布へと、描かれた対象が無意味なものへと貶められている『大使たち』、そこで時間と空間を獲得するのは見る者であろう。左へずれる視点によって同様に貶められる『盗まれたタブローの仮説』の対象(タブロー)、ここで時間と空間を獲得するのはカメラであり、その上で、対象もまた時間と空間を有することができるのだろう。カメラを向けることによって、カメラを向けてこそ、目の前の対象は「現実」となる・・・、のか。
しかし、『見い出された時』においては、カメラは罠を積極的に統御し暴き出すことなく、罠に(意識的にしろ)ただ巻き込まれているかのようだ。カメラがまず獲得し、そして対象に与えられるはずだった時間と空間は、またしてもそこから逃れていってしまう・・・。はて?では、スクリーンを見つめる僕達こそを、このフィルムは強く要請している、というのか・・・。
ん〜、うまく掴めないんだけど、ただ、こうした<見る・見られる>関係の不安定さ、そしてそこに侵入する不純な要素が『見い出された時』では強く現れている、それだけはいえるのかな。そういえば、同じようなだまし絵的な要素はデプレシャンの『魂を救え』でも見られたはずだけど。
ついでに、中断してた『失われた時を求めて』に再びとりかかる意欲が湧いてきました(ようなこないような)。
(松井宏)

 何故ロメールについてうだうだと書いたかといえば、ジャン・ユスターシュの『ぼくの小さな恋人たち』を見たからで、この映画を見てまず連想したのが『獅子座』だった。『ぼくの小さな恋人たち』では、サーカスの設営地に響く木槌の音や、ダニエルの無表情っぷりや、ラリナスという村で木々を揺らす風や、刻一刻と色を変えていく日の光や、そういったすべての構成要素が結果
的にあるひとつ物語を浮かび上がらせる。その物語はとても単純なものだろうし、もっといえば、ありふれた退屈なものかもしれない。しかしこの映画には、物語を異化したり複雑にしたりで忙しい映画群からは感じることの少ない魅力に溢れている。その魅力はもしかしたら「豊かさ」とでも呼べるのかもしれないが、もしそう呼ぶとしてもそれは物語が豊かなのではなく、監督のユスターシュが豊かなのでもなくて、カメラの前の空間が豊かだったのだ。その豊かさをきちんと提示すること。それがユスターシュの意図であり、私たちが「物語」と呼ぶものの力だ。
何故ロメールについてうだうだと書いたかといえば、ジャン・ユスターシュの『ぼくの小さな恋人たち』を見たからで、この映画を見てまず連想したのが『獅子座』だった。『ぼくの小さな恋人たち』では、サーカスの設営地に響く木槌の音や、ダニエルの無表情っぷりや、ラリナスという村で木々を揺らす風や、刻一刻と色を変えていく日の光や、そういったすべての構成要素が結果
的にあるひとつ物語を浮かび上がらせる。その物語はとても単純なものだろうし、もっといえば、ありふれた退屈なものかもしれない。しかしこの映画には、物語を異化したり複雑にしたりで忙しい映画群からは感じることの少ない魅力に溢れている。その魅力はもしかしたら「豊かさ」とでも呼べるのかもしれないが、もしそう呼ぶとしてもそれは物語が豊かなのではなく、監督のユスターシュが豊かなのでもなくて、カメラの前の空間が豊かだったのだ。その豊かさをきちんと提示すること。それがユスターシュの意図であり、私たちが「物語」と呼ぶものの力だ。