
『港』発売記念 湯浅湾3時間ライヴ (@六本木スーパーデラックス)
4月も中盤に差し掛かってなんだか生暖かい日々が続き、神田川などに目を向ければ桜の花びらが川面を覆っている。暖かさに誘われるように夜の街に出かけてみると、人々が地面の下に向かって列をなして潜っていくところに出くわした。六本木の土の中ではこの夜、果てしない営みが行われていた。
湯浅湾。6年ぶりの3rdアルバム
『港』の発売を記念して彼らが敢行した3時間ライヴの模様をお伝えしたい。


ザ・バンドからグレイトフル・デッド、はっぴいえんどから裸のラリーズ、そしてブラック・ミュージックから歌謡曲まで、大衆音楽の歴史をたっぷりと飲み込んで、溢れ出ては渦を巻く音の泉。
牛も豚も猿もミミズも、みんな喜ぶ
湯浅湾、6年ぶりのサード・アルバム
湯浅湾『湾』
発売日:2009年4月17日
定価:2,310円(税込)
制作・発売:boid
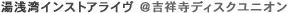
4/19(日)20:00より(入場無料)
詳細はこちらからどうぞ boid.net : http://www.boid-s.com
取材・構成:結城秀勇、田中竜輔、宮一紀
撮影:鈴木淳哉