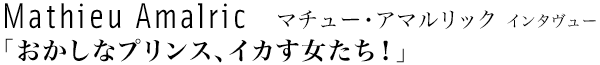マチュー・アマルリックの最新作『さすらいの女神たち』がついに公開される。2010年のカンヌ国際映画祭でコンペティション部門に選ばれ、最優秀監督賞を受賞し、フランス国内でもスマッシュヒットを飛ばした作品だ。ハリウッド映画にも出演するなど、すでに俳優として確固たるキャリアを築いているマチュー・アマルリックだが、本作は決して「俳優の片手間」作品ではない。彼はその監督デビュー作『スープをお飲み』(97)から、フランスのもっとも重要な映画作家のひとりでありつづけている。
これまでは家族(『スープをお飲み』)、夫婦(『公共問題』)、あるいは女性という個(『ウィンブルドン・スタジアム』)など、どちらかと言えば小さく親密な世界を描いてきた監督マチュー・アマルリック。『さすらいの女神たち』ではその親密さに加え、より大きな笑いと哀しみと喜びと、そして勇気に満ちた豊かな世界を描き出す。しかも監督作としては初めて本人が主演も務めている。2011年イチ押しの作品を、見逃すなかれ。
――今作はいわば「舞台もの」です。「舞台もの」の作品は――まさしく横長の舞台を映すために――シネマスコープで撮られることが多いと思うのですが、『さすらいの女神たち』は違います。なぜシネマスコープを選択しなかったのでしょう?
マチュー・アマルリック(以下M.A.) たしかに。実は最初ヴィスタとシネマスコープの両方でテストしてみた。でもスコープだとダンサーたちの身体をあるがままにとらえられないと気付いた。上下が足りなくて、彼女たちの身体のケタ違いのシルエットが薄められてしまうんだ。風景に関わる作品を作るのが目的ではなかったし、そう、そもそもここには「フランス的な」ものがいっさいない……。それに審美的なものには絶対したくなかったし、もちろん逆にうらぶれたものにもしたくなかった。あからさまではないかたちで、この作品に美しさが宿ってほしかった。画に関しては、とりあえず手持ちが多くなるとわかっていたが、いかにもな「手持ち」感や手探り感は禁物だ。すべてのショットはあらかじめ構想されていた。
それからスコープだと、どうしても照明を多く焚かないといけない。望むと望まないにかかわらず、照明を当てるべき空間が増えてしまう。そうこうして僕は、もしスタンダードでいけるなら絶対にスタンダードで撮りたいと思うようになった。スタンダードなら足元も入れられる。スタンダードというのは身体を必要とするんだ。
スタンダードはとても美しいフォーマットだ。もちろん、もはや消えつつあるフォーマットでもある。僕らはいま「横長」の様式の中にいるんだ。とはいえ「横長」だってひとつの様式にすぎないわけで、かつてズームがそうだったようにやがて消え行くと思う。いまだったら3Dかな。これも消えるだろうし……。まあとにかく、結局はスタンダードでの撮影が不可能となったので、ヴィスタサイズになったわけだ。
――全編にわたってつねにフレームが何かで埋め尽くされている印象を受けました。けっして窮屈な感じではないのですが、画面の中ではたびたび、同時に複数の出来事が起こっています。

M.A.そうかもしれない。僕はどうも自分に自信がないというか、観客が退屈するのが怖くて、いつもいろんなものをショットに入れ込んでしまう。たったひとつの何かだけをシンプルに撮るという段階には、自分はまだ達していないんだね。
一方で僕には、つねにガラスを撮りたい欲望がある。ただし、たとえばその後ろで何かを書いている最中の人物と一緒にね。あるいは可能なら、そのさらに後ろで何かが起こっていればなお良い。窓の向こうや、窓の前で何かが起きていてほしい。それこそ実人生における謎だろう。僕らの思考はたったひとつではない。同時に5つの思考を持っている。たとえばいま君たちはそこにいて僕の話を聞いているけど、同時に別の何かも考えているだろう。脳みそってとんでもないよ! それこそ「そこにいること=存在すること」のとんでもなさじゃないかな。『さすらいの女神たち』のニューバーレスクのダンサーたちは自分たちが生きてきた経験や年月とともに、そこにいるんだ。彼女たちはどうやって「そこにいる」べきかどうかを、学んできた。だから本当の存在感を持っている。だが一方で僕が演じたプロデューサーのジョアキムは「そこにいない」。彼は自分がどこにいるのかさえ、わかっていないからね。
――実際、ジョアキムは手品のように突如画面から消えてしまう瞬間がある。
M.A.舞台の大道具を持ったスタッフが前を通り過ぎる。すると彼は消えている……。そういうアイデアはふと生まれるものだ。後になって、こうやって作品について話す段になって「なぜ?」を考える。作っている最中に必要なのは、かならずしも疑問ではないんだ。
とはいえ今回は自分たちにひとつテーマが生まれると、あるとき確信した。シナリオ執筆中のときだったか、彼女たちダンサーに初めて実際会ったときだったか……。僕らはよくジョアキムのことを「永久の観客」と呼んでいた。つまり彼は、彼女たちがやっていることを自分ではできない人間だ。そこから、まさに中心に関わる問題、つまり「そこにいること」の問いが生まれたんだと思う。その意味でこれはコメディに等しい。同時に複数の物事を起こさせること。ふたつの要素が摩擦を起こすとき、そこにはアイロニーが生まれる。たとえば言語。彼は英語で話し、彼女はフランス語で答える。果たして彼女は本当に彼が言ったことを理解しているのか? あるいは彼がダンサーたちを罵っている最中に、その後ろでは男たちがバトミントンをしていて……。物事というのはつねにそうやって重なり合っているんじゃないかな。僕はそこにすごく惹かれる。
――今作では登場人物を「背中から」撮るショットが多いような気がしましたが……。
M.A.とはいえ、たとえば『ウィンブルドン・スタジアム』(01)よりは少ないと思うし、とくに今回は背中というものを考えていたわけじゃなかった……。ただ僕はつねに自分にこんな問いを投げかけていた。舞台上のショウが作品全体の中でカッコに括られるのではなく、それがつねに登場人物の誰かによって感じられているようにするには、どうすればいいかと。そこで必然的に、たとえばミミが舞台上でショウをやるときはジョアキムを舞台袖に置いて、ショウが「脇から」見られるようにした。だから僕なら「背中から」というより「脇から」と言いたいね。
とにかく「背中から」のショットはそれほど多くないんじゃないかな……。いま思い出したが、ラスト、ジョアキムと一夜を過ごしたミミが部屋を出て廊下を歩くところでは――幽霊ホテルのところだね――たしかに、彼女を背中からとらえつづけているね。まあ、あそこでは彼女がどんな場所にいるかを観客にわからせたくてそうしたんだが……。だがそれにつづくショットは、彼女を正面からとらえたものだ。あれは彼女をとらえたショットの中で、僕がもっとも気に入っているものだ。あの瞬間の彼女は本当に美しくて……。まったく、あの瞬間の彼女のみずみずしさと言ったら!
それから今回は自分が撮る人々に対して、よりシンプルな関係でいたというか、適切な場所で適切に存在していたように思う。もちろん、ときにはアクションからそれが要求されることもある。ジョアキムが舞台上のミミを見るのであれば、やはり「脇から」彼女を見えるようにした。ただそうじゃなくても、僕が適切な場所に適切に存在することで、彼らがみなキャメラの存在を忘れてくれるようになってほしかった。それは『ウィンブルドン・スタジアム』とは真逆だ。あの作品には形式の快楽があった。原作の小説がすでにそうだったように、あそこで重要なのは地理的なこと、つまり場所そのものだった。だから、ちょっと冷たく見えるような引きのショットで、そこにジャンヌを置く必要があった。今回は撮影監督が『ウィンブルドン・スタジアム』と同じクリストフ・ボーカルヌだったから、最初はその手の引きのショットをいくつか撮ってみたが、すぐに気づいたよ。この物語に必要なのは、それと真逆の形式だってことが。
――この作品は集団を扱ってはいますが、中盤でジョアキムがパリに行くところから突然、彼の視点と同様にミミの視点がぐっと前面に出てきますね。
 M.A.ジョアキムはそれまでずっと、グループの中にはいるが、しかし彼女たちを個別に観察してきたわけじゃない。彼の心配とは、あのダンサーが、このダンサーが、ちゃんとオッパイを見せるかどうか、という類いのもの。要は演出部や制作部としての心配だ。僕自身も映画の演出部や制作部をたくさん経験してきた。そこでつねに考えなきゃいけないのは、荷物や移動、食事、ホテルといった問題であって、誰かひとりに特別に注意を払っているわけじゃない。
M.A.ジョアキムはそれまでずっと、グループの中にはいるが、しかし彼女たちを個別に観察してきたわけじゃない。彼の心配とは、あのダンサーが、このダンサーが、ちゃんとオッパイを見せるかどうか、という類いのもの。要は演出部や制作部としての心配だ。僕自身も映画の演出部や制作部をたくさん経験してきた。そこでつねに考えなきゃいけないのは、荷物や移動、食事、ホテルといった問題であって、誰かひとりに特別に注意を払っているわけじゃない。
だがジョアキムは突如、自分の過去に急降下する。それは帰還だ。つまりパリへの悪夢のような帰還であり、そこで彼の過去の罪が水面に浮上してくる。彼自身はプリンスのように帰還できると考えていたが、実際は悲惨なものだ。
ミミとの交替モンタージュを思いついたのは、まさに編集作業中だった。もともとシナリオに書かれていたのはこうだった……。夜、彼は息子たちと一緒にパリから高速道路で戻って来る。息子たちは車の中で眠っている。彼は車を止め、ハザードランプを点ける。手にはチョコパンだ。すると迷いなく高速道路を歩いて横切り、ガソリンスタンドの女性――パリに行く途中に同じ高速道路で出会った女性だ――のところへ向かう……。でもその一連の彼の姿は画面奥ではぼけていて、画面手前のハザードランプだけがはっきりと見えるようになっている。チックタックと光が点滅して、あたかもメトロノームのようになるんだ。そしてジョアキムの手が映り、彼は姿を消す。いったい何が起こったのか観客にはわからない。すると突然、ミミの視点へと移行する。他のダンサーではなくミミだったのは、ほとんど偶然だが、とにかくその後の時間はミミのものとなる。そこで僕らは彼女の孤独の中に入っていて、だからキャメラは彼女と一緒に舞台にも上がる。なぜなら彼女の頭の中にいるのだから。ジョアキムがミミに再会するのもまさに舞台の上だ。その後彼女は、部屋にいる彼を鍵穴越しに見て、そこで彼に息子たちがいることを知る……。そうやってシナリオを書いた。
――ではなぜそれを編集で変更したのでしょう?
M.A.編集中に気付いたんだ。もっとおもしろくできるんじゃないかと。つまり観客が無意識のうちに登場人物たちをちょっとだけ先取りすれば、もっと良くなるんじゃないかと。ジョアキムとミミは互いに惹かれ合っているけど、そのことに本人たちはまだ気付いていない。でも観客にはそれに気付いてもらいたいと思った。そのためにはミミとジョアキムのあいだに何かを作りださなきゃいけない。そのために交替モンタージュが必要だった。彼らはまるでアメリカ映画のコメディみたいにケンカばかりしている。それを見ている僕らが望むのはたったひとつのこと。そう、彼らがキスをすることさ!(以下本誌につづく!)
※インタヴュー全文は10月中旬発売予定「nobody 36号」で読めます。
マチュー・アマルリック Mathieu Amalric
1965年生まれ。父はル・モンド紙の名物記者、母は文芸評論家。84年、オタール・イオセリアーニ監督『Les favoris de la lune』に出演して映画デビュー。その後、映画スタッフとして働きながら自ら短編を撮りはじめるが、アルノー・デプレシャン監督『魂を救え!』(92)に出演して以降は、俳優として広く知られるようになり、『そして僕は恋をする』(96)ではセザール賞有望若手男優賞、『キングス&クイーン』(04)ではセザール賞主演男優賞を受賞。近年はハリウッド映画にも進出し、スティーヴン・スピルバーグ監督『ミュンヘン』(07)、マーク・フォースター監督『007 慰めの報酬』(08)に出演。
また俳優業と並行して監督業も継続しており、『スープをお飲み』(97)を皮切りに、『ウィンブルドン・スタジアム』(01)、『公共問題』(03/カンヌ国際映画祭監督週間上映)を制作。そして長編第4作目となる今作はカンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出された。
取材・構成:エレオノール・マムディアン、松井宏
写真:鈴木淳哉