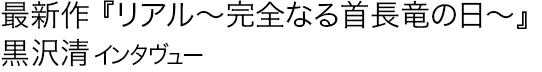――黒沢監督の最新作『リアル~完全なる首長竜の日~』(以下、『リアル』)には、乾緑郎さんの原作『完全なる首長竜の日』から持ち込まれた、「センシング」と呼ばれる技術によって他者の心の中に人が入り込むという設定があります。「映画では人の心の中を撮ることはできない」という監督ご自身の言葉を何度も耳にしてきた者にとって、今作はほとんど前言撤回のような驚くべき試みであるように思われました。
黒沢ご存知のように『トウキョウソナタ』(08)以来、いくつか企画を進めてはいたんですが劇場用映画はひとつも実現していない。そんな中で、東宝で公開される大きな企画としてこの原作を頂き、これをやらずしてどうするとは思いました。が、これは厄介だなと。人の心の中を撮ったという映画はなかなかうまくいかないなあと。僕も同じ目にあってしまうかもと危惧しながら、しかし心の中を撮るにはこう撮ればいいというものを自分で編み出してみようと、こんな無茶なことに挑んでしまったわけです。

――原作のタイトルにつけ加えられた「リアル」という言葉の選択は黒沢監督によるものですか?
黒沢これは「原作を知らない人にとってわかりやすいタイトルを」ということでプロデューサーから提示されました。でも僕は当初ものすごく抵抗を感じたんです。内容からすれば「アンリアル」でしょうと。でも今や、本心を言えば『リアル』でよかったと思っているんです。
映画で人の心の中を描けないのは当たり前で、意識下と現実とをどう描き分けるんだとか、実際様々な難問が待ち構えている。でもこれ映画ですよね、って。リアルかアンリアルかじゃなくて、映画ですよねって。映画っていうメディアではどう転んでも、ある場所で、ある俳優が演技か何かをやっていて、そこへカメラを向けるわけで、そのことには心の中であれ、意識下であれ、現実であれ、たぶん違いはない。どれが意識下でどれが現実なのか、どれがリアルでどれがアンリアルなのかということは、本当に物語上の話でしかない。物語の上では、シーンによって「これはリアルで、これはアンリアルだ」と区別できるのですが、映画であるシーンが終わると、直結で「次のシーン」がくる、これを何十回か続けて映画は終わる、その原則は不変なわけで、ここに映画の真のリアルがあるということだったんです。わかりますかね?(笑)。
――『リアル』は、都市の風景を捉えたタイトルバックに引き続いて、この映画の中心的な舞台となる佐藤さんと綾瀬さんが住まう部屋を映し出します。この場所を捉えた最初のワンショットは、演劇の舞台のようなつくりものめいた質感とともに、光のきらめき具合も重なってかなり異様なものとして目に入りました。
黒沢この部屋はセットですから、異様に見せようと思えばいくらでもそう見せられる。現実の場面では文字通りリアルな、生々しい普通の部屋を出すことも考えました。現実と意識下においてその部屋をどれくらい違ったものにするかと考えて、結果、ちょっと違うけどけっこう似ている、ということにしました。衣装の使い分けを含めて悩ましい問題でしたね。たしかに意識下の部屋だけが舞台っぽくなっていれば区別はつきやすいんですが、直感的にあんまり面白くない気がして微妙なところを狙ったんです。露骨に嘘っぽくはないと思うんですが、『トウキョウソナタ』(08)の住宅に比べればちょっとアンリアル感が漂う。このトーンでどうにか最後までいけないだろうかということが狙いになりました。
――今作でも重要な役柄として出演されていますが、『LOFT ロフト』(05)での中谷美紀さん以来、小泉今日子さんをはじめとして、黒沢監督の映画における女性の役割というものはどんどん大きなものになっています。『リアル』における後半部での綾瀬はるかさんは、これまでの黒沢監督の映画には現れなかったタイプの女性像だと思いました。
黒沢ええ、それはそうですね。前半は佐藤健さんが主体ですが、後半のあるときに主役が綾瀬さんに入れ替わると、そのままラストになだれ込む。前半は非常に謎めいているんですが、そこからはほとんど無理矢理にでも綾瀬はるかさんが主体なのだと力づくで持っていきたかった。ゆっくりしている暇はない、行動あるのみ、躊躇しない、ずんずん行動して理屈抜きに、彼女が目の前のものを乗り越えられるのかどうか、といういわばアクション映画の原理を全開にすることにしたんです。綾瀬さんは本当に運動神経のいい方で、それに見事に答えてくれました。
――『リアル』では、たとえば幽霊へのズームアップで画面の粒子が見えるシーンのような、極端な効果というものがこれまでの黒沢監督の作品に比べても積極的に取り入れられているように思えました。

©2013『リアル~完全なる首長竜の日~』製作委員会
黒沢撮影の芦澤明子さんも僕もへそ曲がりで…。どういうことかと言うと、今回、実は初めて全部デジタルだったんですよ。フィルムは一回も挟まってない。撮るのもデジタル、完成したのもデジタル。いまどきデジタルでもまるでフィルムみたいに見せかけることはできる、でもだったらフィルムでいい、だからフィルムでは絶対やらないようなことやりませんか、というのが芦澤さんとの取り決めでした。ですから、編集のときの効果も含めて、これまで僕はほとんどやらなかったオーヴァーラップや急激なズームアップみたいなものーー実際には後でつけたデジタル的な効果ですがーー、自分に禁じていた方法をおそるおそる思い切ってやりました。俺が悪いんじゃない、デジタル化した世間が悪いんだという理屈でね。
――終盤ではそのような姿勢が最大限に高められることで、あの巨大な首長竜が出現するわけですね。
黒沢原作はどれが現実か結局は判らないという文学の香高い終わり方でしたが、映画にした場合、しかも娯楽映画にした場合、たぶんその終わり方は違うと思った。この映画では主人公たちが最大の難関を乗り越える、戦う、ハードルを越える、つまりアクションこそを映画の最後の見せ場にしたいと強く思いました。そうすると必然的に最後の難関は首長竜しかないでしょうと。
「ジュラシック・パーク」シリーズにはどれにも首長竜は出てこないのですが、このシリーズは少し前の作品だということもあって、ひとつわかりやすい理由が想像できます。何かと言うと水の表現なんですね。CGでは水の表現は本当に難しい。本物の水を使うなら『ジョーズ』(75)みたいに人形を使えばいいんですけど、当時、CGの恐竜が自ら水の中から現れる映像というのは本当に厳しかったんだろうと思います。おそらくスピルバーグであっても今首長竜をやれと言われたら、途中までは水の中での映像をつくるかもしれませんが、そこからは陸に上げると思いますね。ですが、『リアル』ではおそらく世界最高水準の水の表現ができていると思います。
首長竜は突如自ら陸に上がって地上をガサガサ這ってくるわけですが……どんなふうにして這うんだろうかと、これも試行錯誤の連続でした。「こういう這い方がリアルなんじゃない?」と言っても、何の根拠もない。たとえばセイウチの這い方をモデルにしようというアイディアもありました。僕も最初はセイウチ説だったんですが……ところがですよ、実際にやるとセイウチにしか見えない(笑)。違うと言っても誰も見たことがないし、参考になるものもない。それで最後に決まったのがあれなんです。今後またもっとすごいものが出てくるかもしれませんが、僕としてはよくあんな無茶苦茶であり得ないものが、実にリアルに見えるようになったなと今は思っています。
(本インタヴューの全文は6月発売予定「nobody issue 39」掲載予定です)
聞き手・構成:田中竜輔、増田景子
写真:鈴木淳哉(ポートレート)