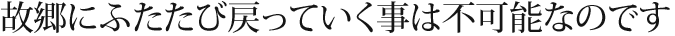――イオセリアーニ監督はよく「映画はセリフではなく、リズムが重要だ」と仰っています。映画におけるリズムとはどのようにして生まれるとお考えなのでしょうか?
オタール・イオセリアーニ(以下、OI)映画は時間の中に流れる芸術です。その点でダンスや音楽に似ています。そして不可逆的にダンスと音楽にはリズムとテンポがあります。リズムという概念は存在するあらゆる職業にとって重要なものです。手首を指で触れると人間の脈拍を感じる事が出来ますが、その人間の脈が人生のリズムを作り出しています。ナポレオンの脈拍は43でした。我々アーティストは最小で70です。したがってアーティスト達は非常に速いリズムでスピーディーに生きているのです。人生のリズムはこのようにして定まっていきます。ナポレオンは若死にしましたが、1分間に43の脈拍ですから、本当であれば120歳まで長生き出来たはずです。昭和天皇・裕仁の脈拍は50だったので、かなり長命でありました。もちろん測った事はありませんが、あのブッダの脈拍は20かそれ以下ではなかったかと思います。
現代の若者はビデオクリップやPVを見る事が大好きです。そこではリズムがあまりにも速いので、我々の世代はついていけません。ギリシャの大詩人ホメーロスはとても長い詩を書いていて、ロシアの女詩人アンナ・アフマートワは彼の詩について「なんと愛すべき長さ」と言いました。長い詩を読む者にとっては、それだけリラックスをしてじっくりと考える時間があります。
たとえば2時間の映画作品があったとして、早回しにして1時間に縮めるとします。そうすると何もかもが失われてしまうと思うのです。一度ベルリンで私の作品が上映された事がありますが、その際、1秒間に25コマの映写機が使われていました。それを知らなかった私は上映中に散歩に出かけていました。ちょうど終わる頃に戻ってきて、観客との質疑応答に当たろうとしたら、映画の上映はとっくに終わっていました。24コマの作品を25コマで回したので、映画は短くなってしまって、6分早く終わっていたのです。その際に私は「リズムとは一体何なのか」を理解しました。映写のスピードはアメリカのヘルツで決まっています。映写機は48ヘルツです。従ってそのスピードは1秒に24コマという事になります。ところがヨーロッパで一般に流通しているのは50ヘルツです。そうすると1秒に25コマになります。そこで私は、映画を1秒間に25コマで撮る事を決めました。そうするとこの「1秒間に24コマ」というアメリカのシステムによって押し付けられていたものよりも長くなるのです。
しかしこれは困った事態です。私はもはやどのようなスピードで映画を撮ればいいのか全くわかりません。それに変わるのは映画の長さだけではなく、音のトーンも一段上に変わってしまうのです。「ラ」の音で言えば、「ラ」だった音が「ラ」のシャープになってしまう。セリフだけではなく、音楽もノイズも全てのトーンが一段上がるのです。
ーーこの映画はゲオルギアとフランスで撮影されています。撮影にあたって何か言葉の問題はありましたか?あなたにとって言葉とはどういったものなのでしょうか?
OI私は残念ながら日本語を話せません。けれども1ヶ月間日本に滞在したとしたら、少なくとも話し言葉は出来るようになるのではないかと思います。私は漢字が少し書けます。中国語が素晴らしいのは、漢字文化でありますから、北京語や広東語で発音が違っていても、書き言葉でお互いに理解出来るという点だと思います。発音が違っていてもわかることは、映画も同じではないかと思うのです。映画もある種の漢字のようなものではないでしょうか。なので、私は映画で話されているセリフの内容には何の価値も与えていません。全ての観客がそこで話されている言語がわからなくても、全ての内容が理解出来るようでなくてはならないと思うのです。映像と音で出来ている映画の全てが、言葉を経ないで理解出来るものでなければならないと考えています。登場人物が話をしているのを見て、彼らが何を話しているのか、喧嘩をしているのか、仲が良いのか、観客は言葉がわからなくても理解出来る。それで私は言葉の内容そのものには全く意味を与えていないのです。
私はフランス語を子供時代に習いました。今は至る所で子供が英語を習うようになっています。けれども昔は皆フランス語を話していました。外交官達もフランス語を話していました。しかしアメリカ経済が世界に進出したために、世界中が下手な英語を話すようになっています。彼らはジェイムズ・ジョイスを英語の原典で読む事も出来なければ、シェイクスピアも読む事が出来ません。「こんにちは」「さようなら」「いくらですか?」、とりわけ「How much?」という言葉は世界中がよく学んでいる英語ですね。これらは言語とは言えません。言語には深さがあるので、これらは言語とは言えません。それはとても悲しい事だと思います。私自身は芥川龍之介の小説を日本語で音読をした時に、どのような響きをするのかわかりません。日本の短歌や俳句がどのような響きをするのか知りません。しかしこれらは書かれたものですから読む事が出来ます。なぜならそこには映像があるからです。だからこそ私は映像を使っている、映画の仕事をしているのです。そこに映像、イメージがあるからです。私はイタリア語、ドイツ語、フランス語、ゲオルギア語、ロシア語、ウクライナ語など、1000もの言葉が話せます。しかしそれら話し言葉には映像、イメージが存在していません。つまりこれらの言葉を読めなければいけないし、読んだ際にそれぞれの言葉の後ろにある内容をよくわかっていないといけないのです。
昨日のインタヴューの際に、ダンテの『神曲』の冒頭部分を引用しました。(イタリア語で)「星を見るために外に出た」。これは翻訳する事は出来ません。これは詩の問題です。詩は翻訳する事が出来ないのです。従って詩にも限界があります。同時に外国語が話せると素晴らしい翻訳という職業が出来ます。文学の翻訳というのはひとつの才能であって、それはテクストを別の言語に忠実に移し替えるという事です。私がとても誇りに思うのはロシアの翻訳家達であって、日本文学を美しいロシア語で訳しています。お陰で日本文学の事を私はよく知る事が出来ました。また、ロシアの翻訳家達はホメーロスの『イーリアス』と『オデュッセイア』をロシア語の韻文に訳しています。韻を踏んだロシアの韻文でもって訳しているのです。ホメーロスをロシア語に訳したのはプーシキンの友人達でした。古代ギリシャの世界を忠実に、しかも美しい韻文のロシア語で訳しています。

© 2010 Pierre Grise Productions
――現在のゲオルギア映画を取り巻く環境はどうようなものなのでしょうか?また監督はそれについてどのように考えているのですか?
OI日本と同じくらい悪い状況ですね。映画ではかつて作家主義という概念が発明されました。単に映画だけが存在していたのに、今では映画をふたつに分けるようになっています。一方にはリュック・ベッソンが作るような「本当の映画」が存在する。その他の映画は全て「作家の映画」という風にまとめられているのです。溝口健二の時代には単に映画だけがありました。オーソン・ウェルズの時代にもやはり映画だけがあった。バスター・キートンの時代も映画だけでした。最近は全ての人々のために映画が作られています。すなわち、あまりにもわかりやすい映画が作られるようになったのです。誰にでもわかる映画ですから、そういう映画は2回目に見た時、真ん中まで見てやっと「もう見た映画だ」とわかります。たとえばヴィットリオ・デ・シーカの『ミラノの奇蹟』(51)を見た時、私は1回しか見ていないのに、今日に至るまで映画の頭から最後まで話をする事が出来ます。それはただ単にそれが映画だったからです。黒澤明の『赤ひげ』(65)にしても同じです。それは映画だったから私のヴィジョンの中に留まっているのです。私はジェームズ・ボンドが大好きです。ジェームズ・ボンドを見るととてもリラックス出来ますし、寝る前に見るのに最高です。しかし3回目にジェームズ・ボンドの同じ作品を半分まで見た時にやっと「もう見た映画だ」とわかります。このように、見た後に消えていってしまう映画もあるのです。
ゲオルギアの映画の状況という話ですが、ゲオルギー・シェンゲラーヤが映画協会の会長をしています。シェンゲラーヤが現在のゲオルギア映画のトップの座にいるという事です。彼は『ピロスマニ』(69)という愛すべき作品を作っています。あまり知られていないのですが、彼が作った作品の中でとても素晴らしい作品があります。『若き作曲家の旅』(76)という作品で、ゲオルギアで内戦が起きていた時、若い作曲家が民謡の採取のために国を旅するという話です。周りでは恐ろしい事が起きているのに、彼は消え去ろうとしているゲオルギアの民謡を録音し、譜面に書き起こして記録に留めようとします。世界の崩壊の中で、すなわちロシア革命が起こって内戦が始まり、さまざまな兵隊が押し掛けてきている状況の中でです。それはかつての日本の帝国主義が大陸で行っていたような状況だと思います。彼は歌の事しか考えていない。歌だけが後に残るもので、他のものは全て消えていくとわかっている。そういう素晴らしい映画を作ったのがゲオルギー・シェンゲラーヤでした。シェンゲラーヤの映画『ピロスマニ』のタイトルも、この「Chantrapas」(=やくたたず)にしても良かったと思います。
――あなたは1979年にフランスに移住しました。フランスにいる間に、故郷であるゲオルギアに戻りたいと思った事はありますか?今後もフランスを拠点に映画を作り続けていくのでしょうか?
OI自分の生まれ故郷に帰る事は外国に行くよりも、もっとひどい事です。全てが変わっているからです。人々がまったく変わってしまっていて、特に高齢者がいません。つまり私達が最も歳を取っていて、何かを思い出す人間は私達だけになってしまっています。私は自分の子供やひ孫たちに、「何かを思い出すように、何かを憶えているように」と育ててきたつもりです。つまり私達の世代は次の世代との橋渡しをする、橋になる存在だと思っています。ところがゲオルギアでは全てが忘れ去られてしまっています。田舎者の成りあがり達が国全体を支配し、占領するようになってしまっています。顔立ちは私達のように古い世代の顔をしているのに、内容や行動は野蛮人になってしまっている。これはとても悲劇的な事で、ボリス・パステルナークの小説『ドクトル・ジバゴ』の最後にそれがはっきりと書かれています。ドクトル・ジバゴとラーラの子供だと思われる女の子が出てきて、その女の子の顔立ちはふたりの生き写しのようです。ところが彼女はあまりにも野蛮になってしまっていて、彼らがどこから来た人なのかはわからなくなっています。このように顔はそっくりなのに、全く内容が変わってしまっている。それが今のゲオルギアだと思います。
特にフランスに関してもそれは同じではないでしょうか。ロートレックの時代のフランスはもう終わりです。「ラ・グリュ」の世界は終わったのです。昔はフレンチカンカンでは長い膝丈のレースでいっぱいのパンツを履いていたのに、今もしもフレンチカンカンを躍らせるとしたら、下着は真っ赤で短いパンツになるでしょう。落書きしたり絵を描いたりしていたカフェの壁は、今はビニールで覆われて誰も触れない状態になっています。そのカフェにはもはやピカソやランボー、ヴェルレーヌ、ボードレール達は訪れません。皆が下を向いて自分のスープを飲んでいるだけです。ですから私はフランスに帰る事も出来ない。フランスに来た頃、私は少しばかりベル・エポックの名残にありつけるかと思っていましたが、その頃にはもうベル・エポックは終わってしまっていました。着いた時が遅すぎたのです。いずれにせよ、「川の流れはいつも同じではないから、同じ川に二度入る事はあり得ない」という格言があるように、自分の生まれ故郷を再び見出そうとしても、そこに戻っていく事は不可能なのです。山並みは同じですし、まだ寺院も残っています。しかし地上で這いまわっている全てのものが不愉快な存在になっています。おそらくそれが「時間が流れる、時が過ぎる」という事なのでしょう。

© 2010 Pierre Grise Productions
――最後に、日本でこの映画が上映されるにあたって何か一言いただけますか?
OI勇気は必要です。こうやって震える大地の上で生きる勇気は皆さんに必要な事でしょう。私達を脅かす事をするこの土地です。それに対して私達は何も出来ません。自然は自分自身の仕事をする。それに対して私達は蟻のようなものです。私達を何がどこでどのようにして待ち受けているのか、我々にはわからない。だから私達に出来る事は、自然が少し落ち着いている間のこの空気を利用する事でしょう。至るところにカタストロフィーが待ち受けています。前世期の最も大きなカタストロフィーはナチズムとボルシェヴィキの成す仕業でした。ナチズムとボルシェヴィキは津波よりも悪い事なのです。
いずれにせよ、若い時は状態がより良く進む事を望むものです。結局いつもと同じように、なんとかなるでしょう。
取材・構成 高木佑介
写真:鈴木淳哉