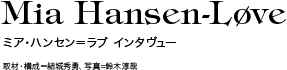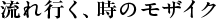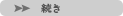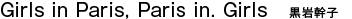恵比寿ガーデンシネマにて絶賛公開中の『あの夏の子供たち』。フランス映画祭にて来日していたミア・ハンセン=ラブ監督にインタヴューを行った。
彼女の長編処女作である前作『すべてが許される』は、みずみずしさとともに古典的な風格さえも備えた作品であり、新たな若い才能が登場したことを高らかに宣言するものであった。『あの夏の子供たち』は、その処女作のプロデューサーを務めるはずだったアンベール・バルサンというひとりの男をモデルにしている。だが、ハンセン=ラブと彼の共同作業は、彼が自ら命を絶ったため実現しなかった。
『あの夏の子供たち』における、父親の死と少女たちの成長といった題材は、前作から共通して彼女が描き続けているものだ。散在する細やかな断片をつなぎ止めるようにしてひとつの世界を構成していた男が、その作り上げた世界から姿を消してしまうとき、残された者たちはそれをどう受け止めることができるのか。安易な解決など見いだせないテーマだ。
しかし、揺るがしがたい現実の重苦しさだけでなく、どこか清々しい思いすら彼女の映画に見いだしてしまうのは、一回限りの喪失でさえもが、それを包む大きな流れの一環であるかのような気がしてしまうからだ。季節が繰り返すように、淡々と時間は流れていく。あるいは歌い継がれてきた古い歌が、もう一度歌われることで新たな生命を持つように。


パリの街並みを切り取ったファーストカット(たしかY字路だ)からすっと画面に引き込まれた。一度もパリの街に降り立ったことがないのに、その風景にどこか懐かしさを感じる。もしかしたら映画の前に「フィルム・デュ・ロサンジュ」のクレジットを目にしたせいで、その会社をつくったエリック・ロメールの映画をその風景に重ね合わせたのだろうか? 一瞬、そのように自問したのだが、否、ミア・ハンセン=ラブと撮影のパスカル・オフレーによって映し出されるパリの街は、ロメールの映画のそれとは違う色合いを見せている。私が懐かしさを感じたのは、ここで切り取られている街に対してではなく、その画面の色合い、その街並みを映し出す日差しに対してだろうか。この映画には夏の夕方を思い起こさせる、濃いけれどやわらかい光が宿っている。そんな光がどうやってもたらされているのか(自然にそう映っているのか、カメラの露出をいじっているのか)はわからないが、その光にとってもたらされる明暗や色合いはこの映画、この物語にとって欠かせないものとしてある。
この映画は、映画プロデューサーの父親、イタリア人の母親、そして3人の娘たちで構成されるひとつの家族の物語だ。映画の前半、カメラは主に父親に寄り添い、彼が自殺して姿を消してしまう中盤以降は、父親に代わるように長女がその姿をカメラの前に現すようになるのだが、そのふたりが主人公なのではない。強いて言えば、家族全員が主人公ということになるのだろうか。この物語は、誰かひとりの視点ではなく、かといって外側からこの家族を見つめるでもなく、家族を構成する5人の、しかし誰のものとは定まらない視線が混在して語られているかのようだ。