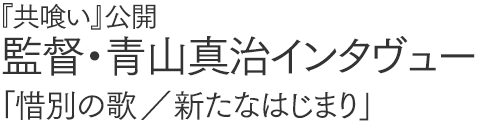――昭和の終わりの時代を舞台とした、父と息子の血をめぐる物語であるこの『共喰い』を見て、やはり『Helpless』(96)をまずは想起させられました。『EUREKA』(00)、『サッド ヴァケイション』(07)を撮られていったあとに、まるで原点に還るかのような作品を撮ったことに、正直に言えば少し戸惑いを感じました。しかし、この『共喰い』はそれらの系譜とはまったく異なる作品であり、青山監督のキャリアの中でもかなり特異な作品であると思います。青山監督が脚本の荒井晴彦さんからこの『共喰い』の原作を薦められてお読みになられたとき、ぜひ自分が監督したいと思ったとインタヴュー記事などで語られていましたが、原作のどういった部分に惹かれたのか、まずはお聞きしたいと思います。

© 田中慎弥/集英社・2013『共喰い』製作委員会
青山真治『Helpless』から見て下さっている人たちには物語が一巡したかのように見えるかもしれないけど、僕としては『サッド ヴァケイション』以降に続く作品だと考えるべきだと思ってて。物語の中の女性が占める割合の大きさ、女性たちの集いや女性たちの語らいのようなものに、あの作品から重きを置くようになって『東京公園』(11)もそういう部分が大きかった作品だった。男が女をとらえる目と、女が男をとらえる目が交錯するようなことを『東京公園』ではやったつもりだから。さらにその延長線として、男の領域から女の領域へと踏み越えていくような、改めて女性たちによってとらえ直される存在としての主人公を描いたのがこの『共喰い』だと思う。
思春期というものがある過程を経て変わっていくのだとしたら、『暗夜行路』じゃないけれども、父権的なものから女性たちとの向き合いの方へ流されるように移行していって、その挙げ句に、いずれ主人公が自分本来の生や生き方を発見していく――そういう流れがこの作品で垣間見えたら良いなと。でも、この作品ではその最後までは描いてなくて、主人公の遠馬(菅田将暉)が女たちに再びとらえられるところで終わる。だからこそ、僕自身がここから先のところへ行くためにも、この田中慎弥さんの『共喰い』をやっておきたいと思ったんです。
――映画の形式の話になりますが、青山監督と荒井さんは「ロマンポルノ」という言葉をこの映画を撮るモチベーションとして語っておられました。結果としてできあがったこの作品は、ジャンル的な枠に収まらない作品だと思っているのですが、この「ロマンポルノ」というタームを青山監督はどのように考えていたのでしょうか?
青山荒井さんとふたりで「日活ロマンポルノみたいなことがやれると良いね」と言っていたのは、ひとつには「昭和の映画」ということだったんだと思う。それはつまり、平成に撮られた映画ではないという意味での昭和の映画。でも平成の映画と言ってもよくわかっていないから、「平成の日本映画って何だよ?」と訊かれても困るけど(笑)。もうひとつは、我々がこの作品に向かうモチベーションとして「日活ロマンポルノ」というタームを出したとき、それはおそらく、プログラム・ピクチャーの速度ということを意味していた。プログラム・ピクチャーを作る速度もそうだけど、特に語りの速度。尺が2時間いかないとか、100分以内に収まるとかね。もちろん、日活ロマンポルノの場合は、大体尺が80分以内で、『共喰い』はそれよりも少し長くなってしまったけど。語りの速度としてのプログラム・ピクチャーを指標としていたから、「ロマンポルノ」という言葉が出てきたんだと思う。そのことは撮影中も編集中も意識していて、もっと速くもっと速くという気持ちで撮ったり繋いでいったりしていたな。
――たしかに、冒頭で遠馬がバスを降りてから町まで歩いていく一連のカットなど、かなり早くカットが切り替わっているように感じました。そういった細部からも、プログラム・ピクチャー的な語りの速さが垣間見えているのかもしれません。
青山そうかもしれないね。もう少し言えば、青春映画のスピードと言えば良いのかな。バスから降りるところは、トニー・リチャードソンの『蜜の味』(61)の冒頭がバスから降りるシーンなんだけど、あんな感じになるといいなと思って撮りました。遠馬が道を歩くところも、何を意識したというわけではないけど、ヌーヴェル・ヴァーグ的な、何かツギハギだらけの感じになれば良いかなと。主人公が歩くスピードとともに町が見えていく。都市ではなくて、人気のない田舎町がね。そこにかなり早口のナレーションが重なる。もしかするとそれはトリュフォー的だと言えるのかもしれないけど、そういう語りの速度のようなものを求めたというのはあった。そのあたりは、昭和の映画、プログラム・ピクチャーとは少し異なるところでもあるのかもしれないけどね。
――ナレーションに関して言えば、青山監督の映画でここまで明確に冒頭と終わりにナレーションによる語りが挿入されている作品はあまりなかったように思えます。そのナレーションの「声」は光石研さんのものですが、「語り手」は昭和の時代が終わってから十何年かが経ち、大人になった遠馬が語っているという設定にされています。たとえばアメリカ映画であれば、そういったナレーションは現在の地点から過去を語る「回想」というかたちとして現れます。エリック・ロスはナレーションを使いながらこと細かい出来事の語り方をしますが、青山監督は以前、そういったエリック・ロス的な語りでは物語が遅くなる、というようなことをお書きになられていたことをいまのお話で思い出しました。

© 田中慎弥/集英社・2013『共喰い』製作委員会
青山つまり、このナレーションは「回想」ではなく、語りの距離感についての問題に関わっているんだと思う。たとえばタバコの吸殻が入っている灰皿がここにあるとして、近くで見ると、いろんな細かいものが見えるんだけど、少し距離を置いてそれを見ると、灰皿だけがあるように見えるという、その距離感。そうすると、この中にはごちゃごちゃといろんなものがありましてね、と語る必要はなくて、ただ吸殻が入った灰皿だけがあると言うだけで良い。その距離感を見つけた気がするし、その距離感によって語りの速度を上げたと言えるのかもしれない。それは大雑把という意味ではないんだけどね(笑)。でも、「あそこに灰皿があった」と一言言うだけで、語りになるようなものを意識していた。
これは一緒にすると怒られるだろうけど、『感情教育』という小説を何年か前に読んだとき、「あれ、こんなに大雑把に書いているのに、ものすごく何かを語っているように見える……」と感じられて。あの小説の中ではかなり長い時間が経過するから、どこそこに行った、誰それに会った、こんな顔してた、残念だった、というようなことがかなり大雑把に羅列されるように思えるんだけど、その方法で終わりのないような時間を語ることができている。トリュフォーは自分はバルザック的だと言うかもしれないけど、僕にはトリュフォーの映画のあの語り方はむしろフローベール的に思える。いま考えてみると、今回の語りは『感情教育』あたりから大きく影響を受けている感じがするな。でも現場では、歩くリズムなどつねにトリュフォー的なものを意識していた。だから、最初は自分でナレーションの声をやってみたんだけど、「下手だ」とスタッフ、殊に荒井さんからNGが出まして(笑)。それで光石さんにお願いしたんだけど、そのときにもやっぱりトリュフォー的なナレーションの在り方は意識してました。
――そういった距離感と関係があるのかもしれませんが、この物語は遠馬の「回想」ないしは「思い出」なのか、それとも遠馬のものですらない何かの「記憶」のようなものなのか、見る側は明確に線引きすることができない印象があります。遠馬が昭和63年を現在としてまさにいま生きている物語にも見える一方で、実は語っているのは遠馬といった特定の人物ではない誰かであるような物語にも見えます。言ってしまえば、日本人というものが忘れていた、あるいは忘れようとしていた「記憶」そのものが、この映画であるかのような感覚があります。それは、昭和天皇の死と、光石研さん演じる円(まどか)という父親の死が二重に語られているからなのかもしれませんが、青山さんご自身は、この物語は誰が見た物語だとお考えですか?
青山さっきの距離感の話からすると、遠馬でさえない、誰でもないようなフラットな日本人――フラットな日本人なんているのかどうかわからないけど――そのものの視点。そういうものの語りというのが、欲求の根っこにあったかもしれない。普通の日本人が普段忘れているようなことをこの映画が語っているように見えれば一番良いんだけど。たとえば、トリュフォーの『恋のエチュード』(71)なら、自分が老いていく様のようなセンチメンタルなものに向かって語られているけど、そういうセンチメンタルな部分を脱色したような語りとして成立しないだろうかと。だからこそ、最初に自分でナレーションをやろうとしていたのは、遠馬のものでもない、円のものでもない、もっと無人称的な記憶の語りを意識していたからで、その距離感というものを今回は探していたんだよね。