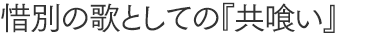――映画の終盤、仁子さん(田中裕子)が刑務所の面会室で、牢屋に入れられているシーンがありますよね。原作はこの面会の場面で終わるのですが、その牢屋のかたちが映画でよく見るような箱型の牢屋ではない。周りをぐるっと鉄格子で囲まれた円形の牢屋なのですが……。
青山あれは美術の清水剛さんのアイディア。あの牢屋の図面を見たとき、「えっ?」って思ったけど、面白いからこれでいこうと。
――どうしても昭和天皇と重なって見えてしまう円を殺した仁子さんが、そのような円形の牢屋に閉じ込められている。これは感想に近いのですが、仁子さんはこの映画の主要な登場人物である一方で、あの牢屋に入れられた彼女は、どこか物語の環から外れる存在になったように思えます。仁子さんが閉じ込められたあの奇妙な場所こそが、何か「外」的なものが垣間見える場、日本人が記憶の彼方に追いやった存在が居る場のような気がするんです。実際、そこで初めて昭和天皇を指す「あの人」という会話が遠馬と仁子さんのあいだで交わされますが、その後、遠馬は何事もなかったかのように元の共同体に戻っていく。
青山以前、別のインタヴューを受けているときに、あの円形の牢屋について、「あれは東京ですか?」と聞いてきた方がいたな。「皇居に仁子さんが居座っているように見える」と。深読みすぎですが、でもそれはそれで面白いなと思った。地方の王を殺して王位に就いた女帝がここにいる(笑)。もちろんそこまではまったく考えてなかったけど、そう見えるのも悪くはないなと。
――それに関連して、この映画でひとつ問題としてあるのは、遠馬たちが生きる「閉じられた共同体」という点です。これまでの青山監督の映画と違って、閉じられた共同体の強固さがむしろこの映画では強調されています。そのために「外部」というものが見えてこない。でも実は、閉じられたこの共同体=円を壊そうとしたが故に、円形に閉ざされた牢屋に入れられてしまう田中裕子さんこそが、遠馬や他の人々に忘れ去られてしまうかもしれない、あるいは、すでに忘れ去ってしまったかもしれない「外部」を背負った存在のような気がします。閉ざされた共同体の中心にこそ「外」があるような。
青山映画芸術誌(444号)で座談会をやったときに、廣瀬純が「ここには斉藤陽一郎みたいな存在がいない」と言っていて、「たしかにそうなんだけどさ」と僕は少しだけ反駁した。もしかしたら、刑務所に入った仁子さんがそういう「外部」みたいなものを垣間見せているのかもしれない、と。たぶん、純が言ったのは、物語の周縁に位置していつも茶々を入れる陽一郎が担っていた外部性のようなものだと思うんだけど、いま言ったような、実は中心にこそ外があるというのがそれに近いような気がするな。鉄格子に囲まれた外。内側にこそ外があるというような見え方。これもあんまり意識はしてないんだけど、でも自分が感じるこの作品の「外部」というものは、たしかに牢屋に入った仁子さんなのかなという気がする。あの座談会を経てから、いまこの作品について考える限りではね。
――もしそうであったとして、中心にこそある「外部」というと、天皇が「外部」なのか?という話になりそうなのですが、とはいえこの映画はそのように撮られているわけでは決してありません。天皇制に言及するということは、たとえば文学の世界では暗黙の了解としてどこかタブー視されていたように思えます。しかし、この『共喰い』では「あの人」という少しぼやかしたような言葉で言い表わされてはいますが、かなり直接的に昭和天皇の死を語るところに踏み込んでいます。

© 田中慎弥/集英社・2013『共喰い』製作委員会
青山あれはぼやかしじゃないんだよね。そこが荒井さんの一番大きな戦略だったと思う。荒井さんが昭和天皇を「あの人」という言葉にしたのは、「天皇」という言葉をここで出したくなかったから。でもテレビのニュースで「天皇」という言葉を使ったから、僕があとで荒井さんに怒られたんだけどさ。というのも、吉本隆明がずっと昭和天皇のことを「あの人」と言っていたことに荒井さんがこだわって、ああいう言い方になっているんです。だから、ぼやかしとかでは決してない。ただ、これは自分の父親や母親の話になるんだけど、僕が子供の頃はああいう言い方は周りで普通にされていたし、祖母も「あの人」というような言い方で言っているのを聞いたことがある。「あの人が死ぬまで死なないよ」と。割と当り前の会話だったから、それをそのまま出しただけなんだよ。昭和の終わりには当り前にああいう会話があって、もし天皇がタブー視されているとしても、だからといって一般庶民のあいだにそういう会話があったということまでは否定できないでしょう。だからタブーを壊したとかそういう気持ちもさらさらない。
――むしろこの映画では、「天皇」は犯してはいけない存在、語りえぬ領域のようなものではまったくなくて、問題はそんなところにはないと逆に明確にしているように思えます。
青山それで良いんじゃないかな。右も左もないような映像としてこの映画を撮ったつもりではある。そしてそれが現在についての映画を作ることだと漠然と感じてる。
――この映画のエンディング曲として、「帰れソレントへ」という民謡を青山監督は選曲されています。町を去ってしまった恋人に帰ってきてほしい、と歌う男の曲なのですが、自分から女を探しに外に出ていくのではなく、あくまでも共同体に留まる者による歌です。それによって、この映画の共同体がさらに強固に閉じられていくように思えますが、むしろそういった閉じられることによってでしか、語ることのできない物語が一方であるのかもしれません。先ほどの仁子さんが「外」的なものを垣間見せるように、篠原友希子さん演じる琴子もあの町を出ていく存在として、また特異な存在だと思います。女性たちの共同体の可能性を見せて終わるこの物語は、青山監督は今後どうなっていくとお考えですか?
青山彼らが今後どうなるかということは、その後の話としてはまったく考えていません。ただ、自分の主題体系としてはこの『共喰い』で、いよいよ女たちの集い・共同体から出られなくなった奴がいるぞとなったから、ではそこからどうするんだというのが、今後の自分が向き合っていく問題。そのための前提をこの作品で表すことができた、というのが自分なりの考えかな。
あの歌は、いま考えるとやっぱり2012年の日本に対する惜別の歌でもあったんだと思う。2012年の日本の現状に別れを告げる歌。共同体に留まる男の歌かもしれないけど、逆説的にそれは、もう俺はここには帰ってこないんだということにもなると思うから。撮影前に自分の母親が死んで、俺が子供の頃に母がよく歌っていたのがあの曲だったから入れたというのもあるんだけどさ。思い返すと、やっぱりここにはもう戻ってこないという自分の意志があった気がする。反戦と反天皇制を説き続けた教員としての母の息子である自分の証しというか。だから、ここに母の墓を建てているわけではないんだけど、そういう惜別の渋みとして、この映画自体が俺にとってはあの歌みたいなものだなと思う。自分としてはいまはそう考えているし、そうすることで、次の段階、次の方向の映画や物語をこれから語っていこうと。それが、この映画を作ったあとの率直な感想。ロカルノ映画祭に行って、まもなく日本の一般公開もされて、さあこれから僕は次の段階に入りますよ、という気持ちにいまはなっているところです。
(2013年8月26日・新宿プリンスホテルにて)
取材・構成:高木佑介
写真:鈴木淳哉(ポートレート)