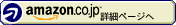『ナンバー・ゼロ』ジャン・ユスターシュ
結城秀勇
[ cinema ]
モノクロ・スタンダードのざらついた画面で、ふたつのカメラ位置が時折切り替わる以外にはほとんど画面上の映像に変化らしい変化が起こらないとさえ言えるこのフィルムを見ていると、にもかかわらず、部分部分でカラーのイメージが思い浮かんだり、動きのある映像が思い浮かんだりする。たとえば、話がペサックの「薔薇の乙女」という祭りに及ぶとき、「ペサックの薔薇の乙女79」に収められたカラー映像の存在はそうした作用に一役買っているのかもしれないし、いじわるな継母がオデットの食器に十字の印をつけて「豚の食器」と呼んだ、などという場面では、特に意味もなく『豚』のあのオーゾンの寒空の下での屠殺が思い浮かびもする。「『ペサックの薔薇の乙女』と『豚』の前二作に見られたすべての要素が、『ナンバー・ゼロ』では祖母の語りを通して撮影されるかのようである」(『評伝ジャン・ユスターシュ 映画は人生のように』須藤健太郎)。オデット・ロベールの語りは、極限まで切り詰められた映像表現の中に、ユスターシュ作品に分かちがたく存在する自伝的要素や伝統を経由して、他の作品で描き出されたイメージすらも召喚する。
というようなことを、2003年にこの作品が初めて日本で上映されたときに思ったのだが、今回改めて見直してみて、それだけでもないよな、とも思った。彼の作品群がある種の小宇宙のようなものを構成するのは間違いないのだとしても、オデットの語りに色彩や運動を感じてしまうのは、彼女の語りそのものが色彩や運動を記述しているからだ。夫の浮気相手の髪はきれいなブロンドだったこと、女たちの髪型、服の柄、生地の質感、透き通る水の底を泳ぐ魚......。しかしふと、まてよ、と。彼女は目が悪いんじゃなかったのか?向かいに座る孫のサングラスと韻を踏むかのようなオデットの黒い眼鏡は、彼女が子供の頃からその目を覆っていたんじゃなかったのか。しかし彼女は、いじわるな継母からの仕打ちを繰り返し嘆いたとしても、たったの一度も、目が悪くて困ったなどとは言わない。
なにも、彼女は本当は見えるのに目が悪いふりをしている、とか、保障手当をもらうための演技なんじゃないか、とか告発したいわけではない。なんとなく「盲目の語り部」という神話的な形容に引きづられて、彼女の"まるで目に浮かぶような語り"が、"実際には目にしていない光景"を語っているのだと勘違いしていたことに気づいただけだ。彼女の語る物語は彼女がたしかに目にしたものであって不思議ではないし、その方が自然だ。だがだからといって、とめどなく溢れるように語られるエピソードの連鎖が、100%彼女の目の前で生き生きと繰り広げられた光景の再現だともやはり思えない。「嘘が多く混じっているので、そこで提示される光景を解釈することが必要になる」、ユスターシュはそう語る。さらには「嘘」かどうかというレベルを超えたところで、語りの技術そのものの問題もある。オデットはバスクの血を引く母方の祖母に物語をよくねだったものだと語る。してみれば、彼女の"見た"もののなかには彼女の祖母が見たものも紛れ込んでいるかもしれず、彼女の語り口にはいわずもがな彼女の祖母の語り口が入り込んでいる。「叙事詩で「兵士」といわず「勇敢な兵士」といい、「王女」といわず「美しい王女」といい、「樫の木」といわず「頑丈な樫の木」というように、老婆はかならず「幸せだった時代」を懐かしみ、「かわいそうな母親」を嘆く。名詞は特定の形容詞と結びつくことで、語り手と聞き手双方の記憶に自然と定着していく」(前掲書)。そうして、一旦は疑っておきながらいつしかまた、オデットが語る、彼女の叔母である「薔薇の乙女」の話を聞きながら、『ペサックの薔薇の乙女』に登場する79年の薔薇の乙女を、68年の薔薇の乙女を、そして歴代の薔薇の乙女たちの面影を、重ねてしまう。
なんのことはない、16年前に見た『ナンバー・ゼロ』とは違った見方をしよう、ユスターシュの「嘘」や倒錯や韜晦の向こう側に行こう、そう試みて結局はまた、なにも知らずに見た16年前と同じ地点からしかこの映画を見れなかったということなのだろう。『評伝ジャン・ユスターシュ』の第二部は「映画は鏡のように」と名付けられている。この本の副題「映画は人生のように」が、ぱっと見そうだよねと納得するような意味とは違う意味で的を射ているように、つまり彼の映画が「自伝的」であるといった通説を越えたところで、その「嘘」や齟齬や韜晦や謎を越えたところで、やはりそれを人生と呼ぶように、私にとって『ナンバー・ゼロ』という映画は鏡のようなものだ。そこにはいまこうある私がではなく、まだ語られることのない物語を前にワクワクしている私が映っている。
「私はノエスという村で生まれた。いまはもうないが、誰もがそこで生まれ死んでいく村」。『評伝ジャン・ユスターシュ』の須藤による訳を読むと、いささか文学的な意訳なのだろうと感じるこのオデットの語り出しの日本語字幕が、それでも私は好きだ。そこからどんな物語でも語れそうな気がする。
アンスティチュ・フランセ「ジャン・ユスターシュ特集 ‐映画は人生のように-」にて上映



 評伝ジャン・ユスターシュ: 映画は人生のように | 須藤 健太郎 |本 | 通販 | Amazon
評伝ジャン・ユスターシュ: 映画は人生のように | 須藤 健太郎 |本 | 通販 | Amazon