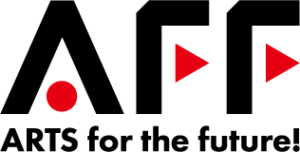『おかしな求婚』エレイン・メイ
佐竹佑海
[ cinema ]
 暗い面持ちのスーツ姿の男性。視線の先には心電図の画面。白衣を着た別の男性も同じ画面を見つめる。波打ち規則的な音を鳴らしていた心電図だが、ふとその波形は崩れ、直線に近づき、不安げな顔が映る。白衣の男たちも心電図を深刻そうな顔で眺める。心電図の波は直線を映し出し、しかし一呼吸おいて「大丈夫です」と言う白衣の男。病院での手に汗握るワンシーンかと思いきや、直後画面に映し出されるのは赤いフェラーリである。これはスーツの男性ヘンリー(ウォルター・マッソー)が愛車の修理を見守る場面だとわかり、その一部始終を見つめる観客は思わず拍子抜けしてしまうだろう。
暗い面持ちのスーツ姿の男性。視線の先には心電図の画面。白衣を着た別の男性も同じ画面を見つめる。波打ち規則的な音を鳴らしていた心電図だが、ふとその波形は崩れ、直線に近づき、不安げな顔が映る。白衣の男たちも心電図を深刻そうな顔で眺める。心電図の波は直線を映し出し、しかし一呼吸おいて「大丈夫です」と言う白衣の男。病院での手に汗握るワンシーンかと思いきや、直後画面に映し出されるのは赤いフェラーリである。これはスーツの男性ヘンリー(ウォルター・マッソー)が愛車の修理を見守る場面だとわかり、その一部始終を見つめる観客は思わず拍子抜けしてしまうだろう。
こうした本作のコミカルさはスクリーンのいたるところに顔を出すが、その最たるものが監督であり、主演を務めるエレイン・メイの素晴らしい演技である。ヘンリーは散財のしすぎで文無しになるが、これといったスキルもない彼は裕福な女性と結婚し、その女性を殺して金を手に入れようと目論む。そんな突拍子もない相手に選ばれたヒロインが、これまた突拍子もないほど不器用な植物学者のヘンリエッタ(エレイン・メイ)である。ヘンリーとの出会いの場となったパーティーの場面で、カメラは基本的にヘンリーの姿を追うが、その背景には部屋の隅でずっとうすら笑みを浮かべるヘンリエッタの姿がぼんやりと映っている。彼女の姿には、まるでコミックに登場するデフォルメされたキャラクターをそのまま実写化したかのような可笑しさがある。レンズの大きな眼鏡はいつも安定せず、細い手で掛け直しては顔の一部にかろうじてぶら下がっている程度。カップを持てば手からすり抜け落ちてしまい、中身を白いカーペットにぶちまける。服のボタンはどこかが外れていて、ギリシャの伝統的な服に袖を通してみれば、腕と首の穴を間違えた変な着方のままで過ごしてしまう始末。裕福だからなのか変わり者が故に周囲から孤立していたヘンリエッタは、ヘンリーにとって最適なターゲットだった。彼はかろうじて持っていた植物学の知識をネタに会話を膨らませ、彼女がドジをすればこれ以上なく紳士な態度でフォローをする。例えば、パーティーで高級なカーペットに紅茶を2度もこぼしたヘンリエッタは、大勢の前でホストの夫人に叱責される。同じパーティにたまたま参加していたヘンリーは彼女を庇い、自分もわざとカーペットの上でカップを逆さまにして中身をこぼす。そしてすかさずヘンリエッタを車で送ろうとエスコートする。まるでお金目当てに結婚相手を探している人間とは思えないほどに男らしい態度である。自分の好きなことに関心を示してくれて、紳士的な態度でヘンリエッタの欠点も肯定してくれるヘンリーに、彼女は見事に口説き落とされてしまうのだった。
まわりからは変人扱いされ距離を置かれている彼女だが、物語が進みヘンリーへの愛情を深めるにつれて、ヘンリエッタの可愛らしさがスクリーン上に溢れてくる。劇中ではヘンリエッタが画面の下方に、ヘンリーが上方に位置する構図が多いが、その際の眼鏡の上から覗く彼女の上目遣いとその視線の真っ直ぐさがたまらない。そしてヘンリーを信頼し、彼の言葉を遠慮がちに受けながらも素直に受け入れ、「貴方は私に自信を持たせてくれる人」と彼に感謝を述べながら、ヘンリーの才能を生かす場を取り持とうとする姿はとても健気で愛おしい。
ロマンチック・コメディはユーモアとロマンスによる物語の緩急にほかならない。したがって、ヘンリエッタの可笑しさや愛らしさは物語のロマンスな側面を増やすとともに、それが結果としてコメディ映画としての側面をさらに際立たせる。俳優として、監督として、ロマンチック・コメディの傑作を製作することに寄与したエレイン・メイは、まぎれもなく幸福を生み出すシネアストである。
特集上映「70ー80年代アメリカに触れる! 名作映画鑑賞会 in 京都みなみ会館」にて上映