レオス・カラックス×黒沢清 スペシャルトークショー 2025/3/23@東京日仏学院 後編
[ cinema ]
AS タバコ休憩に行かれましたが、すぐ戻ってくると思います。後半は会場のみなさまからの質問もお受けしたいと思います。さて、レオスのパリ、あるいは東京というのは、レオスのイリュージョンなのかもしれませんが、逆にとても現実感があるように感じます。今日『TOKYO!』を久しぶりに見て、やはり「東京が映っているな」とも思わずにはいられませんでした。
KK そうですよね。レオスはかなり最初の段階から銀座や渋谷の歩道橋で撮影したいと言っていて、私は「絶対に無理!横浜ならどうにかなるかもしれないけど......」と伝えたのですが、彼はとてもこだわっていた。でも、まさにそこで撮影をしていましたね。
AS あの渋谷の歩道橋はいま、もっとごちゃごちゃになっているじゃないですか。
KK いまは中途半端に途切れたり、改築中なのでしょうけどね。
AS その変わる前の歩道橋を、渋谷を撮った映画っていうのは、ほとんどないのではないですか。
KK 『メルド』だけだと思います。大昔は分かりませんが、近年の日本映画業界で「渋谷は絶対撮影不可能」と言われてますからね。それはどういう意味かというと、警察ではない怖い方たちが来るということです。私が自主制作映画を撮っていても、「ちょっと何してるの?」ってすごく怖そうな人たちが実際に来ました。なので、許可を取る、取らない以前に「渋谷は無理」というのが業界の常識でしたね。ここだけの話ですが、レオスが渋谷の歩道橋で撮影したあと、制作部は大変だったようです。撮れはしたのですが、その後のさまざまな処理が色々と。
話は変わりますが、近年は私もパリに頻繁にいくようになり、ポンヌフ橋とサマリテーヌ・デパートを見るたびに、ここがパリの中心だ、という感じがしていました。きっとそれは、レオスの『ポンヌフの恋人』を見たからなのでしょうね。なので、『ホーリー・モーターズ』を見たときも、またレオスがパリらしいパリで撮影をしている、という風に思ったのですが、これもレオスに洗脳されていただけなのかもしれません。
AS そうなのかもしれませんね。(レオスが舞台に戻ってくる)おかえりなさいませ。
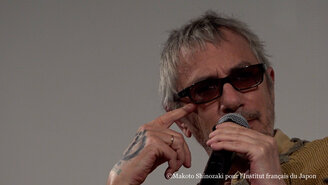 LC 東京にしろパリにしろ、何かしらのリアリティを見てもらえればと思っています。でもいまは大きい都市は、やはりお金というファンタジーを求めたり、観光客のものになってきています。昔はここが中心だなという感じがありました。ニューヨークでも東京でも、私は旅をするのが好きです。いま私はパリに住んでいるわけですが、そのサマリテーヌというのは、おそらくパリでも最初の方にできた大きな百貨店のひとつです。最初にできた時、たくさんのフロアがあって階段も美しくて、たくさんの女性が働いている場所でした。ですが20年くらい前でしょうか、おそらく安全上の理由で閉店しまして、そしてみんな解雇された。それはパリの中心にあってもそうなのですが、お金が欲しいということで、新しい人に売って、新しくお店になったりホテルになったりした。本当にお金持ちのため、観光客のための場所になってしまったのです。
LC 東京にしろパリにしろ、何かしらのリアリティを見てもらえればと思っています。でもいまは大きい都市は、やはりお金というファンタジーを求めたり、観光客のものになってきています。昔はここが中心だなという感じがありました。ニューヨークでも東京でも、私は旅をするのが好きです。いま私はパリに住んでいるわけですが、そのサマリテーヌというのは、おそらくパリでも最初の方にできた大きな百貨店のひとつです。最初にできた時、たくさんのフロアがあって階段も美しくて、たくさんの女性が働いている場所でした。ですが20年くらい前でしょうか、おそらく安全上の理由で閉店しまして、そしてみんな解雇された。それはパリの中心にあってもそうなのですが、お金が欲しいということで、新しい人に売って、新しくお店になったりホテルになったりした。本当にお金持ちのため、観光客のための場所になってしまったのです。
AS それでは会場からもご質問や感想を。
質問者1 貴重なお話をありがとうございます。カラックス監督にお訊きしたいのですが、さきほど映画を作るうえで何か怒りのようなものが溜まっていると仰っていたと思います。最近の作品を見ると、『ポーラX』(1999年)の時よりも何か怒りだけではないものも入っているのかなと思いました。
LC 人生の残り時間が少ないということもあると思います。あと、若い時に見ていた映画が、リズムが変わってきたからなのかわからないですが、いまは好きじゃなくなってしまった。映画だけではなく、世界との関わり方も変わってきています。独り身の時であれば何でもできるわけです。明日死んでもいいし、戦争に行ってもいいし、まったく人生を変えてもいい。何も考えずにすべてを忘れて映画のためだけに3年費やすこともできます。しかし、子どもがいるとまた違う。自分がこの世界を去ったとしても、自分の娘はこれからも生きていく。それはかなり重いことです。これがお答えになっているかどうかわからないですが。
質問者2 ぜひおふたりにゴダールの影響を伺いたいです。『IT'S NOT ME』はフォーマットとしてはゴダールの『映画史』などを参照にしつつ、内容はまったく違う。ゴダールとは違うことをカラックス監督は意識的にやられたんだと思います。いろいろなインタビューを拝読すると、黒沢さんもゴダール作品をリアルタイムでご覧になってきて、すごいと思いつつ、だからこそもっと違うことをやろうとしたという話を何度もされております。私はリアルタイムではゴダール作品を見ていないので、それらをリアルタイムで見て、そして映画監督になったおふたりは、ゴダールからどのような影響を受けたのでしょう。
 KK 私からお答えいたしましょう。ジャン=リュック・ゴダールと言っても、いろんな時期のゴダールがいるので、様々な面で影響を受けていることは間違いありません。ひとつ明らかに影響を受けていると思うのは、編集をする時ですね。あるカットとあるカットを繋げようとした時に、「これは繋がっていないのだ」ということを自覚しながら繋げています。絶対に繋がっていないものを繋げている、というのが編集なんだなと。綺麗に繋げることもできるのですが、繋がっていないまったく違うものがそこに続くのだ、それが積み重なってひとつの映画になるのだということを必ずどこかで意識しています。商業映画の世界ではどうやって繋げるかということがいつも話題になるのですが、「いや繋がっていない」と私がいつも意識しているのはなぜだろうと、「あ、ゴダールを見たからだな」という自覚があります。
KK 私からお答えいたしましょう。ジャン=リュック・ゴダールと言っても、いろんな時期のゴダールがいるので、様々な面で影響を受けていることは間違いありません。ひとつ明らかに影響を受けていると思うのは、編集をする時ですね。あるカットとあるカットを繋げようとした時に、「これは繋がっていないのだ」ということを自覚しながら繋げています。絶対に繋がっていないものを繋げている、というのが編集なんだなと。綺麗に繋げることもできるのですが、繋がっていないまったく違うものがそこに続くのだ、それが積み重なってひとつの映画になるのだということを必ずどこかで意識しています。商業映画の世界ではどうやって繋げるかということがいつも話題になるのですが、「いや繋がっていない」と私がいつも意識しているのはなぜだろうと、「あ、ゴダールを見たからだな」という自覚があります。
LC キヨシが仰っていたように、映画の重要性は綺麗に繋げるというところにはありません。カットが急に変わったり、すごく暴力的なところさえあるとゴダールは教えてくれました。
ゴダールは、20世紀から21世紀にかけての奇妙な時の流れを掴んでいたように思います。少し遡れば私が映画を撮り始めたのは70年代後半なのですが、その当時、シネマというものは人々の人生にとって、もっと重要なものでした。いまはあまりそうではありません。かつてみんなにとってシネマが重要だったのは、もしかしたらゴダールが言わずして、つまり、さまざまな運動を作り、映画を重要なものにしていたからです。彼がシネマの大切さを語らずして体現していた。
私自身は戦後15年ほど経って生まれました。もう絶対戦争には戻りたくないと思っていましたし、みんなもそう思っていたわけです。そのような今日の人が考えるような、ここに至るまでの考え方や哲学は、今回私がつくった小さな映画『IT'S NOT ME』に反映されています。そして、これは初めて自分一人で編集した映画でもあります。その編集をしている間に、ゴダールは自らの命を絶つという決断をしました。
AS もう時間が経ってきたので、最後の質問にしたいと思います。『IT'S NOT ME』で「アートの子供時代 enfance de l'art」という言葉が出てくる。それをどうすれば救えるのか、映画の中でレオスはそう自問しているように感じました。19世紀の産物である映画は、20世紀になって二つの戦争を経ました。そして21世紀になり、資本主義社会の中で再び戦争が起こってきているいま、「アートの子供時代」をどのように見出していけるのか。そしてそのことで映画を、世界を救うことができるのでしょうか?
LC 私は映画作りに関してペシミスティックになっています。映画は世代によって作り替えられてきました。また、世界ではすべてのことが変わり続けています。そういう意味では非常に大変だなと思う。映画は、先ほども言いましたけれど、今日においては以前よりも重要ではなくなってきている。それは映画だけではなく、本もそうですが、いろいろなことがあまり重要ではなくなってきています。今日における新しい課題は、シネマを作り直すことではありません。アビと一緒に鎌倉に行って、その時に小津の墓に行きました。小津の墓にはたくさんのお酒が置いてあり、その中に無という漢字があった。たぶん小津が言ったことだと思うのですが、私が17歳くらいの時に聞いた言葉で、「ふたつの視線のあいだに目を洗う」ということを言っていました【1】。しかし、いまそれはできていません。我々はつねに目を開けっぱなしでなければいけない。これが大きな問題です。映画が新しくなるかどうかということについては、私はあまり心配していません。私が心配しているのは、人々がものを見ることができなくなってしまうことです。
 KK レオスの口から小津の名前が出るというのは、軽い驚きと喜びがありますね。やはり映画の価値は下がりつつあるのかもしれませんが、でもたかが百数十年しか経っていない芸術ですから、今後どうなるかはわかりません。一方にゴダールがいて、一方に小津がいる。映画ってそれを考えただけでもすごいなと単純に思いました。その真ん中にレオスがいるのかもしれませんね。
KK レオスの口から小津の名前が出るというのは、軽い驚きと喜びがありますね。やはり映画の価値は下がりつつあるのかもしれませんが、でもたかが百数十年しか経っていない芸術ですから、今後どうなるかはわかりません。一方にゴダールがいて、一方に小津がいる。映画ってそれを考えただけでもすごいなと単純に思いました。その真ん中にレオスがいるのかもしれませんね。
AS 黒沢さんもいます。
KK 私はまあ端っこの方にいます。こんな変なまとめ方ですが(笑)
【1】小津ではなく溝口健二の言葉からの引用だと思われるが、カラックス監督の記憶の仕方を重視し、そのままにした。このことに関しては以下のサイトが詳しい。「更新:レオス・カラックスが引用した小津安二郎(ではなく溝口健二)の言葉」(最終アクセス2025年4月26日)


